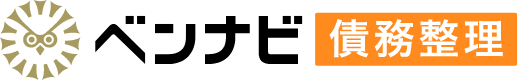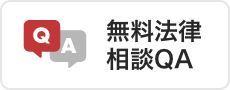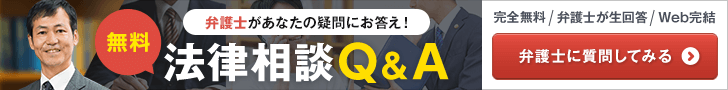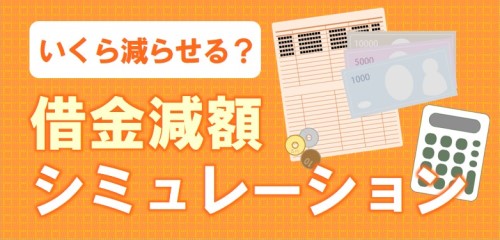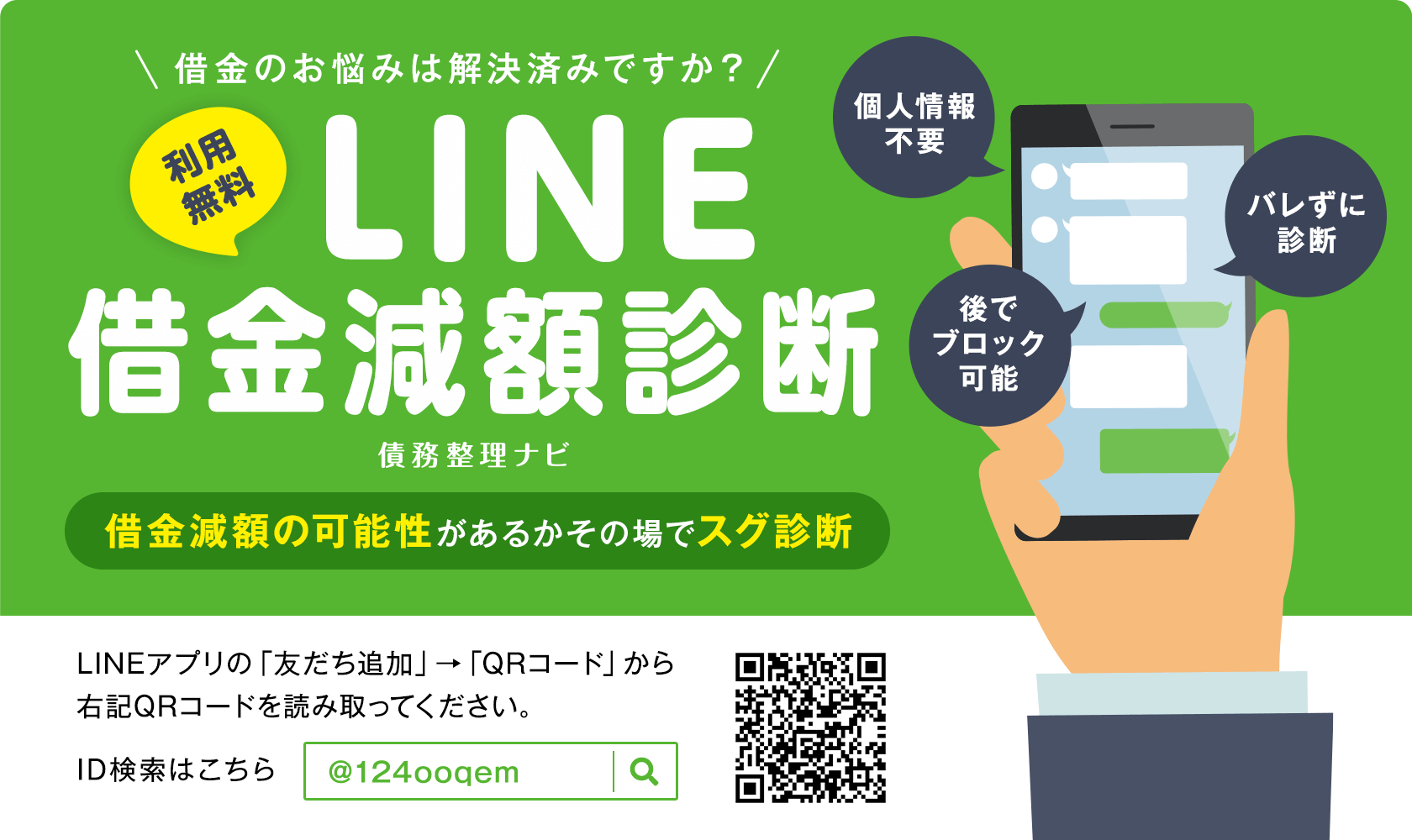個人再生について相談できる窓口は?個人再生の条件や弁護士費用も解説


この記事では、
- 個人再生について相談できる無料窓口
- 個人再生の特徴・メリット・デメリット
- 住宅ローン特則
- 個人再生ができる条件
- 個人再生が適しているケース
- 個人再生を依頼する際の費用
- 個人再生の途中で自己破産に変更できるかなどの個人再生に関するQ&A
をご紹介しています。
また、東京・横浜・福岡・札幌をはじめとして全国の弁護士事務所も掲載しています。相談時に必要な情報や書類などもご紹介しているので、相談先を探している方だけでなく、相談先が決まっている方も一読されるとよいかもしれません。

無料相談できる弁護士一覧
個人再生について相談できる窓口・機関・相談方法

以下では、個人再生について相談できる無料窓口をご紹介しています。
相談は、可能な限り早く行うことを推奨します。早く相談した分、債務整理に着手するまでの時間を短縮でき、遅延損害金などの余分な債務の発生を防げるからです。逆に、相談を引き延ばしてなかなか債務整理に手を打たないでいると、債務が膨れ上がってしまう可能性があります。早めに相談して、債務整理を行いましょう。
ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)
当サイトでは、債務整理を得意とする弁護士/司法書士を多数掲載し、累計相談数は約14,000件以上に上ります。相談すると、実際に依頼した場合の費用を提示してもらうことも可能です。まずはお気軽にご相談ください。
法テラス
法テラスの正式名称は『日本司法支援センター』で、国が設立した法律支援団体です。法テラスには、弁護士/司法書士が在籍しており、一般の人から寄せられる法的トラブルを解決するために、情報やサービスを提供していています。
[対応]
電話・メール
[受付時間]
電話:平日9~21時・土曜9時~17時
メール:24時間
日本弁護士連合会
日本弁護士連合会は、日本全国の弁護士が登録している弁護士法人で、HPでは全国の法律相談センターを紹介しています。各法律相談センターのHPにアクセスすると、電話やネットで相談申し込みができ、予約した日に弁護士に面会して相談することが可能です。相談申し込みをする際は、氏名、連絡先、相談内容、面談日時、相談場所を伝えます。
相談方法やダイヤルの受付時間は、弁護士会によって異なるので、日本弁護士連合会のHPから各弁護士会のHPにアクセスしてお確かめください。
生活困窮者自立支援制度
生活全般にわたる、困りごとの相談窓口を各地方公共団体が提供してます。居住地域ごとに相談できるセンターが変わってきますので、まずはHPで確認しましょう。
主な受付方法は電話・メール ・インターネットです。受付方法や受付時間はセンターによって異なります。
窓口一覧:自立相談支援機関窓口情報(令和2年5月25日情報)
消費生活センター
消費生活センターは、商品やサービスなどの生活全般に関する苦情や問い合わせを受け付けている窓口で、各地方公共団体が設置しています。対象となる相談者は、原則としてその自治体に在住、在勤、在学している消費者です。
受付方法や受付時間は各消費者センターによって異なるので、各消費生活センターのHPで確かめてください。
国民生活センター
国民生活センターでは、全国の消費生活センターへの案内を行っていますが、消費生活センターが開いていない土・日曜、祝日や、消費生活センターに電話がつながらないときなどには相談も受け付け付けています。主に商品やサービスなどに関する苦情や問合せなどを受け付けていますが、多重債務やクレジットカードの使い過ぎなどの相談にも対応しています。
[対応]
電話
[受付時間]
平日:午前10時~12時・午後13時~16時
土日祝:午前10時〜午後4時
その他
上記のほかに個人再生について相談できる窓口として、下記があります。
財務局
全国クレサラ金被害連絡協議会
日本クレジットカウンセリング協会
日本司法書士会連合会
個人再生の特徴・利用できる条件
個人再生は、任意整理と自己破産の中間の債務整理です。法的に債務を削減することができたり、住宅を手放さずに済んだりするという特徴があります。
個人再生を行えるのは、債務の総額が5,000万円以下の方です。また、個人再生には、小規模個人再生と給与所得者再生の2種類あり、それぞれ行える条件と債務の返済額が異なります。
小規模個人再生
小規模個人再生は、個人再生の基本的な手続きです。最低弁済額※と所有する財産の総額のどちらか金額の多い方を返済額とします。例えば、最低弁済額が500万円で、所有する財産の総額が550万円である場合、最低弁済額は550万円になります。小規模個人再生では、債権者が再生計画案を作成します。
※最低弁済額とは、最低限支払わなければならない金額のことです。下記「メリット②債務を大幅に削減できる」で、最低弁済額の具体的な金額をご提示しています。
小規模個人再生が利用できる条件
- 将来において、継続した収入が見込まれること
- 借金の総額が5,000万円を超えないこと
給与所得者再生
最低弁済額と、所有する財産の総額、過去2年分の手取り収入のなかで、一番金額が多いものを返済額とします。給与所得者再生では、裁判所が債権者の意見を聴収して再生計画案を作成します。
給与所得者再生が利用できる条件
- 給与などの定期的な収入を得られる見込みがあること
- その収入の変動が小さいと見込まれること
給与所得者再生の条件を満たしているならば、同時に小規模個人再生の条件も満たしていることになるので、給与所得者再生と小規模個人再生のどちらも選択することができます。選択の基準は「給与に変動があるかないか」です。例えば、収入があっても給料が歩合制で変動が激しい場合などは、小規模個人再生が適していると考えられます。
個人再生のメリット・デメリット
個人再生の主なメリット・デメリットは下記です。
メリット①住宅ローン特則で住宅を残せる
個人再生では、『住宅ローン特則(住宅資金特別条項)』を利用することで、住宅の所有を続けられます。住宅ローン特則とは、延滞した分の住宅ローンの返済を延期することで、住宅を所有し続けることができる制度です。ただし、住宅ローンが減額されることは基本的にありません。住宅ローンは基本的に3年~5年、最長で10年かけて分割払いします。
住宅ローン特則は、小規模個人再生と給与所得者再生のどちらでも利用できます。
住宅ローン特則を利用できる条件
住宅ローン特則を利用できる条件については、下記の記事で詳述していますのでご覧ください。
メリット②債務を大幅に削減できる
個人再生では、債務の一部を免除できます。削減できる債務額は下記の通りです。
|
借金額 (住宅ローンを除くすべての借金の総額) |
最低弁済額 (最低返済額) |
|
100万円未満 |
借金全額 |
|
100万円~500万円未満 |
100万円 |
|
500万円~1,500万円未満 |
借金額の5分の1 |
|
1,500万円~3,000万円未満 |
300万円 |
|
3,000万円~5,000万円 |
借金額の10分の1 |
注意点ですが、所有する財産の合計額が最低弁済額を超えている場合は、財産を現金化し、全額返済に充当しなければなりません。例えば、最低弁済額が100万円の場合は、100万円以上の財産は現金化して返済に充当します。
デメリット①ローンの組み立てとクレジットカードの作成・利用が不可能に
個人再生を行うと、約5年間はローンの組み立てやクレジットカードの作成・利用ができなくなります。信用情報機関に個人情報が登録されることで、ローンや新規クレジットカードの審査に通らなくなるからです。5年が経ち、信用情報機関から個人情報が削除されると、ローンの組み立てやクレジットカードの作成が可能になります。
デメリット②連帯保証人への影響が大きい
原則として、個人再生により債務を削減できるのは、個人再生を申し立てた本人のみです。申立人が債務整理を行っても、連帯保証人の保証義務は影響を受けません。そのため、申立人について債務圧縮がされても、連帯保証人は自身の保証債務にしたがって債務全額を返済する義務を負うことになります)なお、申立人が弁済した分については保証債務も消滅します)。
連帯保証人も個人再生を行うことで、債務を削減できますが、その場合は、連帯保証人もローンの組み立てやクレジットカードの作成・利用ができなくなります。
個人再生に適したケースとは
個人再生以外にも、債務を整理する方法はありますが、個人再生が適しているのは、下記2つの条件に当てはまるケースです。
住宅を残したい
上記「メリット①住宅ローン特則で住宅を残せる」で既述した通り、個人再生では自己破産と異なり、住宅を残すことができます。任意整理でも住宅を残すことは可能ですが、その場合は住宅ローンを避けて債務を整理しなければならないので、通常通り住宅ローンを返済していかなければなりません。
収入があり債務を返済していける
上記「個人再生の特徴・利用できる条件」でも既述した通り、個人再生をして債務を大幅に削減しても、残った債務は返済していかなければなりません。
よって、個人再生が行える条件は、残った債務を返済できるだけの収入があることと定められています。
個人再生に関するよくある相談
以下では、個人再生を相談しようとしている方からしばしば寄せられる質問をご紹介しています。
無料相談ではどんなことを聞かれますか?
下表は、無料相談でよく聞かれる事項です。
|
債務の借り入れ先 |
全ての借り入れ先を聞かれるので、借り入れ先を一覧にしておくと便利 下記で債権者一覧をダウンロード可能 債権者一覧表(「破産・免責申立」項目内の「債権者一覧表」) |
|
債務の総額 |
債務整理を選択するうえで判断材料になる |
|
取引期間 |
取引期間によっては、過払い金が発生している可能性がある 取引明細があると便利 |
|
借金をした理由 |
借金をした理由によっては、実施できない債務整理がある |
|
1ヶ月の収入と返済可能な金額 |
債務整理を選択するうえで判断材料になる |
|
所有している財産 |
個人再生後に、削減した債務額以上の財産は現金化しなければいけないため |
個人再生について無料相談するとき用意するものは?
下表は、無料相談をするときに用意すると望ましいものです。身分証明証以外は必須ではありませんが、用意すると相談内容を具体的に伝えることができます。
|
身分証明証 |
運転免許証やパスポートなど本人確認ができるもの |
|
収入に関する書類 |
給与明細や所得証明書など収入がわかる書類 |
|
取引明細 |
過払い金請求でも必要ない場合は、下記「取引明細がない場合」を参照 |
|
債権者一覧表 |
あると便利。下記でダウンロード可能 債権者一覧表(「破産・免責申立」項目内の「債権者一覧表」) |
|
印鑑 |
無料相談後に、弁護士/司法書士とそのまま契約を結ぶことになれば必要 |
|
財産に関する書類 |
不動産の登記簿謄本や保険証券、車の車検証など |
|
督促状・訴状など |
債務整理が緊喫の課題であることを示し、債務整理を選ぶ際の判断材料になる |
|
財産に関する書類 |
保険証券、車の車検証など |
取引明細がない場合
取引明細が手元にない場合は、取引をした貸金業者に問い合わせれば、取引履歴を開示してもらえます。どこの貸金業者と取引をしたか忘れてしまった場合は、個人信用情報機関に問い合わせれば、取引をした貸金業者を知ることができます。
主な信用情報機関は以下です。
相談するときは窓口と弁護士/司法書士のどちらを選べばいいの?
窓口よりも弁護士/司法書士がおすすめ
無料相談をするなら断然、弁護士/司法書士を推奨します。弁護士/司法書士に相談すると、相談後にそのまま個人再生を依頼することができるからです。一方で、無料相談窓口に相談すると、窓口でアドバイスをもらってから、依頼する弁護士/司法書士を探さなくてはいけないので、二度手間になります。
多くの弁護士/司法書士が、無料相談後に依頼した場合の費用を提示してくれますし、無料相談をしたからといって必ずしも依頼する必要はないので、気軽に弁護士/司法書士に相談してみてください。
手続の代理は弁護士へ
個人再生のような法的手続きを行いたいのであれば、相談をする方は、弁護士に相談しましょう。司法書士は、このような法的債務整理手続きを代理することはできません。

無料相談できる弁護士一覧
個人再生を依頼すると費用はどのくらいかかるの?
専門家費用の相場は以下です。ただし、依頼費は依頼する弁護士の報酬基準や債務額により変動します。
- 弁護士の費用相場:約40~60万円
個人再生にはどれくらいの期間がかかるの?
個人再生の申し立てから確定までは、約4~6ヶ月かかると言われています。ただし、確定までにかかる期間は、依頼する弁護士や債務額により変動します。
なんで相談が無料なの?
多くの機関が、無料で債務整理を受け付けているのには理由があります。無料相談を受け付けると、報酬がもらえるシステムがあるためです。例えば、法テラスでは、在籍している弁護士や司法書士は、相談を受けると法テラスから報酬をもらえます。法テラスは国立の機関なので、報酬は税金から出金されています。個人が経営している事務所では、無料相談を受け付けそのまま契約に至ると、相談者から報酬金などの費用をもらえます。
つまり、相談を無料で受け付けても、相談側は報酬がもらえるシステムがあるので、無料相談が実施されているというわけです。
連帯保証人がいる場合はどうなるの?
上記「デメリット②連帯保証人への影響が大きい」で既述した通り、連帯保証人は主債務者の個人再生の恩恵を受けることはできません。なお、連帯保証人自身も個人再生をした場合は、連帯保証人もローンの組み立てやクレジットカードの作成・利用ができなくなります。
過払い金請求をしながら個人再生をすることは可能?
可能です。過払い金請求で返還してもらったお金は債務の返済に充てることになります。なお、過払い金額が高額である場合は、個人再生ではなく任意整理を選択することも検討に値します。
過払い金の計算方法については、下記の記事をご覧ください。
その他よくある個人再生Q&A
上記以外にも、個人再生に関して頻出する質問をご紹介します。この他に疑問がある場合は、個人再生を相談する際に窓口や弁護士にお尋ねください。
- 個人再生では、債務を作った経緯は問われません。
- 相談後に必ず依頼する必要はありません。複数の弁護士に相談してから依頼先を決めましょう。
- 変更することはできますが、手間や費用がかかるため、はじめから適切な債務整理を行うことが重要です。
- 官報には名前が掲載されますが、一般の人が官報を読むことは稀です。
- 個人再生手続きでも一定の範囲で財産は換価処分が必要となる場合もあります。
まとめ
個人再生について無料で相談できる窓口や弁護士は無数に存在します。個人再生の場合は弁護士に相談するのが得策だとお伝えしました。
弁護士に相談する際に必要な情報や持ち物もご紹介したので、ぜひご参考ください。
早めに相談し個人再生に着手すれば、その分早く返済に苦しむ生活から解放されます。逆に、相談せずに債務整理を延期すると、債務が膨らんでますます貧窮するという悪循環に陥る恐れがあります。
早く相談して、債務を削減し、さらに貧窮するリスクを回避しませんか?

無料相談できる弁護士一覧

【初回相談30分無料】年間100件以上!の対応実績◎支払いの督促が来た/返済しきれず限界を感じているなど、早めにご相談ください!◆依頼者目線の丁寧かつ的確な対応には自信がございます【詳細は写真をクリック!】
事務所詳細を見る
【全国65拠点以上】【法律相談実績90万人以上】【周りに知られずに相談OK】はじめの一歩は弁護士への無料相談!あなたの街のアディーレに、何でもお気軽にご相談ください
事務所詳細を見る
【初回面談0円|来所不要】「家族や周囲にバレずに借金を解決したい」「督促の電話を早く止めたい」「借金を返すために借金をする生活から抜け出したい」そんな方は当事務所へ|借金問題の解決実績は累計500件以上!
事務所詳細を見る当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

個人再生に関する新着コラム
-
ベンナビ債務整理では、個人再生に強い弁護士に無料で電話相談ができます。47都道府県全国からの相談に対応。個人再生に強い弁護士に無料相談する方法・窓口...
-
個人再生後は、基本的に住宅ローンをはじめとするローン商品は利用できません。しかし、5〜10年程度経過すれば、信用情報機関のブラックリストから削除され...
-
不景気といわれている現代でも、住宅ローンを組まれる家庭は多くいらっしゃいます。住宅ローンは、何十年の長い期間で返済する高額なローンのため、少しでも返...
-
借金の返済が重荷になった時の法的債務整理の一つに個人再生があります。実は個人再生後でもスマホや携帯を今まで通り利用する方法がありますのでそれについて...
-
個人再生が失敗するケースは全体の3%程度と少ないですが、万が一に備えて不備なく手続きを済ませるポイントを押さえておきましょう。本記事では、個人再生が...
-
小規模個人再生とはどのような債務整理なのか、特徴や条件、再生計画案が認可される要件などを給与所得者等再生と比較しつつご紹介します。
-
返済に困って個人再生をしたいのに、費用が高すぎて申立てができないという悩みを抱える方はたくさんいます。本記事では、弁護士費用に不安を感じる方のために...
-
個人再生を含む債務整理は、家族に内緒で申し立てることができます。しかし、状況によっては大きな財産(車など)を処分する必要もでてきますので、内緒で行う...
-
任意整理後、あなたの代わりに弁護士・司法書士事務所が代わりに返済を行う返済代行という方法があります。返済代行にはメリットもあればデメリットもあること...
-
今回は個人再生をした後に自己破産を行った方に話を聞きました。個人再生をしてから自己破産に至るまでの経緯や、奥さんにばれずに自己破産をした方法など貴重...
個人再生に関する人気コラム
-
個人再生後は、数年間クレジットカードを発行できなくなります。ただ、カードの種類によっては発行できますし、一定の期間後は、再び発行することができます。...
-
個人再生が失敗するケースは全体の3%程度と少ないですが、万が一に備えて不備なく手続きを済ませるポイントを押さえておきましょう。本記事では、個人再生が...
-
個人再生は裁判所を介して借金の返済計画手続きを申立てることで借金を大幅に減額することができますが、一方で、車を手放すことになるとも言われています。本...
-
個人再生を行うと金融事故情報として公的な書類である官報に掲載されます。これを俗に「ブラックリストに載る」と言われていますが、具体的にどのくらいの期間...
-
これから個人再生を申し立てる方に向けて、必要な提出書類から書類の準備・作成方法についてまとめました。この記事を見ていただくことで、個人再生申立てに必...
-
時効の援用をすることで、時効が成立し借金の返済義務が消滅します。ただ誰でも利用できるわけではありません。この記事では、時効を狙っている人や時効間近の...
-
個人再生で失敗するリスクを減らすために、やってはいけないことや失敗例、個人再生など債務整理の得意な弁護士の選び方を解説します。
-
個人再生では家計簿を提出します。この記事では、家計簿を提出する理由、いつからいつまで書くのか、家計簿の作成方法・注意点、裁判所のチェックポイント、家...
-
個人再生をするためには、2つの条件を満たす必要があります。この記事では、個人再生できる条件や、収入状況別(バイトや年金など)に個人再生を利用できるか...
-
返済に困って個人再生をしたいのに、費用が高すぎて申立てができないという悩みを抱える方はたくさんいます。本記事では、弁護士費用に不安を感じる方のために...
個人再生の関連コラム
-
個人再生の最低弁済額(最低限返済する金額)は、借金の総額やあなたが所持している総資産額によって変わてきます。この記事では、どのように最低弁済額が決ま...
-
個人再生を含む債務整理は、家族に内緒で申し立てることができます。しかし、状況によっては大きな財産(車など)を処分する必要もでてきますので、内緒で行う...
-
借金完済は、債務者にとっての目標であり夢です。今もなお借金完済を目指して奮闘している人も多くいらっしゃることでしょう。しかしただやみくもに頑張ろうと...
-
不景気といわれている現代でも、住宅ローンを組まれる家庭は多くいらっしゃいます。住宅ローンは、何十年の長い期間で返済する高額なローンのため、少しでも返...
-
個人再生をしても、基本的に会社にバレることはありません。しかし、本記事で紹介する4つのパターンに該当する場合、バレてしまう可能性があります。本記事で...
-
給与所得者等再生とは、主にサラリーマンが対象の個人再生です。利用条件が小規模個人再生より厳しいですが、債権者の同意が必要ないため多くの債権者が反対し...
-
個人再生では、基本的に個人再生委員が選任されます。個人再生委員は、再生計画案の認可を左右する重要な役割を担っています。この記事では、具体的な役割や選...
-
個人再生は裁判所を介して借金の返済計画手続きを申立てることで借金を大幅に減額することができますが、一方で、車を手放すことになるとも言われています。本...
-
一度個人再生を行っていても、2回目の個人再生を申し立てることは可能です。しかし、1回目とは違い、いくつか注意すべきポイントがあります。2回目の個人再...
-
個人再生は司法書士、弁護士どちらに依頼すべきか悩んでいる人も、この記事を読むことで、あなたがどちらの専門家に依頼すべきか判断できるかと思います。司法...
-
小規模個人再生とはどのような債務整理なのか、特徴や条件、再生計画案が認可される要件などを給与所得者等再生と比較しつつご紹介します。
-
個人再生を行うと、保証人・連帯保証人が残りの借金を一括(分割)返済しなくてはならなくなります。この記事では、保証人と連帯保証人の違い、個人再生が保証...
弁護士・司法書士があなたの借金返済をサポート
債務整理では、債権者と交渉する任意整理や法的に借金を減額する、個人再生や自己破産などがあります。また、過去の過払い金がある方は、過払い請求を行うことも可能です。
ただ、どれもある程度の法的な知識や交渉力が必要になってきます。債務整理をしたくてもなかなか踏み切れないあなたをベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)の弁護士・司法書士がサポートいたします。
個人再生をもっと知りたいあなたに