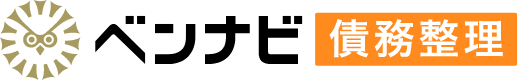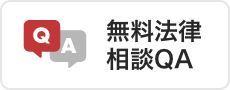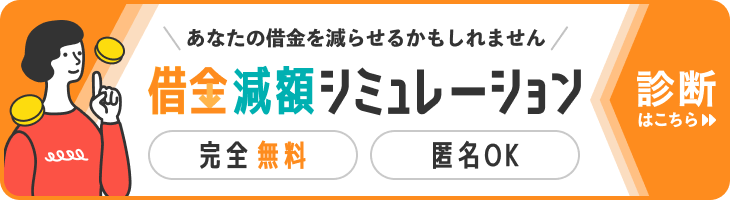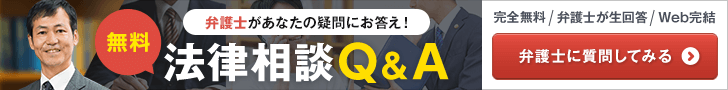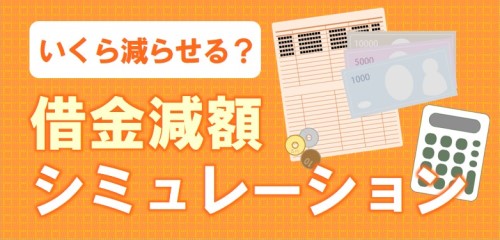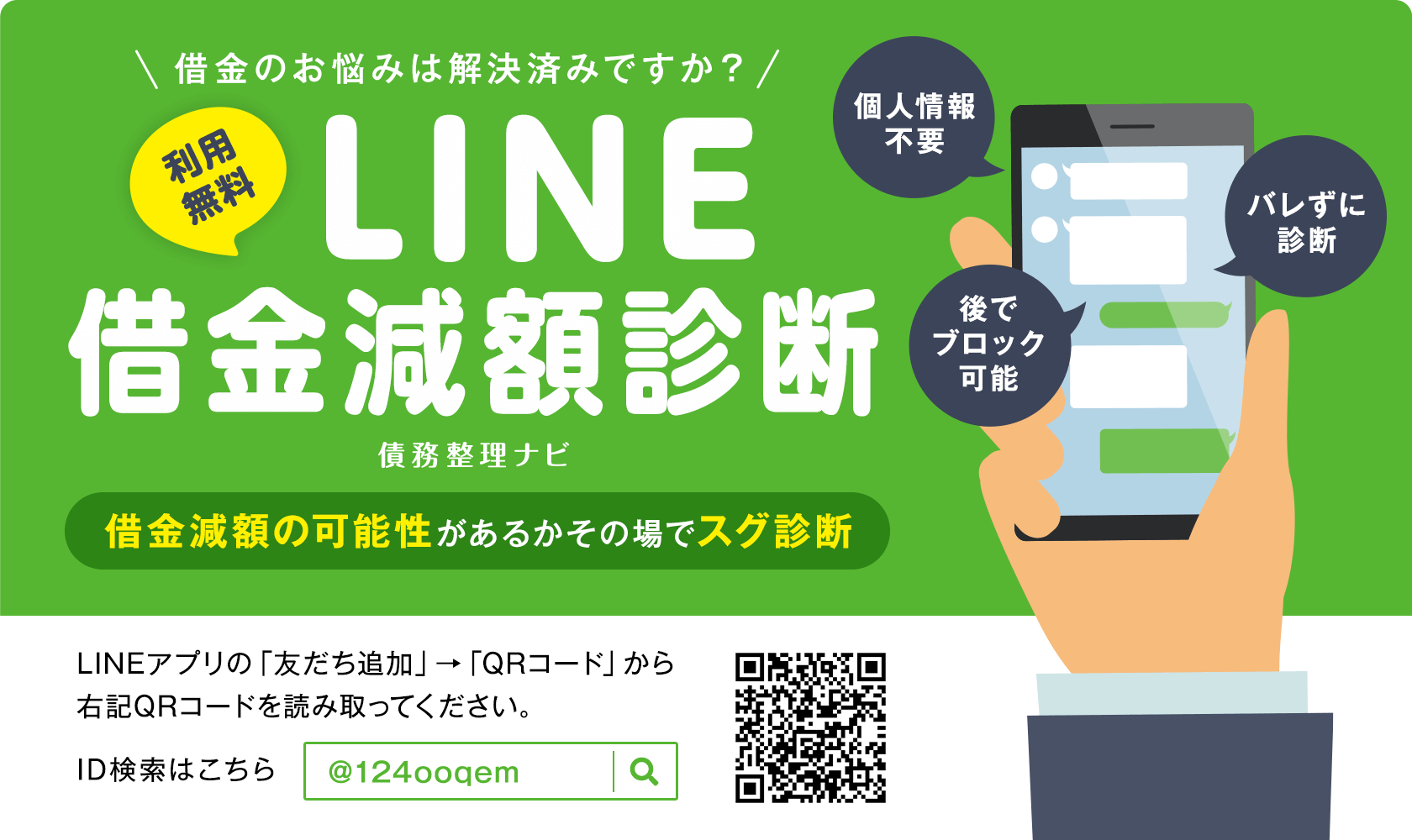小規模個人再生とは?給与所得者等再生との違いを比較


小規模個人再生とは、2種類ある個人再生のひとつです。
特徴として、減額幅が大きく、利用しやすい点が挙げられます。

※再生計画案とは、今後の返済額や期間などの返済計画をまとめた書類です。
この記事では、小規模個人再生でどれくらい借金を減額できるのか、特徴や利用条件などをわかりやすく解説します。
小規模個人再生とは
小規模個人再生とは、裁判所に借金の返済計画をまとめた再生計画案を提出し、債権者の同意を得ることで、借金を減額できる債務整理です。

小規模個人再生には借金の返済義務がありますので、手続き終了後から原則3年で借金を返済することになります。
小規模個人再生は個人再生の基本的な方法で、司法統計によると、令和元年の個人再生総数13,601件のうち、小規模個人再生は12,628件(93%)に上がったそうです。
小規模個人再生は、個人事業主のように安定しない収入の方を対象にした債務整理です。
しかし、給与所得者等再生より減額幅が大きく利用しやすいことなどから、収入の安定している会社員でもほとんどの人が小規模個人再生を行っています。
小規模個人再生は最大90%借金を減額できる
小規模個人再生は、借金の総額もしくは財産の価格(清算価格)で最低限返済しなければいけない金額(最低弁済額)が変動します。
両方の金額を算出し、最低弁済額が高い方に決定されます。
借金の総額で変わる最低弁済額
借金額によって、下表のように最低弁済額が変動します。
|
借金総額 |
最低弁済額 |
|
100万円未満 |
借金総額 |
|
100~500万円未満 |
100万円 |
|
500~1,500万円未満 |
借金総額の20% |
|
1,500~3,000万円未満 |
300万円 |
|
3,000~5,000万円未満 |
借金総額の10% |
例えば、借金が500万円ある場合、最低弁済額は500万円の20%なので、100万円になります。
清算価格で変わる最低弁済額
裁判所が判断する財産(不動産や車)の総額を清算価格といいます。
これを計算し、借金の総額から計算した最低弁済額と比較して、高い方がその小規模個人再生の最低弁済額となります。

上の図のように、通常なら最低弁済額は100万円ですが、清算価値が上回っているため、最低弁済額が200万円に変わります。
小規模個人再生の3つの利用条件とは
小規模個人再生は、主に個人事業主を対象としており、利用条件は以下の3つとなります。
- 個人の債務者であること
- 反復的かつ継続的な収入が見込めること
- 負債の総額が5,000万円以下であること
このように、小規模個人再生は、収入が安定しない人でも継続的な収入があれば利用できるようになっております。
ただし、以下のような人は、この限りではありません。
アルバイト・パートタイムで勤務している人
アルバイトやパートの方でも、3つの条件を満たせていれば利用できる可能性があります。
ただし、短期間で就職先を変えていたり短期バイトなど、就職期間が決まっていたりする場合は、利用するのは難しいでしょう。
年金を受給している人
年金は、死ぬまで受け取ることができ、安定した収入と見なされますので、小規模個人再生を利用できるでしょう。
ただし、「障害年金」「遺族年金」など、必ずしももらえるとは言えない年金を受け取っている場合は、小規模個人再生の利用ができません。
生活保護を受けている人
生活保護を受けている人は、定期的な収入があるとはいえ、継続的な収入とはいえません。
そのため、債務整理をする際は「自己破産」をすすめられるでしょう。
小規模個人再生で再生計画案が認可される要件
申し立てても再生計画案が認可されなければ、借金は減額できません。
ここでは、再生計画案が認可されるためのポイントについてご紹介します。
再生計画案認可には債権者の認可が必要
再生計画案を認めてもらうには、債権者の同意が必要です。
これは、民事再生法第230条によって定められています。
6 第四項の期間内に再生計画案に同意しない旨を同項の方法により回答した議決権者が議決権者総数の半数に満たず、かつ、その議決権の額が議決権者の議決権の総額の二分の一を超えないときは、再生計画案の可決があったものとみなす。
7 再生計画案に同意しない旨を第四項の方法により回答した議決権者のうち第百七十二条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりその有する議決権の一部のみを行使したものがあるときの前項の規定の適用については、当該議決権者一人につき、議決権者総数に一を、再生計画案に同意しない旨を第四項の方法により回答した議決権者の数に二分の一を、それぞれ加算するものとする。
引用元:民事再生法|e-Gov法令検索
これを要約すると、以下のような反対がある場合は再生計画案が認められません。
- 債権者からの半数以上の反対がある
- 反対した債権者から借り入れている借金額が、借金総額の半分以上に該当する
反対があった場合、その小規模個人再生は失敗になります。
ただし、このように拒否されることはほとんどありません。
理由としては、自己破産になってしまえば、まったく返済されなくなるため、小規模個人再生を認めて、少しでも返済された方がマシを考えられるためです。
再生計画案が認可される5つの要件
再生計画案の認可・不認可については、民事再生法第174条に定められています。
一 再生手続又は再生計画が法律の規定に違反し、かつ、その不備を補正することができないものであるとき。ただし、再生手続が法律の規定に違反する場合において、当該違反の程度が軽微であるときは、この限りでない。
二 再生計画が遂行される見込みがないとき。
三 再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったとき。
四 再生計画の決議が再生債権者の一般の利益に反するとき。
引用元:民事再生法|e-Gov法令検索
要約すると、以下のような場合に再生計画案は認可されます。
- 小規模個人再生の手続きや再生計画が法律の規定に違反していないとき
- 再生計画が遂行される見込みがあるとき
- 再生計画の認可・不認可を決める決議の方法に不正がないとき
- 再生計画の取り決めが債権者の一般の利益に違反しないとき
これに加え、先ほど説明した債権者の同意が必要です。
弁護士や司法書士とよく相談し作成すれば、よほどのことがない限り不認可になることはないでしょう。
また、再生計画が遂行される見込みの判断資料になる「履行テスト(履行可能テスト)」(※)で滞納や不払いを起こしてしまうと、不認可になる可能性が高まりますのでご注意ください。
|
履行テスト(履行可能テスト) |
|
再生計画で提示した支払いを再生委員の指定する口座に6回行うものです。 継続して返済計画案で提示した金額を返済できるか判断する重要な資料になります。 裁判所によって行い方が違いますのでご注意ください。 なお、支払った金額は、最終的に再生委員の報酬額を差し引かれた後に、返還されます。 |
再生計画案が否決された場合
再生計画案が、債権者から過半数の支持を得られなかった場合、認可が下りないことをお伝えしました。
その場合、以下のような3つの解決方法が考えられます。
- 給与所得者等再生
- 再度の小規模個人再生
- 破産手続きを行う
1:給与所得等再生
債権者によっては、より減額の幅を小さくするために、給与所得等再生で話をまとめようとする債権者もいます。
そのため小規模個人再生の手続きが失敗した人は、給与所得等再生をおこなうのが一般的です。
2:再度の小規模個人再生
再度、小規模個人再生を行うのもひとつの方法です。
以下の2点に気を付けて、債権者からより賛同の得やすい計画案を作り直しましょう。
- 反対をした債権者に対する返済額の増加
- 返済の期日の見直し
ただ、再度拒否されるリスクがある上に、手間と時間、専門家へかかる費用などが負担になります。
3:破産手続きを行う
個人再生ができない場合の最終手段として、「破産する」ことも検討しましょう。
破産には、以下のようなメリット・デメリットがあります。
|
メリット |
|
|
デメリット |
|
借金をゼロにする手続きではありますが、借金原因によっては免責が受けられない可能性があります。
給与所得者等再生との違い
給与所得者等再生との違いは、以下の通りです。

給与所得者等再生は、利用条件が小規模個人再生のものに加え『安定していること』が必要です。
そのため、収入の変動が大きい個人事業主などは利用できないこともあります。
ただ、債権者の同意が必要ありませんので、もし債権者の多くが反対しても、認可要件を満たしていれば再生計画案が認可されるというメリットがあります。
ほとんどの人は小規模個人再生になるかと思いますが、最適な債務整理方法は人によって異なります。
あなたの最適な方法については弁護士もしくは司法書士にご相談ください。

【借金の減額・免除で再スタート!】最短で催促ストップ◆家族や職場にバレにくい解決◆複数社から借り入れ、返済が苦しい等、当事務所へご相談ください【親身に対応◎】【秘密厳守】※個人間の金銭貸し借り・借金以外の一般法律相談に関する問い合わせは受け付けておりません。
事務所詳細を見る
「返済のために借入社数が増えてしまっている…」「借金総額が膨らんでわからなくなっている…」毎月の返済額の負担を軽減し、借金生活をやめたい方◆まずは最適な解決のために無料診断を◆
事務所詳細を見る
闇金問題の相談窓口【初回相談無料/分割払い・後払い対応】闇金問題に豊富な経験あり・月間400件以上の解決実績のある司法書士が違法な取り立てからお客様を解放します/任意整理・時効援用にも対応可<即日対応・24時間体制>
事務所詳細を見る当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

個人再生に関する新着コラム
-
個人再生後に車を残すことは可能です。ただしローンが終わっておらず、車検証上の所有者が債権者になっているなら処分しなければならないのが原則です。本記事...
-
ベンナビ債務整理では、個人再生に強い弁護士に無料で電話相談ができます。47都道府県全国からの相談に対応。個人再生に強い弁護士に無料相談する方法・窓口...
-
個人再生後は、基本的に住宅ローンをはじめとするローン商品は利用できません。しかし、5〜10年程度経過すれば、信用情報機関のブラックリストから削除され...
-
不景気といわれている現代でも、住宅ローンを組まれる家庭は多くいらっしゃいます。住宅ローンは、何十年の長い期間で返済する高額なローンのため、少しでも返...
-
借金の返済が重荷になった時の法的債務整理の一つに個人再生があります。実は個人再生後でもスマホや携帯を今まで通り利用する方法がありますのでそれについて...
-
個人再生が失敗するケースは全体の3%程度と少ないですが、万が一に備えて不備なく手続きを済ませるポイントを押さえておきましょう。本記事では、個人再生が...
-
小規模個人再生とはどのような債務整理なのか、特徴や条件、再生計画案が認可される要件などを給与所得者等再生と比較しつつご紹介します。
-
返済に困って個人再生をしたいのに、費用が高すぎて申立てができないという悩みを抱える方はたくさんいます。本記事では、弁護士費用に不安を感じる方のために...
-
個人再生を含む債務整理は、家族に内緒で申し立てることができます。しかし、状況によっては大きな財産(車など)を処分する必要もでてきますので、内緒で行う...
-
任意整理後、あなたの代わりに弁護士・司法書士事務所が代わりに返済を行う返済代行という方法があります。返済代行にはメリットもあればデメリットもあること...
個人再生に関する人気コラム
-
個人再生後は、数年間クレジットカードを発行できなくなります。ただ、カードの種類によっては発行できますし、一定の期間後は、再び発行することができます。...
-
個人再生が失敗するケースは全体の3%程度と少ないですが、万が一に備えて不備なく手続きを済ませるポイントを押さえておきましょう。本記事では、個人再生が...
-
個人再生は裁判所を介して借金の返済計画手続きを申立てることで借金を大幅に減額することができますが、一方で、車を手放すことになるとも言われています。本...
-
個人再生を行うと金融事故情報として公的な書類である官報に掲載されます。これを俗に「ブラックリストに載る」と言われていますが、具体的にどのくらいの期間...
-
これから個人再生を申し立てる方に向けて、必要な提出書類から書類の準備・作成方法についてまとめました。この記事を見ていただくことで、個人再生申立てに必...
-
時効の援用をすることで、時効が成立し借金の返済義務が消滅します。ただ誰でも利用できるわけではありません。この記事では、時効を狙っている人や時効間近の...
-
個人再生で失敗するリスクを減らすために、やってはいけないことや失敗例、個人再生など債務整理の得意な弁護士の選び方を解説します。
-
個人再生をするためには、2つの条件を満たす必要があります。この記事では、個人再生できる条件や、収入状況別(バイトや年金など)に個人再生を利用できるか...
-
個人再生では家計簿を提出します。この記事では、家計簿を提出する理由、いつからいつまで書くのか、家計簿の作成方法・注意点、裁判所のチェックポイント、家...
-
返済に困って個人再生をしたいのに、費用が高すぎて申立てができないという悩みを抱える方はたくさんいます。本記事では、弁護士費用に不安を感じる方のために...
個人再生の関連コラム
-
住宅ローンが残っていても、個人再生の住宅資金特別条項(住宅ローン特則)の利用により、家を手放さず債務整理できます。また、競売手続きが開始された場合で...
-
任意整理から個人再生に切り替えるには、利用条件を満たす必要があります。この記事では、個人再生へ切り替えるためのメリットやデメリット、切り替えるべき人...
-
一度個人再生を行っていても、2回目の個人再生を申し立てることは可能です。しかし、1回目とは違い、いくつか注意すべきポイントがあります。2回目の個人再...
-
個人再生を申し立てる際、通帳の提出を求められますが、何か不利なことがバレてしまうのではないかと不安に思う方も多いでしょう。この記事では、通帳を提出す...
-
個人再生の最低弁済額(最低限返済する金額)は、借金の総額やあなたが所持している総資産額によって変わてきます。この記事では、どのように最低弁済額が決ま...
-
個人再生と自己破産には、減額できる借金や手続き後に受ける制限などに大きな違いがあります。この記事では、最低返済額、利用条件、手続き後の制限、没収され...
-
時効の援用をすることで、時効が成立し借金の返済義務が消滅します。ただ誰でも利用できるわけではありません。この記事では、時効を狙っている人や時効間近の...
-
不景気といわれている現代でも、住宅ローンを組まれる家庭は多くいらっしゃいます。住宅ローンは、何十年の長い期間で返済する高額なローンのため、少しでも返...
-
返済に困って個人再生をしたいのに、費用が高すぎて申立てができないという悩みを抱える方はたくさんいます。本記事では、弁護士費用に不安を感じる方のために...
-
個人再生の申立て準備中に給与差押される可能性はゼロではありません。この記事では、給与差押えの解消方法と給与が差し押さえられた場合のリスクをご紹介しま...
-
可処分所得とは、収入から税金などを差し引いて残った自由に使えるお金のこと。自由に使えるといっても、そこから生活費が引かれるため、使ったり貯めたりでき...
-
個人再生を行うと金融事故情報として公的な書類である官報に掲載されます。これを俗に「ブラックリストに載る」と言われていますが、具体的にどのくらいの期間...
弁護士・司法書士があなたの借金返済をサポート
債務整理では、債権者と交渉する任意整理や法的に借金を減額する、個人再生や自己破産などがあります。また、過去の過払い金がある方は、過払い請求を行うことも可能です。
ただ、どれもある程度の法的な知識や交渉力が必要になってきます。債務整理をしたくてもなかなか踏み切れないあなたをベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)の弁護士・司法書士がサポートいたします。
個人再生をもっと知りたいあなたに