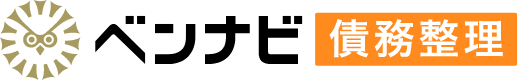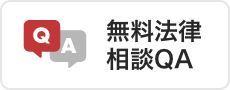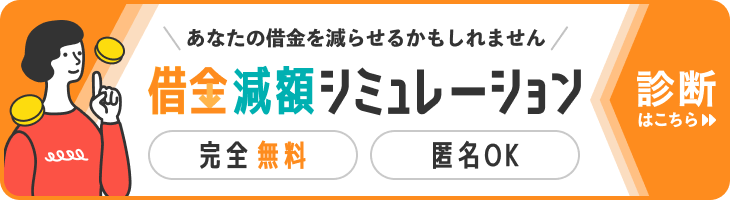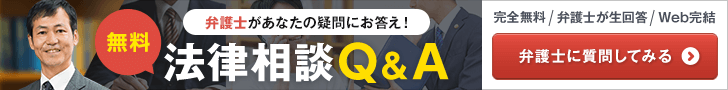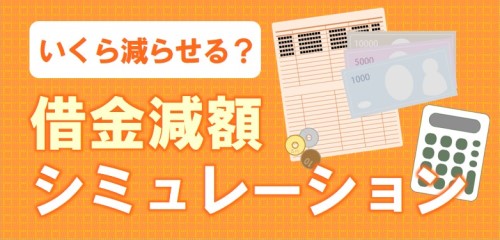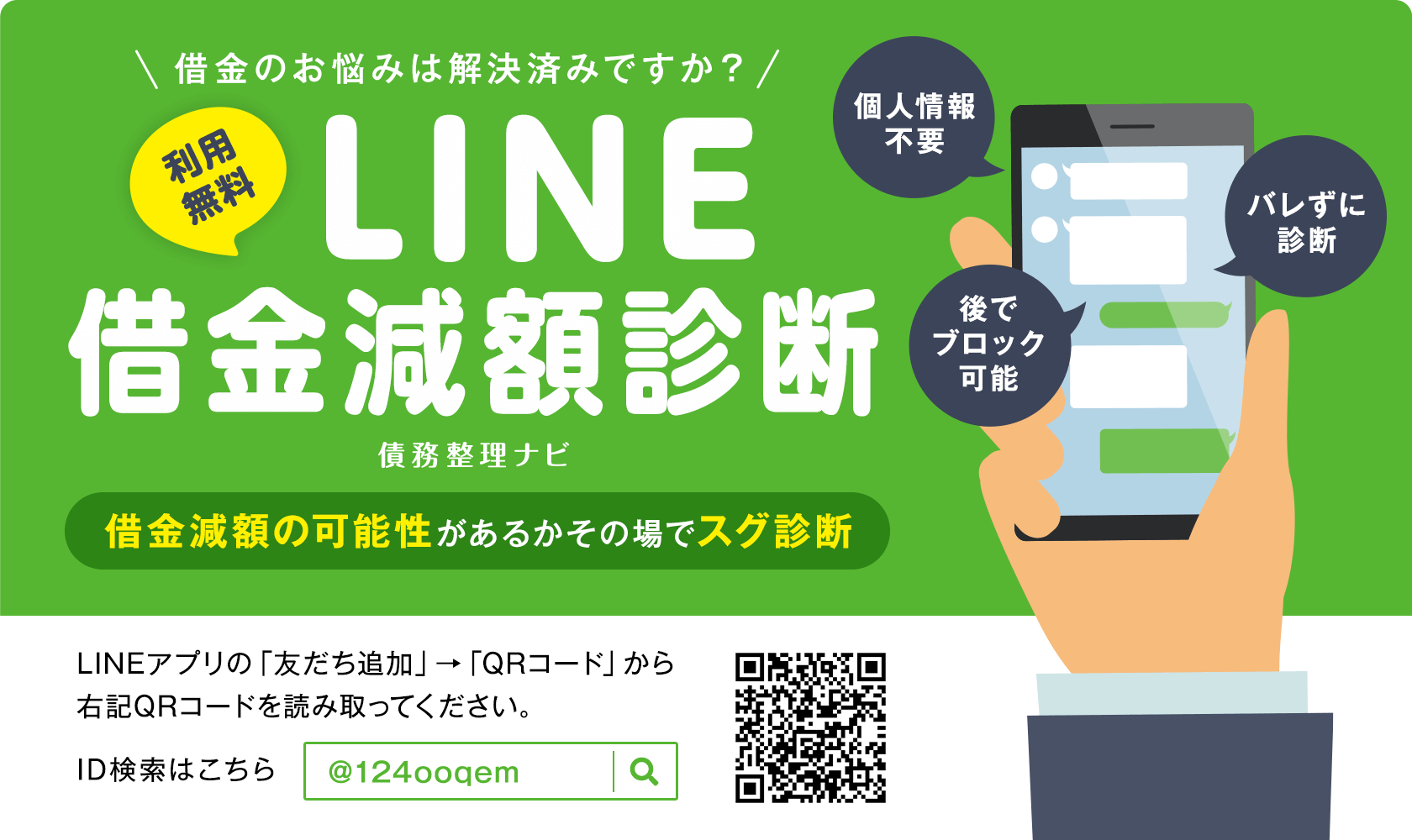個人再生しても持ち家を残せる条件とは?住宅ローン有無に分けて解説


債務整理をする際、持ち家がどうなるのか不安に思っている方は少なくありません。個人再生は、持ち家を残せるだけでなく、競売にかけられた家を取り返せる可能性がある債務整理です。
これらが可能になるのは、個人再生に「住宅ローン特則(住宅資金特別条項)」が設けられているためです。今回は、個人再生において持ち家を残しながら債務整理ができる仕組みについて解説していきます。
【関連記事】個人再生に失敗したらどうなる?|失敗パターンと成功のための対策
|
【注目】家が競売される前に!! 家を残したい方限定 |
|
現在、家が競売にかけられてなくても、このまま借金問題を放置すると競売にかけられてしまう危険性があるでしょう。 「家を残したい」 「競売にかけられた家を取り戻したい」 とお考えの方は、早い段階で弁護士や司法書士などの債務整理の専門家に相談することおすすめします。 専門家への依頼では、以下のようなことが望めます。
借金原因は問いません。ひとりで悩まず、まずは専門家に相談してみましょう |
個人再生で家を残せる理由|住宅ローン特則とは
個人再生で最も特徴的なのが、住宅を残したまま債務整理が出来ることです。ここでは、個人再生で家を残せる理由について探っていきます。
個人再生で家が残せるのは住宅ローン特則があるから
個人再生を行いながら持ち家を残すには、住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を利用する必要があります。
住宅ローン特則(住宅資金特別条項)とは、住宅ローン以外の借金については個人再生の整理対象とするものの、住宅ローンは従来通り支払続けることで持ち家を手元に残せる、という特則です。
持ち家は債務者の生活の拠点となるため、債務者の経済的再建がしやすいように、このような特則が認められています。
個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2つがありますが、どちらの場合でも、住宅ローン特則を利用することができます。
住宅ローン特則の効果
住宅ローン特則の具体的な効果を箇条書きでまとめると、次のようになります。ただし、個々の事情によって特則の内容が変化します。下記の効果の全てが得られるわけではないので、注意が必要です。
- 強制的に行われた競売手続きを中止させることができる
- 住宅ローンを滞納していても、元本と損害金を分割で支払うことができる
- 住宅ローンの返済期間を延長できる(最大10年)
- 再生計画の期間中、住宅ローンの元本の一部及び利息のみを支払えばよくなる
- 同意があれば、上記以外の支払の取り決めができる
同意があれば、支払いについても交渉の余地がありますが、基本的に住宅ローン特則は、住宅ローンを免除・減額する趣旨のものではないため、過度な期待は禁物です。
本来は個人再生の整理対象となっていた借金を、他の借金と別個のものとして整理対象に含めない、という扱いをするに過ぎません。
住宅ローンが残っている家を個人再生で残す4つの条件
住宅ローン特則を利用して家を残すには、いくつか条件を満たさなければなりません。そのため、個人再生を行えば必ず残せるわけではないので注意しましょう。
住宅ローン特則を利用するための条件は、主に次の4つです。
- 所有権が申立人にあり、居住目的の家である
- 家が住宅ローン以外の担保になっていない
- 保証会社の代位弁済から6ヶ月以内
- 家に保証会社の抵当権が設定されている
1:所有権が申立人にあり、住居目的の家である
住宅ローン特則の対象となるのは、所有権が申立人にあり、居住用に利用している住宅1棟のみです。2件目以降の居住用住宅・別宅や別荘、投資目的のアパート・マンション、事業目的の住宅・ビルは対象となりません。
ここでいう住宅とは、床面積の2分の1以上が居住用に利用されていればよく、自宅兼事務所としている建物でも特則の対象にすることが可能です。
また仮に、居住用に使用している家が2件以上ある場合は、その中でもメインで利用している家が対象となります。
2:家が住宅ローン以外の担保になっていない
住宅ローンの債権者である銀行やローンの保証会社等が、特則の対象となる住宅に、抵当権を設定している場合は問題ありません。
しかし、住宅ローン以外の借金の担保として対象となる住宅に抵当権が設定されている場合は、住宅ローン特則を利用することはできません。
例えば、不動産担保ローンを利用したために、特則の対象となる住宅に(根)抵当権が設定されていれば、住宅ローン特則を利用することができなくなります。
3:保証会社の代位弁済から6ヶ月以内
住宅ローンの返済を滞納していると、保証会社が借金を肩代わりして、残金の全額を一括返済する「代位弁済」が行われるのが通常です。
このような代位弁済は、滞納から3ヵ月~6ヵ月以内に行われるのが一般的です。
このような保証会社の代位弁済から6ヵ月以内に個人再生を申し立てることで、住宅ローン特則を利用することができます。逆に言えば、代位弁済から6ヵ月を超えてしまうと、特則を利用できなくなるので注意が必要です。
4:家に保証会社の抵当権が設定されている
住宅ローンの債権者である銀行やローンの保証会社等が、特則の対象となる住宅に、抵当権を設定していても問題ありません。
住宅ローン特則を利用するためには、以上のような条件を全て満たす必要があります。内容が専門的で、要件を満たしているのか判断がつきにくい場合もあるので、まずは、弁護士や司法書士などの法律専門家に相談することをおすすめします。
住宅ローンがない家は個人再生で残せる?
ここまで住宅ローンがあることを前提に解説してきましたが、「住宅ローンがない場合、持ち家は残せないのか?」と気になった方もいらっしゃるかもしれません。
住宅ローン特則とはあまり関係がありませんが、以下で確認していきましょう。
家の資産価値が最低弁済額より少なければ残せる場合がある
結論から先に言えば、個人再生で住宅ローンを完済した家を残すのは、なかなか難しいといえます。
なぜなら、個人再生には「清算価値保障の原則」というものが認められているからです。「清算価値保障の原則」とは、再生債務者は少なくとも保有財産の価値以上のお金を返済しなければならない、という原則です。この原則は、お金を貸した債権者を保護するために認められています。
例えば、保有している財産価値が500万円あれば、少なくとも500万円は返済しなければなりません。家の資産価値が600万円であれば、少なくとも600万円は返済しなければなりません。
住宅ローンを完済した家を残せるケース
個人再生で住宅ローンを完済した家を残すことも、状況によってはできます。債権者に最低でも返済しなければならない額(最低弁済額)が家の資産価値よりも大幅に上回っていれば、家を売却しなくて済みます。
例えば、家の資産価値が100万円しかなく、最低弁済額が500万円であれば、家を残したまま個人再生ができる可能性があります。
家の資産価値が最低弁済額より高い場合は経済的に困難な可能性がある
家を加えた資産価値が最低弁済額より高い場合は、最低弁済額は当該視線価値まで引き上げられます。
この最低弁済額を不動産の売却なく弁済していけるのであれば敢えて不動産を売却する必要はありませんが、経済的に困難である場合の方が多いと思われます。
家のリフォームローンがある人の個人再生
住宅ローン特則は、住宅を購入するためのローンだけでなく、住宅を増改築や改良するための「リフォームローン」も対象に含める場合があります。
対象に含まれるか否かをめぐっては、リフォームローンの債権者が住宅に抵当権を設定しているかどうかで異なります。
家のリフォームローンに抵当権がついている場合
リフォームローンの債権者が住宅に抵当権を設定している場合は、リフォームローンにも住宅ローン特則が適用されます。
そのため、住宅を担保にしてリフォーム資金を借りている場合や、住宅ローンと合わせてリフォームローンを借りている場合は、住宅ローン特則を利用することができます。
ただし、前述したように、住宅ローン特則は、住宅ローン等を減免するものではありません。住宅ローン特則を利用したとしても、リフォームローンも住宅ローンと同様に、今後も継続して返済していくことになります。
家のリフォームローンが無担保の場合
リフォームローンに抵当権がついていない場合(無担保の場合)、住宅ローン特則の適用はありません。
リフォームローンに抵当権がついていない場合は、カードローンなどの他の借金と同様に、個人再生の整理対象となって一部免除になります。
債権者に個人再生を拒否されるリスクがある!
小規模個人再生で個人再生を行ったとき、リフォームローンに抵当権がついていない場合だと、リフォームローンが一部免除されるため、債権者に個人再生を拒否される可能性があります。
まとめ
ここまで、住宅ローン特則を中心に解説してきました。
個人再生を進めていくには、かなり専門的な知識が必要となります。弁護士費用等を節約したい気持ちも分かりますが、個人再生の効果を十分発揮させるために、弁護士や司法書士といった法律のエキスパートに任せることをおすすめいたします。

【全国65拠点以上】【問い合わせ件数1日1,000件以上】【周りに知られずに相談OK】はじめの一歩は弁護士への無料相談!あなたの街のアディーレに、何でもお気軽にご相談ください ※ 2024年1月~12月の平均受電数より問い合わせ件数算出
事務所詳細を見る
【相談料0円|最短即日で対応可能!】弁護士4名体制で全国のご相談に対応可能です!債権者との交渉に自信◎豊富な対応実績を基に毅然とした態度で交渉に臨みます!「借金を0にしたい」「借金を減額したい」といった方はご依頼を!
事務所詳細を見る
【全国65拠点以上】【問い合わせ件数1日1,000件以上】【周りに知られずに相談OK】はじめの一歩は弁護士への無料相談!あなたの街のアディーレに、何でもお気軽にご相談ください ※ 2024年1月~12月の平均受電数より問い合わせ件数算出
事務所詳細を見る当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

個人再生に関する新着コラム
-
個人再生後に車を残すことは可能です。ただしローンが終わっておらず、車検証上の所有者が債権者になっているなら処分しなければならないのが原則です。本記事...
-
ベンナビ債務整理では、個人再生に強い弁護士に無料で電話相談ができます。47都道府県全国からの相談に対応。個人再生に強い弁護士に無料相談する方法・窓口...
-
個人再生後は、基本的に住宅ローンをはじめとするローン商品は利用できません。しかし、5〜10年程度経過すれば、信用情報機関のブラックリストから削除され...
-
不景気といわれている現代でも、住宅ローンを組まれる家庭は多くいらっしゃいます。住宅ローンは、何十年の長い期間で返済する高額なローンのため、少しでも返...
-
借金の返済が重荷になった時の法的債務整理の一つに個人再生があります。実は個人再生後でもスマホや携帯を今まで通り利用する方法がありますのでそれについて...
-
個人再生が失敗するケースは全体の3%程度と少ないですが、万が一に備えて不備なく手続きを済ませるポイントを押さえておきましょう。本記事では、個人再生が...
-
小規模個人再生とはどのような債務整理なのか、特徴や条件、再生計画案が認可される要件などを給与所得者等再生と比較しつつご紹介します。
-
返済に困って個人再生をしたいのに、費用が高すぎて申立てができないという悩みを抱える方はたくさんいます。本記事では、弁護士費用に不安を感じる方のために...
-
個人再生を含む債務整理は、家族に内緒で申し立てることができます。しかし、状況によっては大きな財産(車など)を処分する必要もでてきますので、内緒で行う...
-
任意整理後、あなたの代わりに弁護士・司法書士事務所が代わりに返済を行う返済代行という方法があります。返済代行にはメリットもあればデメリットもあること...
個人再生に関する人気コラム
-
個人再生後は、数年間クレジットカードを発行できなくなります。ただ、カードの種類によっては発行できますし、一定の期間後は、再び発行することができます。...
-
個人再生が失敗するケースは全体の3%程度と少ないですが、万が一に備えて不備なく手続きを済ませるポイントを押さえておきましょう。本記事では、個人再生が...
-
個人再生を行うと金融事故情報として公的な書類である官報に掲載されます。これを俗に「ブラックリストに載る」と言われていますが、具体的にどのくらいの期間...
-
個人再生は裁判所を介して借金の返済計画手続きを申立てることで借金を大幅に減額することができますが、一方で、車を手放すことになるとも言われています。本...
-
これから個人再生を申し立てる方に向けて、必要な提出書類から書類の準備・作成方法についてまとめました。この記事を見ていただくことで、個人再生申立てに必...
-
時効の援用をすることで、時効が成立し借金の返済義務が消滅します。ただ誰でも利用できるわけではありません。この記事では、時効を狙っている人や時効間近の...
-
任意整理後、あなたの代わりに弁護士・司法書士事務所が代わりに返済を行う返済代行という方法があります。返済代行にはメリットもあればデメリットもあること...
-
個人再生では家計簿を提出します。この記事では、家計簿を提出する理由、いつからいつまで書くのか、家計簿の作成方法・注意点、裁判所のチェックポイント、家...
-
個人再生で失敗するリスクを減らすために、やってはいけないことや失敗例、個人再生など債務整理の得意な弁護士の選び方を解説します。
-
個人再生をするためには、2つの条件を満たす必要があります。この記事では、個人再生できる条件や、収入状況別(バイトや年金など)に個人再生を利用できるか...
個人再生の関連コラム
-
借金の返済が重荷になった時の法的債務整理の一つに個人再生があります。実は個人再生後でもスマホや携帯を今まで通り利用する方法がありますのでそれについて...
-
給与所得者等再生とは、主にサラリーマンが対象の個人再生です。利用条件が小規模個人再生より厳しいですが、債権者の同意が必要ないため多くの債権者が反対し...
-
個人再生では、再生計画案通り返済ができるかどうか履行テスト(履行可能性テスト)を行うケースがあります。これを失敗すると、再生計画案の認可に大きく影響...
-
不景気といわれている現代でも、住宅ローンを組まれる家庭は多くいらっしゃいます。住宅ローンは、何十年の長い期間で返済する高額なローンのため、少しでも返...
-
個人再生が失敗するケースは全体の3%程度と少ないですが、万が一に備えて不備なく手続きを済ませるポイントを押さえておきましょう。本記事では、個人再生が...
-
個人再生は自己破産と違い、生命保険を解約しなければならないということはありません。ただし、解約返戻金がある生命保険は個人再生の最低弁済額(最低限返済...
-
返済に困って個人再生をしたいのに、費用が高すぎて申立てができないという悩みを抱える方はたくさんいます。本記事では、弁護士費用に不安を感じる方のために...
-
個人再生後は、数年間クレジットカードを発行できなくなります。ただ、カードの種類によっては発行できますし、一定の期間後は、再び発行することができます。...
-
個人再生の認可決定後「確定」することで手続きが終了し、再生計画案に沿った弁済が開始されます。この記事では、再生計画案認可後の流れや、行っても問題ない...
-
個人再生のデータをみると、全体の成功率(再生計画認可率)は約92%に上ります。ただし、約8%の人の全員が失敗したわけではありません。どのような結果に...
-
個人再生では、退職金も財産の一つとして返済額に影響します。ただし、退職金を受け取るタイミングによって返済額に計上される金額が変わります。この記事では...
-
この記事では、個人再生の無料相談窓口、個人再生の特徴・メリット・デメリット、住宅ローン特則、個人再生ができる条件、個人再生を依頼する際の費用、自己破...
弁護士・司法書士があなたの借金返済をサポート
債務整理では、債権者と交渉する任意整理や法的に借金を減額する、個人再生や自己破産などがあります。また、過去の過払い金がある方は、過払い請求を行うことも可能です。
ただ、どれもある程度の法的な知識や交渉力が必要になってきます。債務整理をしたくてもなかなか踏み切れないあなたをベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)の弁護士・司法書士がサポートいたします。
個人再生をもっと知りたいあなたに