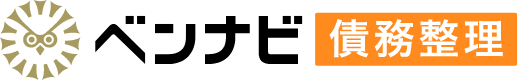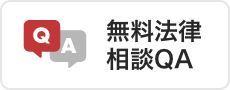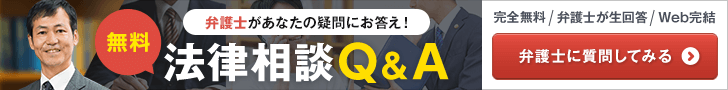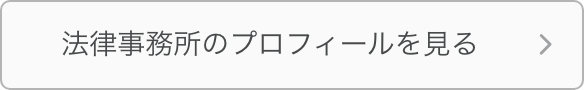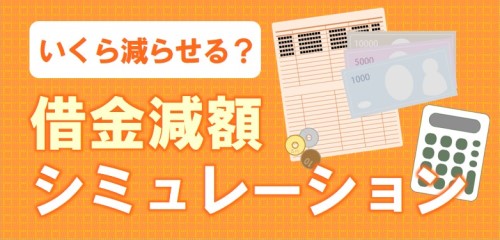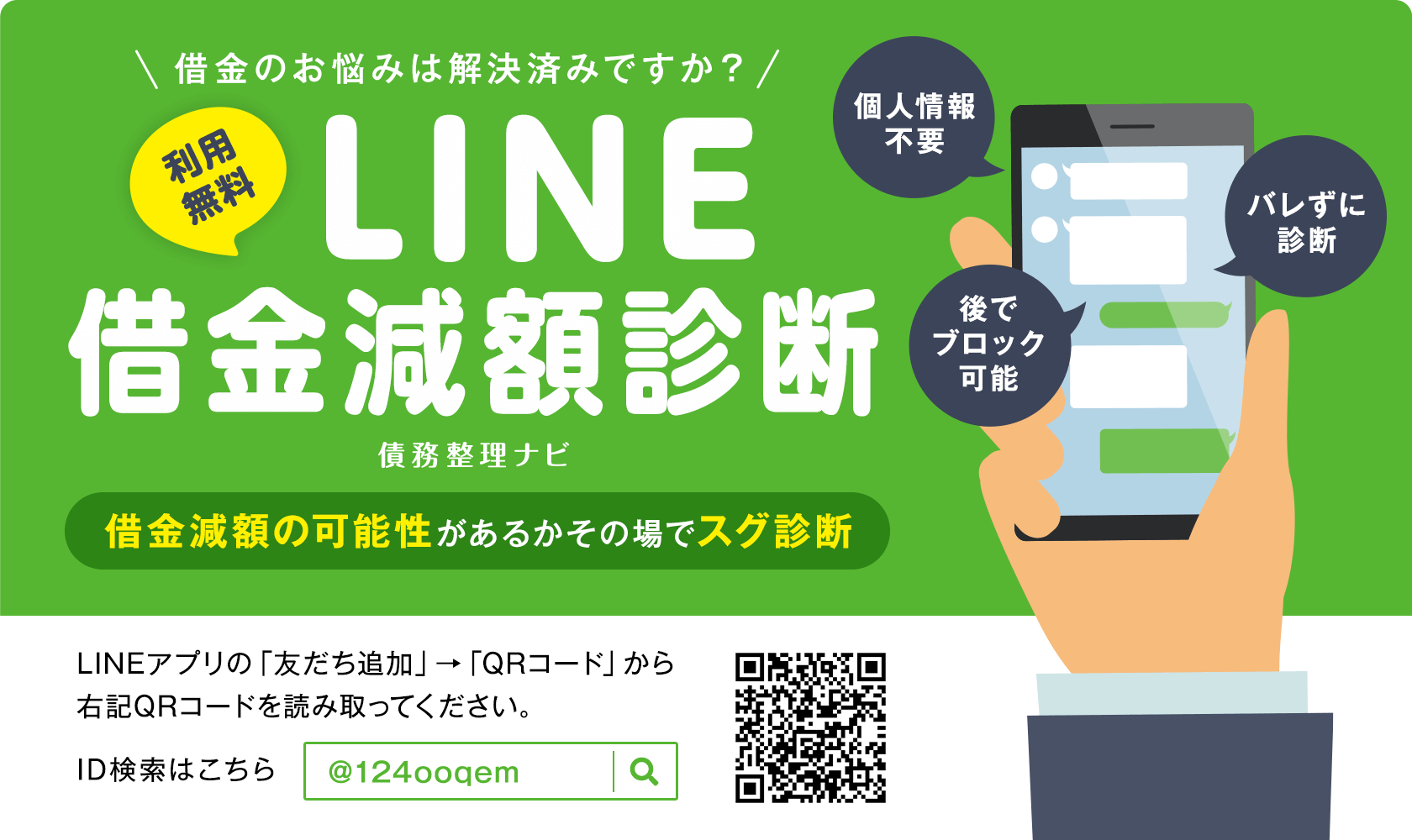【弁護士監修】自己破産の費用は?支払い困難な時の対処法&おすすめの相談先も解説

自己破産にかかる費用は、どれくらいかかるか知りたい方も多いのではないでしょうか。自己破産には3パターンの手続き方法があり、どの方法を選ぶかによって費用相場も大きく異なります。
いずれにしても、借金の返済にお困りの方にとって決して安くない金額がかかるので、手続きを検討するときは、費用相場をしっかりと理解しておくことが大切です。
本記事では、自己破産にかかる費用の相場と内訳について具体的に解説します。
また、自己破産の費用を払えない時の対処法や相談先も解説しますので、自己破産の費用について悩みを早急に解決したい方は、ぜひ最後までご一読ください。

無料相談できる弁護士一覧
【手続き別】自己破産の費用相場
自己破産の手続きにかかる費用は、どの手続きが適用されるかによって大きく異なります。自己破産の手続きは、主に「同時廃止」「管財事件」「少額管財事件」という3つの種類に分かれており、費用相場もそれぞれ異なります。
以下では、手続き別の費用相場をまとめました。

自己破産を検討するときは、手続きにかかる費用相場を知っておくことが具体的な準備を進めるための第一歩となります。
続いて、手続きの概要と費用相場を見ていきましょう。
同時廃止事件:40万円~50万円が相場
- 弁護士費用:30万円~50万円
- 裁判所費用:3万円~5万円程度
同時廃止の費用相場はトータルで40万円程度、手続きにかかる期間が3~4ヶ月程度です。
同時廃止とは、「破産管財人」が選任されず、破産手続の開始決定と同時に手続きが終了する方法です。
破産管財人は、申立人の財産を調査・換価し、債権者へ配当する役割の人を指します。
同時廃止の手続きは主に書類審査で進められるので、時間的な負担や費用を大幅に抑えられる点が大きなメリットです。
準備期間を含めても、同時廃止は管財事件の半分程度の期間で完了します。
管財事件:100万円~130万円が相場
- 弁護士費用:50万円~80万円
- 裁判所費用:50万円程度
管財事件の手続きにかかる費用相場は、一般的に50万円以上かかるとされ、場合によっては100万円を超えるケースもあります。
同時廃止よりも費用がかかる主な理由は、裁判所に納める「予納金」が高額であり、さらに破産管財人への報酬も必要だからです。
管財事件は、自己破産手続きの中でも、より複雑で時間と費用がかかる手続きです。
管財事件は、申立人に一定以上の財産がある場合や、借金の原因が免責不許可事由(例:ギャンブルや浪費)であると疑われる場合に適用されます。
具体例としては、20万円以上の現金や評価額が20万円を超える預貯金、不動産、生命保険の解約返戻金、自動車を所有しているケースが挙げられます。
また、個人事業主や会社の代表者の場合は、財産調査や債権者への配当が必要になるので、原則として管財事件として扱われます。
少額管財事件:50万円~70万円が相場
- 弁護士費用:30万円~50万円
- 裁判所費用:20万円程度
少額管財事件の費用総額は、裁判所費用と弁護士費用を合わせて、おおむね50万円以上で見込んでおくのが一般的です。
少額管財事件とは、手続きをより迅速かつ費用を抑えて進めるために設けられた制度です。
管財事件に該当するものの、財産状況がそれほど複雑ではなく、破産管財人の業務負担が比較的少ないと見込まれる事案で適用されることが多いとされています。
少額管財事件の手続きは、原則として弁護士が代理人として申立てをおこなう場合に限られます。
司法書士では対応できないため、弁護士に依頼したほうが少額管財事件として処理してもらえて、費用が安くなることも。
例えば、換価する財産の種類や数が少ない場合や免責不許可事由の調査が比較的容易な場合が考えられます。
手続きを簡略化すれば、管財事件よりも裁判所に納める予納金を大幅に低く抑えられる点が大きな特徴です。
自己破産にかかる費用の内訳とは
自己破産の手続きを進めるためには、一定の費用が必要となります。
自己破産の費用は、「裁判所に納める費用」と、「弁護士や司法書士に手続きを依頼する時の費用」の2種類に分かれます。
自己破産に関する弁護士費用は、安くて50万円ほど、高い場合は100万円以上かかります。
弁護士・司法書士費用の内訳
自己破産の手続きを弁護士や司法書士に依頼した場合、その対価として費用が発生します。
費用は、一般的に「相談料」「着手金」「報酬金」の3つで構成されています。
以下では、具体的な費用の内訳をまとめました。
| 弁護士 | 司法書士 | |
| 相談料 | 0円~5,000円 | 0円~5,000円 |
| 着手金 | 10万円~30万円程度 | 10万円~20万円程度 |
| 報酬金 | 20万円~50万円程度 | 20万円~40万円程度 |
| 総費用(相場) | 30万円~60万円 | 30万円~50万円 |
「相談料」とは、正式に依頼する前の法律相談にかかる費用です。
最近では初回相談を無料としている事務所も多くあります。
続いて「着手金」とは、委任契約を結び、手続きに着手してもらうために支払う費用です。
これは依頼後の結果に関わらず、原則として返金されません。
次に「報酬金」は、自己破産の申立てが認められて免責許可決定を得られたときに支払う成果報酬です。
なお、なかには報酬金を設定していない法律事務所も存在します。
なお、司法書士に依頼する場合、借入額が140万円以下の事案に限られる点には注意が必要です。
具体的な費用体系や金額は法律事務所によって異なるので、依頼前にしっかりと確認しておきましょう。
また、総費用は司法書士のほうが安くなる傾向がありますが、基本的には大きく変わりません。

無料相談できる弁護士一覧
裁判所費用の内訳
自己破産の手続きを進める際、裁判所に納めなければならない費用があります。
これは主に「予納金」「収入印紙代」「郵券代」という3つで構成されています。
これらは手続きに不可欠な実費として、申立て時に裁判所へ納付することが求められます。
裁判所の手続きにおける費用相場は、以下のとおりです。
| 種類 | 相場 |
| 予納金 | 1万5,000円~3万円程度 |
| 収入印紙代 | 1,500円~3,000円程度 |
| 郵券代 | 1,000円~2,000円程度 |
まず「予納金」についてみていきましょう。
予納金とは、自己破産に関する情報を官報公告に掲載するための費用です。
管財事件や少額管財事件に該当する場合は、選任される破産管財人の活動費用や報酬もこの予納金から賄われます。
次に「収入印紙代」ですが、これは自己破産の申立てをおこなうための手数料にあたります。
申立書に、裁判所が定める金額(一般的には1,500円)の収入印紙を貼付して提出し、納付します。
最後に、「郵券代」とは、裁判所から債権者や申立人本人に手続きに関する書類を送付するために必要な郵便切手の代金です。
申立ての際に、裁判所が指定する種類と枚数の切手をあらかじめまとめて納める必要があります。
自己破産の費用を払えない場合の対処法
自己破産を検討する際、費用の問題は大きな壁となりがちです。
しかし、費用がすぐに用意できないからといって、諦める必要はありません。
いくつかの対処法を検討すれば、道が開ける可能性があります。
ここでは、自己破産の費用を支払えないときの対処法を4つ解説します。
方法ごとのメリットとデメリットを理解し、ご自身の状況に合った選択肢を見極めましょう。
自力で自己破産の手続きを進める
弁護士や司法書士に依頼せずに自力で手続きを進めれば、裁判所に納める費用のみで手続きを進められるので、自己破産の費用を最小限に抑えられます。
しかし結論として、この方法はあまりおすすめできません。
なぜなら、自己破産の手続きは複雑で、専門的な知識が求められるからです。
まず、申立書の作成自体が非常にたいへんです。
自力で手続きを進める場合、収入や財産、借金の状況を詳細に記載し、それを裏付ける書類(例:給与明細、預金通帳のコピー、課税証明書、借入先のリスト)を収集する必要があります。
書類に何らかの不備があると、裁判所から訂正を命じられるだけでなく、最悪の場合、申立てが却下される可能性もあります。
また、手続きが始まると裁判所とのやり取りや債権者との対応も全て自力でおこなわなければなりません。
管財事件になった場合には、破産管財人との面談や調査協力も必要となるので、法律知識がない方にとって相当の負担がかかります。
安く依頼できる弁護士・司法書士に依頼する
堅実な方法として、依頼費用が安い弁護士や司法書士の力を借りることが挙げられます。
弁護士や司法書士は、自己破産手続きに関する専門知識と経験を有しているので、複雑な書類作成や裁判所とのやり取り、債権者との交渉を代行してくれます。
最近は初回相談を無料で受け付けている事務所も多いので、まずは相談してみて、費用やサービス内容、担当者との相性を確認すると良いでしょう。
なお、価格帯だけでなく、「自己破産案件の実績が豊富か」「説明が丁寧で信頼できるか」といった点も考慮することが大切です。
ここで注意したいポイントは、「弁護士と司法書士では対応できる業務範囲に違いがある」という点です。
司法書士の場合、代理人として扱えるのは、1社あたりの借金額(元本)が140万円以下の案件に限られます。
また、地方裁判所での代理権がないので、裁判所への提出書類の作成は可能ですが、破産審尋では代理人として同席できません。
したがって、借金の総額が大きい場合や個別の債権額が140万円を超える場合、あるいは管財事件になる可能性が高い複雑な事案の場合は、弁護士に依頼するのが一般的です。
分割払いに対応した弁護士に依頼する
多くの法律事務所では、依頼者の経済状況に配慮し、費用の分割払いや後払いに柔軟に対応しています。
分割払いを利用する最大のメリットは、月々の支払い負担を軽減できることです。
弁護士に自己破産手続きを正式に依頼すると、弁護士は各債権者に対して「受任通知」という書類を送付します。
この通知を受け取った貸金業者や債権回収会社は、債務者本人への直接の取立てができなくなります。
つまり、弁護士に依頼した時点で、借金の返済や督促を一時的にストップできます。
この返済がストップしている期間を利用して、弁護士費用を分割で支払っていくことが可能です。
これまで借金の返済に充てていたお金を、弁護士費用の支払いに充てられるので、実質的な月々の負担を増やさずに費用を積み立てられます。
なお、支払い回数や月々の支払額は、依頼先の法律事務所とよく相談して、ご自身の収入状況に合った無理のない計画を立てることが重要です。
まずは初回相談時に、分割払いが可能かどうかと、具体的な支払い方法について確認してみましょう。

無料相談できる弁護士一覧
法テラスの「民事法律扶助」制度を利用する
弁護士や司法書士への依頼費用を支払うことが困難な場合は、「法テラス(日本司法支援センター)」が提供する「民事法律扶助制度」の利用を検討するのをおすすめします。
法テラスは、国によって設立された公的な法人であり、経済的な理由で法律専門家のサポートを受けられない人々を支援することを目的としています。
民事法律扶助制度を利用すると、法テラスが弁護士や司法書士に支払う費用を一時的に立て替えてくれます。
法テラスを利用するためには、以下の条件を全て満たす必要があります。
| 法テラスの利用条件 |
| ①月収や資産が一定以下であること |
| ②自己破産の免責が見込まれること |
| ③民事法律扶助の趣旨に適していること |
| ③破産者が個人であること |
審査を通過できたら、法テラスが契約した弁護士や司法書士に依頼できるだけでなく、着手金や実費といった費用を法テラスが立て替えてくれます。
立て替えてもらった費用は、原則として手続き終了後に法テラスに対して分割で返済します。
月々の返済額は、通常5,000円~1万円程度の無理がない範囲で設定されます。
なお、生活保護を受給されている場合は、立て替え費用の返済が免除される場合があります。
さらに、生活保護を受けていなくても、返済が困難な事情がある場合は返済の猶予や免除を受けられる可能性もあります。
自己破産費用を支払う時の具体的な流れ

自己破産の手続きを進めるときは、費用を支払うタイミングや支払い方法をしっかりと把握していくと安心です。
一般的に、自己破産の費用を支払うときは「専門家への相談・依頼」→「費用支払い」→「裁判所への申立て」→「免責許可決定」というステップを踏んでいきます。
ここでは、弁護士や司法書士に依頼し、費用を支払うときの流れを解説します。
なお、細かい流れは依頼する事務所や管轄の裁判所によって異なる場合があるため、あくまで目安として参考にしてください。
STEP①:弁護士や司法書士に相談する
最初のステップは、借金問題に詳しい弁護士や司法書士に相談することです。
多くの事務所では初回の無料相談を実施しているので、積極的に利用するのをおすすめします。
ご自身の借金の状況や収入、所有している財産を正直に伝えたうえで、任意整理や個人再生ではなく、自己破産がもっとも最適な解決策なのかをアドバイスをもらいましょう。
相談の結果、自己破産の手続きを依頼することが決まったら、委任契約を結びます。
なお、相談料がかかる事務所に依頼した場合は、相談の時点で一度支払いが発生する可能性があります。
STEP②:依頼費用・司法書士費用を支払う
弁護士や司法書士と委任契約を結んだら、依頼費用の支払いが発生します。
一般的に、自己破産を依頼する方は資金面に困っているケースが多いので、分割払いを認めている事務所が多い傾向です。
分割払いを選択した場合、自己破産の申立て準備と並行して、数ヶ月間にわたって費用を分割で支払っていきます。
弁護士は、この支払いと同時に、債権者への受任通知の送付や申立てに必要な書類の収集・作成の準備を進めます。
一般的には、着手金として定められた金額(あるいは総額)の支払いが完了するまで、裁判所への自己破産の申立てはおこなわれません。
STEP③:裁判所への申立てを進める
弁護士・司法書士費用の支払いが完了し、申立てに必要な書類の準備が整ったら、管轄の地方裁判所に自己破産の申立てをおこないます。
申立ての際は、裁判所に納める費用として、「申立手数料」(収入印紙で納付、通常1,500円程度)と「予納郵券代」(連絡用の郵便切手代、数千円程度)を支払う必要があります。
申立書が受理されると、裁判所での手続きが開始されます。
その後、通常は1ヶ月程度で裁判官と面談する「破産審尋」がおこなわれることがあります。
ただし、弁護士に手続きを依頼している場合は、この破産審尋に債務者本人が出席する必要がないケースもあります。
STEP④:予納金(官報公告料)を支払う
自己破産の申立て後、裁判所から「官報公告料」の支払い指示があります。
予納金とは、自己破産の手続きが開始されたことを官報に掲載するための費用であり、1万円~2万円程度ほどかかります。
なお、支払い時期は裁判所によって異なりますが、2週間~1ヶ月程度で納付を求められるのが一般的です。
あらかじめ依頼している弁護士・司法書士に、管轄裁判所の手続きの詳細を確認しておくとスムーズです。
STEP⑤:自己破産手続の開始が決定される
裁判所に自己破産の申立てをおこない、破産の原因や免責不許可事由の有無がひと通り審査されると、裁判所は「破産手続開始決定」を出します。
この決定によって、正式に自己破産の手続きが法的な効力を持ってスタートします。
この決定が出されると、その旨が官報に公告されます。
同時廃止の場合は、この開始決定と同時に手続きが終了(廃止)となるので、この段階で手続きは完了します。
一方、管財事件や少額管財事件の場合は、この開始決定を受けて、破産管財人による本格的な財産調査や管理、換価・配当といった手続きが始まります。
STEP⑥:破産管財人の選任&引継予納金の支払い
自己破産の手続きが「管財事件」または「少額管財事件」となった場合、裁判所によって「破産管財人」が選任されます。
破産管財人は通常、その裁判所の管轄区域内の弁護士から選ばれます。
管財人の主な役割は以下のとおりです。
- 申立人と面談をおこない、財産状況を詳しく調査すること
- 隠し財産がないかを確認すること
- 換価できる財産があれば現金化し、債権者に法律に基づいて公平に分配すること
なお、①~③の調査結果を裁判所や債権者集会で報告するのも管財人の役割です。
この一連の管財業務を遂行するための費用として、申立人は裁判所に対して「引継予納金」を支払う必要があります。
この予納金は、管財人への報酬にも充てられます。
STEP⑦:免責審尋・免責許可の決定
自己破産手続きの最終段階において、裁判所が借金の免責を許可するかどうかを最終判断するためにおこなわれるのが「免責審尋」です。
主に免責審尋は、同時廃止事件や管財事件で、免責不許可事由が疑われる場合に実施されます。
裁判官が、申立人本人から破産に至った経緯や現在の生活状況、借金に対する反省の度合いを聴取し、免責を許可することが適切かどうかを見極めます。
申立人は、嘘をつかずに誠実な態度で質問に答えることが重要です。
免責審尋の結果、特に問題がないと判断されれば、裁判所は「免責許可決定」を下します。
STEP⑧:免責確定・成功報酬を支払う
裁判所から「免責許可決定」が出されると、その決定内容が官報に掲載されます。
官報公告から通常2週間、債権者から不服申立て(即時抗告)がなければ、免責許可決定は法的に確定します。
この「免責確定」をもって、自己破産の手続きは全て終了となり、原則として全ての借金の支払い義務が正式に免除されます。
長かった手続きが完了し、経済的な再スタートを切ることができます。
手続きが無事に終了した後、依頼していた弁護士や司法書士事務所との間で、「成功報酬」の支払いが契約で定められている場合があります。
成功報酬とは、文字通り、自己破産(免責許可)が成功した場合に発生する費用のことです。
もし成功報酬の取り決めがある場合は、契約内容に従って、このタイミングで支払う必要があります。
具体的な支払い方法や支払い時期は、依頼した専門家にあらかじめ確認しておきましょう。
自己破産の手続きで困ったら弁護士に相談しよう
もしあなたが自己破産の手続きについてお困りなのであれば、弁護士への相談をおすすめします。
弁護士に依頼すれば、自己破産の申立てや書類作成、裁判所とのやり取りも全て代行してくれます。
弁護士が債権者に受任通知を送付すれば、最短即日で債権者からの督促や取り立てがストップするので、精神的なプレッシャーからも解放されます。
債権者からの催促が止まっている期間は、自己破産手続きが完了するまでの間、借金の返済をする必要がなくなります。
この期間を利用して、自己破産の手続き費用や弁護士費用を支払うための資金集めが可能です。
また、弁護士はあなたの状況を詳しくヒアリングし、自己破産が本当に最善の策なのか、個人再生や任意整理といった他の債務整理の方法がベストなのではないか、といった専門的な視点からのアドバイスも提供してくれます。
借金問題は一人で抱え込まずに専門家である弁護士に相談すれば、解決への道筋が見えてくるはずです。
多くの事務所で無料相談を実施しているので、まずは気軽に相談してみましょう。
「ベンナビ債務整理」を利用すれば、お近くの債務整理に強い弁護士を効率的に探せます。
自己破産の悩みを弁護士へ相談して一日でも早く悩みを解決しよう
自己破産は、裁判所に認めてもらえれば、全ての借金の支払い義務が免除される法的制度です。
返済しきれないほど多額の借金を抱えてしまった方にとっては、まさに人生を再スタートさせるための有効な手段となり得ます。
借金のプレッシャーから解放されれば、経済的にも精神的にも新たな一歩を踏み出せるようになるでしょう。
ただし、自己破産の手続きを進めた場合、持ち家や高級車といった財産は原則として手放さなければなりませんし、手続き期間中は弁護士や警備員の仕事に就けなくなる資格制限もあります。
また、信用情報機関に事故情報が登録されるので、5~10年は新たな借り入れやクレジットカードの作成ができなくなります。
どの手続きが自身に適しているかを自己判断するのは、決して簡単ではありません。
だからこそ、借金問題の解決実績が豊富な弁護士に相談することが重要です。
弁護士は、あなたの状況を客観的に分析し、手続きごとのメリット・デメリットを説明した上で、ベストな解決策を見つけ出してくれます。
一人で悩まず、一日でも早く専門家に相談して、問題解決への第一歩を踏み出しましょう。
「ベンナビ債務整理」では、初回無料相談を受け付けている弁護士が多数掲載されているので、まずは気軽に相談から始めてみましょう。

無料相談できる弁護士一覧

「返済のために借入社数が増えてしまっている…」「借金総額が膨らんでわからなくなっている…」毎月の返済額の負担を軽減し、借金生活をやめたい方◆まずは最適な解決のために無料診断を◆
事務所詳細を見る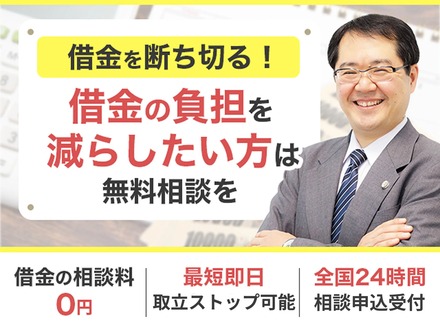
【借金の減額・免除で再スタート!】最短で催促ストップ◆家族や職場にバレにくい解決◆複数社から借り入れ、返済が苦しい等、当事務所へご相談ください【親身に対応◎】【秘密厳守】※借金とは、元本及び利息等を併せた金額をいいます
事務所詳細を見る
【借金の減額・免除で再スタート!】最短で催促ストップ◆家族や職場にバレにくい解決◆複数社から借り入れ、返済が苦しい等、当事務所へご相談ください【親身に対応◎】【秘密厳守】※個人間の金銭貸し借り・借金以外の一般法律相談に関する問い合わせは受け付けておりません。
事務所詳細を見る当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

自己破産に関する新着コラム
-
不景気といわれている現代でも、住宅ローンを組まれる家庭は多くいらっしゃいます。住宅ローンは、何十年の長い期間で返済する高額なローンのため、少しでも返...
-
自己破産を弁護士に依頼した後、任意整理に変更することは可能です。ただし、早めに行動しないと手遅れになることも。本記事では、自己破産から任意整理に変更...
-
法テラスの民事法律扶助制度では、相場より費用を抑えて自己破産が可能です。一方でデメリットもあるので注意しましょう。本記事では法テラスで自己破産を進め...
-
生活保護受給中でも自己破産手続きは可能です。法テラスの弁護士費用立替制度を利用すれば、弁護士費用の自己負担なく借金を整理できます。生活保護と自己破産...
-
自己破産は借金の返済義務が免除される強力な手続きです。しかし、基本的には弁護士のサポートがなければ、手続きを進めることはできないので、弁護士費用を負...
-
自己破産後はクレジットカードが使えません。ブラックリストに載ることでもともとあるカードは強制解約になり、新規の作成もできなくなるためです。本記事では...
-
無条件で自己破産できるわけではなく、法律で定められた要件を満たさなくてはなりません。本記事では、自己破産ができないケースの具体例や、自己破産できない...
-
自己破産においては、債務者にとって有利なことばかりが起こるわけではありません。本記事では、自己破産のメリット・デメリット、自己破産をするときに弁護士...
-
自己破産をすると、多くの場合で携帯電話が強制解約となります。ただし、利用料金の滞納や分割払いの残債がなければこれまで通り利用できるほか、自己破産によ...
-
自己破産のデメリットには、ブラックリストに登録されることや職業・資格制限を受けることなどいくつかありますが、誤解されることも少なくありません。本記事...
自己破産に関する人気コラム
-
自己破産を検討されている方にとっては、破産後の生活は気になるところでしょう。この記事では、自己破産後に受ける制限や、生活を良くするために考えておきた...
-
廃課金とは、廃人と課金を合わせたネットスラングで、一般的に収入に見合わない金額を課金する人を指します。本記事では廃課金の定義や課金してしまう人の特徴...
-
自己破産は、全ての借金の支払い義務を逃れ、所持する高価な財産を処分する法的手続きであり、生活をゼロから再建するための最終手段です。本記事では自己破産...
-
自己破産では裁判所に支払う費用のほか、弁護士に依頼する場合は弁護士費用もかかります。状況により費用は異なり、弁護士費用は後払い可能な場合もあります。...
-
ブラックリストに掲載される期間はどの程度なのでしょうか。 よく、「ブラックリストに載るとカードが作れない」などという話を聞きますが、そもそもブラック...
-
破産宣告(はさんせんこく)とは何かを解説!手続きの流れや条件、かかる費用に加えて、自己破産を最短で進める為の方法をご紹介していきます。自己破産にはデ...
-
結論からいいますと、借金がある状態でも生活保護を受けることができます。そこで、生活保護と借金の関係を深堀していきたいと思います。
-
自己破産はできる条件があります。これに該当しない場合には自己破産が実現できず借金を免責することができません。この記事では、自己破産ができない4つのケ...
-
奨学金を借りたはいいものの、就職後も返済が厳しく破産に追い込まれる件数は1万件にのぼっています。ただし、破産にはリスクがあり、あなたの借金が免除され...
-
自己破産をする上で、破産管財人(はさんかんざいにん)が何をするのか、どのような人なのかを知っておくことで、免責を受けられる可能性が高まります。この記...
自己破産の関連コラム
-
自己破産は借金の返済義務が免除される強力な手続きです。しかし、基本的には弁護士のサポートがなければ、手続きを進めることはできないので、弁護士費用を負...
-
自己破産によって差し押さえられない年金の種類と、差し押さえられるケースはどのようなものかについて解説していきます。基本的に自己破産によって年金が差し...
-
免責不許可事由があると、支払える費用がないと主張しても、同時廃止にならない可能性があります。同時廃止にならないということは、費用が何十万と必要になっ...
-
官報といえば、国の情勢を把握したい人が読むものですが、具体的にどのような内容が掲載されているかご存知ない方が多いのではないでしょうか。場合によっては...
-
自己破産を弁護士に依頼した後、任意整理に変更することは可能です。ただし、早めに行動しないと手遅れになることも。本記事では、自己破産から任意整理に変更...
-
自己破産した場合に自身の退職金がどうなるのか気になる方も多いことでしょう。本記事では、自己破産手続で、退職金がどのように取り扱われるのか、その行方に...
-
自己破産で免責を受けても、税金の滞納金などの支払い義務はなくなりません。支払いを怠れば、財産の差し押さえなどのリスクが発生します。この記事では、自己...
-
無職の人が債務整理をおこなう場合、任意整理ではなく自己破産などを選択するのが通常です。本記事では、無職の人が任意整理を原則的にできない理由と、例外的...
-
自己破産は、借金問題を解決するための有力な選択肢です。自己破産による影響について正しい知識を備え、自己破産すべきかどうかを適切に判断しましょう。本記...
-
不景気といわれている現代でも、住宅ローンを組まれる家庭は多くいらっしゃいます。住宅ローンは、何十年の長い期間で返済する高額なローンのため、少しでも返...
-
無条件で自己破産できるわけではなく、法律で定められた要件を満たさなくてはなりません。本記事では、自己破産ができないケースの具体例や、自己破産できない...
-
自己破産はできる条件があります。これに該当しない場合には自己破産が実現できず借金を免責することができません。この記事では、自己破産ができない4つのケ...
弁護士・司法書士があなたの借金返済をサポート
債務整理では、債権者と交渉する任意整理や法的に借金を減額する、個人再生や自己破産などがあります。また、過去の過払い金がある方は、過払い請求を行うことも可能です。
ただ、どれもある程度の法的な知識や交渉力が必要になってきます。債務整理をしたくてもなかなか踏み切れないあなたをベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)の弁護士・司法書士がサポートいたします。
自己破産をもっと知りたいあなたに