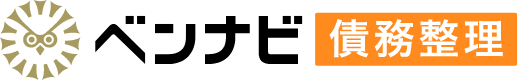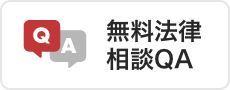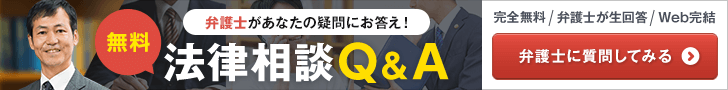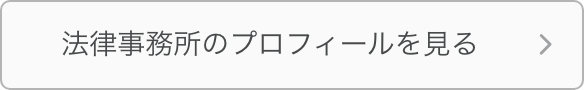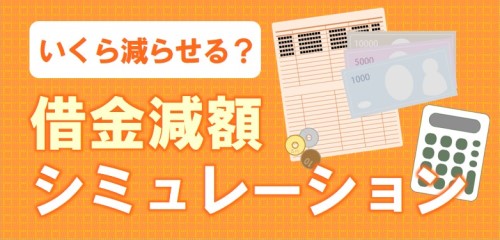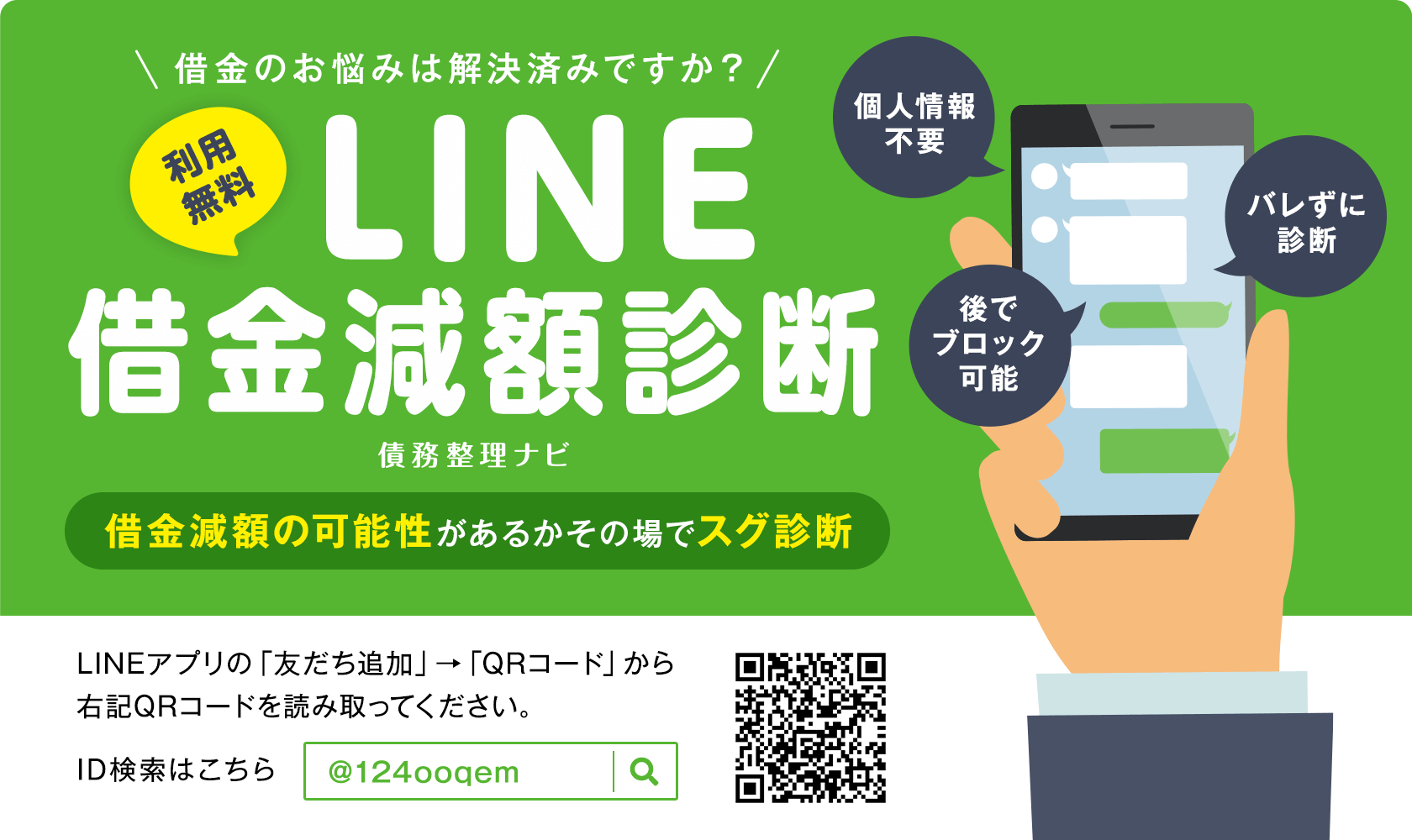【全国対応】自己破産の無料相談窓口おすすめ8選!選ぶポイントも解説

自己破産を無料相談できる窓口は数多くあります。
たとえば法律事務所や法テラスをはじめ、全国の弁護士会や地方自治体、金融関連団体などです。
それぞれの窓口には特徴があり、利用条件が決まっている窓口もあるため、自分の状況や希望に合った場所を選ぶことが重要です。
本記事では、自己破産・借金問題を無料で相談できる窓口を8つ紹介。
特徴や利用条件をわかりやすく紹介します。
無料相談へ行く前に準備しておくことや弁護士を選ぶポイントも解説するので、ぜひ参考にしてください。
自己破産が認められれば、すべての借金がなくなりますが、その代わり最低限の財産以外手放すことになります。
借金問題を解決させる方法には、任意整理や個人再生などの方法もあるのです。
もしかしたらあなたにとって自己破産をすることが、ベストな選択肢ではないかもしれません。
自己破産をご検討中の方は、弁護士に依頼するのがおすすめです。
弁護士に依頼をすれば、下記のようなメリットがあります。
- 自身にとって最適な解決策を提案してくれる
- 面倒な手続きを一任できる
- 依頼した時点で、取り立てが停止する など
初回相談が無料の弁護士事務所も多数掲載しております。
| 無料相談・土日祝日対応・19時以降の相談可能な事務所を多数掲載中! |

無料相談できる弁護士一覧
自己破産・借金問題を無料で相談できる窓口8選
自己破産や借金問題について無料で相談できる窓口は複数存在します。
それぞれの窓口には特徴があり、提供されるサービス内容や利用条件も異なるため、現在の状況や希望に合わせて最適な相談先を選びましょう。
|
|
ベンナビ債務整理 |
法テラス |
全国の弁護士会 |
全国の司法書士会 |
地方自治体 |
多重債務 |
貸金業相談・紛争解決センター |
全国銀行協会相談室 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
無料相談の詳細 |
初回無料相談 |
1回30分×3回無料 |
債務整理相談は無料 |
無料相談会 |
無料法律相談会 |
電話無料相談 |
電話無料相談 |
対面・電話の無料相談 |
|
利用条件 |
条件なし |
収入や資産が一定の基準を下回る方 |
条件なし |
条件なし |
その地域在住の方など |
条件なし |
条件なし |
条件なし |
|
電話相談 |
事務所による |
〇 |
〇 |
〇 |
× |
〇 |
〇 |
〇 |
|
オンライン相談 |
事務所による |
〇 |
× |
〇 |
× |
× |
× |
× |
|
おすすめな人 |
自己破産の手続きを具体的に進めたい |
費用の捻出が難しい |
中立的な立場からアドバイスがほしい |
借入額が140万円以下である |
まずは気軽に話を聞いてみたい |
複数から借入をおこなっている |
貸金業者とトラブルになっている |
銀行ローンの返済に困っている |
※司法書士会の司法書士総合相談センターは東京司法書士会の場合を記載
1.ベンナビ債務整理|無料相談OKの事務所多数
ベンナビ債務整理は、全国の債務整理が得意な弁護士を掲載している弁護士検索サイトです。
債務整理について相談するなら、弁護士に直接連絡するのが最も確実です。
しかし、弁護士を自分で探すのは手間がかかります。ベンナビ債務整理なら、複数の弁護士事務所のサイトを比較する手間がかかりません。弁護士の解決実績・料金・得意分野・対応エリア等で、簡単に比較できます。
さらに、初回相談無料・電話相談可・土日祝対応という事務所が多く掲載されているのも魅力です。実際に依頼しなくてもいいので、気軽に無料相談できます。また実際に依頼する場合も、最短即日で取り立てを止めるなど、弁護活動をすぐに受けられます。
事務所によっては電話以外にも、メール・LINE・オンラインなど、様々な手段で無料相談できます。
【相談内容別】ベンナビ債務整理で弁護士を探す
ベンナビ債務整理では、債務整理の分野別に弁護士を探すことも可能です。
債務整理と一言でいっても、弁護士によって得意分野があります。ベンナビ債務整理なら自己破産に強い弁護士を比較して探すことができるため、弁護士に初めて相談する人にもおすすめです。
自分の状況に向いている債務整理方法に強い弁護士を簡単に探せるので、ぜひ活用してくださいね。





ベンナビ債務整理に掲載している弁護士の解決事例
ベンナビ債務整理では、解決実績が豊富な債務整理に強い弁護士を多数掲載しています。
以下では、ベンナビ債務整理に掲載されている弁護士の自己破産の解決事例を見ることができます。
実際に依頼してもいいか迷っている人は、ぜひ参考にしてみてください。
【都道府県別】ベンナビ債務整理で弁護士を探す
ベンナビ債務整理では、全国の債務整理に強い弁護士を掲載しています。
東京・大阪をはじめ、47都道府県で絞り込んで探せます。さらに市区町村・駅で探すことも可能です。
無料相談だけでも、そのまま弁護士に依頼してもOK。気になる人は、ぜひ以下からお住まいの都道府県の債務整理に強い弁護士を検索してみてください。
2.法テラス(日本司法支援センター)
経済的に余裕がなく、弁護士への相談や依頼費用を捻出するのが難しいという方には、法テラス(日本司法支援センター)の利用がおすすめ。
法テラスは国によって設立された公的な機関で、収入や資産が一定の基準を下回る方を対象に、無料の法律相談を提供しています。
資力基準を満たせば、同一の問題について3回(1回につき30分)まで無料相談を受けることが可能です。
さらに法テラスでは、弁護士費用を法テラスが一時的に立て替える制度を設けています。
今すぐに費用を支払えなくても、あとから無理のない範囲で分割返済していくことが可能です。
利用を希望する場合は、住んでいる地域にある法テラスの事務所に電話で問い合わせるか、公式Webサイトで利用条件の詳細を確認し、相談予約をおこなってください。
法テラスの無料相談を利用できる条件
法テラスの無料法律相談を利用するためには、収入と資産が一定の基準以下であることが条件です。
具体的には、手取りの平均月収額(賞与含む)と、現金及び預貯金の合計額が基準となります。
配偶者がいる場合はその収入・資産も合算して判断されます。
基準額は家族の人数や居住地域によって細かく定められており、たとえば東京都特別区・大阪市に住んでいる場合の基準は次のとおりです。
|
家族人数 |
収入基準 |
資産基準 |
|---|---|---|
|
1人 |
200,200円 |
180万円以下 |
|
2人 |
276,100円 |
250万円以下 |
|
3人 |
299,200円 |
270万円以下 |
|
4人 |
328,900円 |
300万円以下 |
神奈川県横浜市や愛知県名古屋市、宮崎県仙台市などの都市部の一部地域にも上記の基準が該当します。
もし基準額を超えても、家賃や住宅ローン、医療費といった生活維持のためにやむを得ない出費がある場合には、相当額が収入から控除され、結果的に基準を満たすと判断されるケースもあります。
| 都道府県 | 電話番号 | 住所 | ホームページ |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 0570-078388 | 〒060-0001 北海道札幌市中央区北1条西9丁目3-1 南大通ビルN1 1F | 詳細ページ |
| 青森県 | 0570-078387 | 〒030-0861 青森県青森市長島1-3-1 日本赤十字社青森県支部ビル2F | 詳細ページ |
| 岩手県 | 0570-078382 | 〒020-0022 岩手県盛岡市大通1-2-1 岩手県産業会館本館2F | 詳細ページ |
| 宮城県 | 0570-078369 | 〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町3-6-1 一番町平和ビル6F | 詳細ページ |
| 秋田県 | 0570-078386 | 〒010-0001 秋田県秋田市中通5-1-51 北都ビルディング6F | 詳細ページ |
| 山形県 | 0570-078381 | 〒990-0042 山形県山形市七日町2-7-10 NANA BEANS8F | 詳細ページ |
| 福島県 | 0570-078370 | 〒960-8131 福島県福島市北五老内町7-5 イズム37ビル4F | 詳細ページ |
| 都道府県 | 電話番号 | 住所 | ホームページ |
|---|---|---|---|
| 茨城県 | 0570-078317 | 〒310-0062 茨城県水戸市大町3-4-36 大町ビル3F | 詳細ページ |
| 栃木県 | 0570-078318 | 〒320-0033 栃木県宇都宮市本町4-15 宇都宮NIビル2F | 詳細ページ |
| 群馬県 | 0570-078320 | 〒371-0022 群馬県前橋市千代田町2-3-12 しののめ信金前橋営業部ビル4F | 詳細ページ |
| 埼玉県 | 0570-078312 | 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-17-15 さいたま商工会議所会館6F | 詳細ページ |
| 千葉県 | 0570-078315 | 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-5-1 Qiball(きぼーる)2F | 詳細ページ |
| 東京都 | 0570-078301 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル13F | 詳細ページ |
| 神奈川県 | 0570-078308 | 〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町2 産業貿易センタービル10F | 詳細ページ |
| 都道府県 | 電話番号 | 住所 | ホームページ |
|---|---|---|---|
| 新潟県 | 0570-078328 | 〒951-8116 新潟県新潟市中央区東中通1番町86-51 新潟東中通ビル2F | 詳細ページ |
| 富山県 | 0570-078351 | 〒930-0076 富山県富山市長柄町3-4-1 富山県弁護士会館1F | 詳細ページ |
| 石川県 | 0570-078349 | 〒920-0937 石川県金沢市丸の内7-36 金沢弁護士会館内 | 詳細ページ |
| 福井県 | 0570-078348 | 〒910-0004 福井県福井市宝永4-3-1 サクラNビル2F | 詳細ページ |
| 岐阜県 | 0570-078345 | 〒500-8812 岐阜県岐阜市美江寺町1-27 第一住宅ビル2F | 詳細ページ |
| 三重県 | 0570-078344 | 〒514-0033 三重県津市丸之内34-5 津中央ビル6階 | 詳細ページ |
| 愛知県 | 0570-078341 | 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄4-1-8 栄サンシティービル15F | 詳細ページ |
| 都道府県 | 電話番号 | 住所 | ホームページ |
|---|---|---|---|
| 滋賀県 | 0570-078339 | 〒520-0047 滋賀県大津市浜大津1-2-22 大津商中三楽ビル5F | 詳細ページ |
| 京都府 | 0570-078332 | 〒604-8187 京都府京都市中京区御池通東洞院西入笹屋町435 京都御池第一生命ビル3F | 詳細ページ |
| 大阪府 | 0570-078329 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満1-12-5 大阪弁護士会館B1F | 詳細ページ |
| 兵庫県 | 0570-078334 | 〒650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー13F | 詳細ページ |
| 奈良県 | 0570-078338 | 〒630-8241 奈良県奈良市高天町38-3 近鉄高天ビル6F | 詳細ページ |
| 和歌山県 | 0570-078340 | 〒640-8152 和歌山県和歌山市九番丁9-15 九番丁MGビル6F | 詳細ページ |
| 都道府県 | 電話番号 | 住所 | ホームページ |
|---|---|---|---|
| 鳥取県 | 0570-078357 | 〒680-0022 鳥取県鳥取市西町2-311 鳥取市福祉文化会館5F | 詳細ページ |
| 島根県 | 0570-078358 | 〒690-0884 島根県松江市南田町60 | 詳細ページ |
| 岡山県 | 0570-078354 | 〒700-0817 岡山県岡山市北区弓之町2-15 弓之町シティセンタービル2F | 詳細ページ |
| 広島県 | 0570-078352 | 〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀2-31 広島鴻池ビル1F | 詳細ページ |
| 山口県 | 0570-078353 | 〒753-0045 山口県山口市黄金町1-10 菜花道門キューブ2F | 詳細ページ |
| 徳島県 | 0570-078394 | 〒770-0834 徳島県徳島市元町1-24 アミコビル3F | 詳細ページ |
| 香川県 | 0570-078393 | 〒760-0023 香川県高松市寿町2-3-11 高松丸田ビル8F | 詳細ページ |
| 愛媛県 | 0570-078396 | 〒790-0001 愛媛県松山市一番町4-1-11 共栄興産一番町ビル4F | 詳細ページ |
| 高知県 | 0570-078395 | 〒780-0870 高知県高知市本町4-1-37 丸ノ内ビル2F | 詳細ページ |
| 都道府県 | 電話番号 | 住所 | ホームページ |
|---|---|---|---|
| 福岡県 | 0570-078359 | 〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通5-14-12 南天神ビル4F | 詳細ページ |
| 佐賀県 | 0570-078361 | 〒840-0801 佐賀県佐賀市駅前中央1-4-8 太陽生命佐賀ビル3F | 詳細ページ |
| 長崎県 | 0570-078362 | 〒850-0875 長崎県長崎市栄町1-25 長崎MSビル2F | 詳細ページ |
| 熊本県 | 0570-078365 | 〒860-0844 熊本県熊本市中央区水道町1-23 加地ビル3F | 詳細ページ |
| 大分県 | 0570-078363 | 〒870-0045 大分県大分市城崎町2-1-7 | 詳細ページ |
| 宮崎県 | 0570-078367 | 〒880-0803 宮崎県宮崎市旭1-2-2 宮崎県企業局3F | 詳細ページ |
| 鹿児島県 | 0570-078366 | 〒892-0828 鹿児島県鹿児島市金生町4-10 アーバンスクエア鹿児島ビル6F | 詳細ページ |
| 沖縄県 | 0570-078368 | 〒900-0023 沖縄県那覇市楚辺1-5-17 プロフェスビル那覇2・3F | 詳細ページ |
3.全国の弁護士会の法律相談センター
各都道府県に設置されている弁護士会が運営する法律相談センターも、借金問題や自己破産について相談できる窓口のひとつです。
弁護士会の相談は原則有料ですが、自己破産や債務整理の相談は無料で受け付けている場合があります。
弁護士会は、特定の営利目的を持たず中立的な立場からアドバイスを受けられるという点で高い信頼性があり、安心して相談できます。
都道府県名と「弁護士会 法律相談センター」を組み合わせてインターネットで検索すれば、最寄りの相談センターの情報を見つけることができるでしょう。
10分程度の電話無料相談にも対応しているため、気軽に相談してみましょう。
【47都道府県】弁護士会の法律センター一覧
| 都道府県 | 電話番号 | 住所 | ホームページ |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 03-3581-2201 | 〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館6階 | 詳細を見る |
| 神奈川県 | 045-211-7707 | 〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通9 | 詳細を見る |
| 千葉県 | 043-227-8431 | 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-13-9 | 詳細を見る |
| 埼玉県 | 048-863-5255 | 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂4-7-20 | 詳細を見る |
| 茨城県 | 029-221-3501 | 〒310-0062 茨城県水戸市大町2-2-75 | 詳細を見る |
| 栃木県 | 028-689-9000 | 〒320-0845 栃木県宇都宮市明保野町1-6 | 詳細を見る |
| 群馬県 | 027-233-4804 | 〒371-0026 群馬県前橋市大手町3-6-6 | 詳細を見る |
| 都道府県 | 電話番号 | 住所 | ホームページ |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 011-281-2428 | 〒060-0001 北海道札幌市中央区北一条西10丁目 札幌弁護士会館7F | 詳細を見る |
| 青森県 | 017-777-7285 | 〒030-0861 青森県青森市長島1-3-1 日本赤十字社青森県支部ビル5F | 詳細を見る |
| 岩手県 | 019-651-5095 | 〒020-0022 岩手県盛岡市大通1-2-1 サンビル2階 | 詳細を見る |
| 宮城県 | 022-223-1001 | 〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町2-9-18 | 詳細を見る |
| 秋田県 | 018-862-3770 | 〒010-0951 秋田県秋田市山王6-2-7 | 詳細を見る |
| 山形県 | 023-622-2234 | 〒990-0042 山形県山形市七日町2-7-10 NANA BEANS8階 | 詳細を見る |
| 福島県 | 024-534-2334 | 〒960-8115 福島県福島市山下町4-24 | 詳細を見る |
| 都道府県 | 電話番号 | 住所 | ホームページ |
|---|---|---|---|
| 新潟県 | 025-222-5533 | 〒951-8126 新潟県新潟市中央区学校町通一番町1 新潟地裁内 | 詳細を見る |
| 富山県 | 076-421-4811 | 〒930-0076 富山県富山市長柄町3-4-1 | 詳細を見る |
| 石川県 | 076-221-0242 | 〒920-0937 石川県金沢市丸の内7-36 | 詳細を見る |
| 福井県 | 0776-23-5255 | 〒910-0004 福井県福井市宝永4-3-1 三井生命ビル7階 | 詳細を見る |
| 岐阜県 | 058-265-0020 | 〒500-8811 岐阜県岐阜市端詰町22 | 詳細を見る |
| 三重県 | 059-228-2232 | 〒514-0032 三重県津市中央3-23 | 詳細を見る |
| 愛知県 | 052-203-1651 | 〒460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸1-4-2 | 詳細を見る |
| 都道府県 | 電話番号 | 住所 | ホームページ |
|---|---|---|---|
| 滋賀県 | 077-522-2013 | 〒520-0051 滋賀県大津市梅林1-3-3 | 詳細を見る |
| 京都府 | 075-231-2378 | 〒604-0971 京都府京都市中京区富小路通丸太町下ル | 詳細を見る |
| 大阪府 | 06-6364-0251 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満1-12-5 | 詳細を見る |
| 兵庫県 | 078-341-7061 | 〒650-0016 兵庫県神戸市中央区橘通1-4-3 | 詳細を見る |
| 奈良県 | 0742-22-2035 | 〒630-8237 奈良県奈良市中筋町22-1 | 詳細を見る |
| 和歌山県 | 073-422-4580 | 〒640-8144 和歌山県和歌山市四番丁5 | 詳細を見る |
| 都道府県 | 電話番号 | 住所 | ホームページ |
|---|---|---|---|
| 鳥取県 | 0857-22-3912 | 〒680-0011 鳥取県鳥取市東町2-221-10-52 | 詳細を見る |
| 島根県 | 0852-21-3225 | 〒690-0886 島根県松江市母衣町55-4 松江商工会議所ビル7F | 詳細を見る |
| 岡山県 | 086-223-4401 | 〒700-0807 岡山県岡山市北区南方1-8-29 | 詳細を見る |
| 広島県 | 082-228-0230 | 〒730-0012 広島県広島市中区上八丁堀2-73 | 詳細を見る |
| 山口県 | 083-922-0087 | 〒753-0045 山口県山口市黄金町2-15 | 詳細を見る |
| 徳島県 | 088-652-5768 | 〒770-0855 徳島県徳島市新蔵町1-31 | 詳細を見る |
| 香川県 | 087-822-3693 | 〒760-0033 香川県高松市丸の内2-22 | 詳細を見る |
| 愛媛県 | 089-941-6279 | 〒790-0003 愛媛県松山市三番町4-8-8 | 詳細を見る |
| 高知県 | 088-872-0324 | 〒780-0928 高知県高知市越前町1-5-7 | 詳細を見る |
| 都道府県 | 電話番号 | 住所 | ホームページ |
|---|---|---|---|
| 福岡県 | 092-741-6416 | 〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通5-14-12 南天神ビル4F | 詳細を見る |
| 佐賀県 | 0952-24-3411 | 〒840-0833 佐賀県佐賀市中の小路7-19 | 詳細を見る |
| 長崎県 | 095-824-3903 | 〒850-0875 長崎県長崎市栄町1-25 長崎MSビル4F | 詳細を見る |
| 熊本県 | 096-325-0913 | 〒860-0078 熊本県熊本市中央区京町1-13-11 | 詳細を見る |
| 大分県 | 097-536-1458 | 〒870-0047 大分県大分市中島西1-3-14 | 詳細を見る |
| 宮崎県 | 0985-22-2466 | 〒880-0803 宮崎県宮崎市旭1-8-45 | 詳細を見る |
| 鹿児島県 | 099-226-3765 | 〒892-0815 鹿児島県鹿児島市易居町2-3 | 詳細を見る |
| 沖縄県 | 098-865-3737 | 〒900-0014 沖縄県那覇市松尾2-2-26-6 | 詳細を見る |
4.全国の司法書士会の司法書士総合相談センター
全国の司法書士会が運営する司法書士総合相談センターも、自己破産を含む借金問題について相談できる窓口のひとつ。
各司法書士会に所属する専門知識を持った司法書士が、多重債務や任意整理、個人再生、そして自己破産といった債務整理全般に関する相談を受け付けています。
相談料は原則有料ですが、初回は無料で相談できたり無料相談会を設けていたりするため、各都道府県の司法書士会ホームページで確認してください。
全国の都道府県ごとに司法書士会と相談センターが設置されており、近くの窓口で相談できるのが利点です。
借金問題に精通した司法書士から、法的に適切で現実的なアドバイスを受けることができるでしょう。
5. 役所などの地方自治体の無料相談
お住まいの市区町村役場など地方自治体が主催する無料法律相談会も、身近な相談先として利用を検討できます。
住民サービスの一環として、地域住民が抱えるさまざまな法律問題を気軽に専門家に相談できる機会を設けていることが多いです。
最大のメリットは、役場などアクセスしやすい場所で相談できる点。
ただし、あくまで法律問題に関する初期的なアドバイスや情報提供を目的としていることが多く、相談時間も1人あたり20分~30分程度と短く限られているのが一般的です。
自己破産の具体的な手続きの依頼や、複雑な個別事情への踏み込んだ対応までは難しいかもしれません。
相談を担当する弁護士も毎回同じとは限らず、継続的な相談には向かないでしょう。
しかし、まずは話を聞いてもらいたい、どこに相談すればよいかわからないといった場合の最初のステップとして活用するには有効な選択肢といえるでしょう。
開催日時や予約方法は、お住まいの市区町村の広報誌や公式Webサイトの「広報」「お知らせ」といったコーナーで確認できます。
6.日本クレジットカウンセリング協会 多重債務ほっとライン
「複数の貸金業者からの借入れが重なり返済が困難になっている」、いわゆる多重債務の状態に陥っている方のために、公益財団法人日本クレジットカウンセリング協会(JCCO)が無料の電話相談窓口「多重債務ほっとライン」を開設しています。
大きな特徴は、電話一本で予約なしに相談できる手軽さ。
誰にも知られずに専門家の意見を聞いてみたいという方にとって、非常に利用しやすい窓口です。
「多重債務ほっとライン」では、専門のカウンセラーが借金の状況や家計の収支を丁寧に聞き取り、問題点を整理することから開始。
そのうえで、家計の見直しや具体的な返済計画の立て方について、親身になってアドバイスを提供してくれます。
カウンセラーは、相談者の状況に合わせて任意整理(債権者と交渉して返済額や期間を見直す方法)など、他の債務整理の方法についても検討し、手続きを支援してくれる場合もあります。
7.日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
消費者金融やクレジットカード会社といった貸金業者からの借入れに関するトラブルや悩みがある方におすすめなのが、日本貸金業協会が設置している「貸金業相談・紛争解決センター」。
貸金業法に基づき金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関で、貸金業に関するさまざまな相談や苦情を無料で受け付けています。
たとえば「返済が苦しい」「借金の整理について相談したい」といった一般的な相談から、「法律で定められた上限金利を超えた利息を請求されている」「脅迫的な取り立てを受けている」といった、貸金業者の対応に関する具体的なトラブルまで幅広く対応しています。
相談内容によっては、弁護士や司法書士といった法律の専門家への橋渡しもおこなってくれるため、具体的な手続きが必要になった場合でも安心です。
全国どこからでも利用可能で、相談方法は電話または協会のWebサイト上の専用フォームから受け付けています。
8.全国銀行協会相談室
銀行からのカードローンや住宅ローンなどの借入れに関して悩みやトラブルを抱えている場合は、全国銀行協会が運営する「全国銀行協会相談室」も相談先のひとつとして挙げられます。
たとえば、「銀行ローンの返済が困難になってしまった」「返済計画の見直しについて相談したい」「銀行との間でトラブルが発生している」といった場合におすすめです。
銀行業務に関するさまざまな相談や苦情を受け付けており、利用者と銀行との間の紛争解決を支援する役割も担っています。
また相談内容に応じて、問題解決のための情報提供やアドバイス、場合によっては銀行との間のあっせん(話し合いの仲介)をおこなってくれることもあります。
ただし、あくまで銀行との間の問題に特化した窓口であり、消費者金融や信販会社からの借入れについては対象外となる点に注意が必要です。
相談料は無料で、対面と電話の両方に対応しています。
【失敗しないために】弁護士を選ぶときのポイント

自己破産の手続きをスムーズに進めるためには、信頼でき、かつ自己破産案件に精通した弁護士を選ぶことが極めて重要です。
自己破産を依頼する弁護士を選ぶ際に、特に注意したい5つのポイントを詳しく解説します。
1. 債務整理が得意な専門弁護士を選ぶ
弁護士を選ぶ上で最も重要なポイントは、その弁護士が債務整理、特に自己破産の手続きに豊富な経験と実績を持っているかどうかです。
弁護士といっても、離婚問題、交通事故、企業法務などそれぞれ得意とする分野は異なります。
債務整理や自己破産の実績が多い弁護士は、さまざまなケースに対応してきた経験から、手続きを円滑に進めるためのノウハウを持っており、予期せぬ問題が発生した場合でも的確に対処してくれる可能性が高いでしょう。
また、自己破産は弁護士に無料相談するのがおすすめ。
司法書士は140万円以下の案件を担当することができません。
また複雑な手続きを全て任せられるため、専門的な知識がなくても自己破産をスムーズに進められるでしょう。
|
依頼内容 |
弁護士 |
司法書士 |
|---|---|---|
|
自己破産 |
代理人 |
書類作成のみ |
|
個人再生 |
代理人 |
書類作成のみ |
|
任意整理(債権額が140万円を超える場合) |
代理人 |
× |
|
任意整理(債権額が140万円以下の場合) |
代理人 |
代理人(ただし認定司法書士のみ) |
2.費用を明確に提示してくれる弁護士を選ぶ
弁護士を選ぶ際には、費用について明確な料金体系を提示し、支払い方法についても柔軟に対応してくれる事務所を選ぶことが大切です。
無料相談の段階で、費用の内訳と具体的な見積もりを出してもらいましょう。
費用に関する説明が曖昧だったり、あとから追加費用が発生する可能性について明確な説明がなかったりする事務所は、後々のトラブルにつながる可能性があるため避けた方が賢明です。
また、費用の分割払いや後払い制度に対応しているかどうかも重要な確認ポイント。
無理なく支払える計画を立てられる事務所を選ぶことが、安心して手続きを進めるための鍵となります。
3.コミュニケーションがとりやすい弁護士を選ぶ
弁護士を選ぶ際には、専門知識や実績だけでなく、相性やコミュニケーションの取りやすさも非常に重要な要素となります。
無料相談を利用する際には、弁護士が親身になってあなたの話に耳を傾けてくれるか、専門的な法律用語を避け、分かりやすい言葉で丁寧に説明してくれるかといった点を注意深く観察しましょう。
高圧的な態度をとったり質問しにくい雰囲気を出したりする弁護士では、不安なことや疑問点を率直に伝えることができず、後々すれ違いが生じる可能性もあります。
4.電話やオンライン相談に対応しているかを確認する
自己破産の手続き中は弁護士と何度も打ち合わせをおこなうため、電話やZoomなどのビデオ会議システムを利用したオンラインでの相談や打ち合わせに対応している弁護士を選ぶと、負担を軽減できます。
最近では初回相談から契約、その後の打ち合わせまでほとんどをオンラインで完結できる事務所も増えています。※実際に依頼をする場合には少なくとも1回は直接対面で面談をする必要がありますので一度は足を運べる場所にある事務所を選びましょう。
反対に、「対面で打ち合わせをおこなうほうが安心できる」という方も、法律事務所が自宅や最寄り駅からアクセスしやすい場所にあるかを確認しましょう。
5.複数の弁護士を比較検討する
最適な弁護士を見つけるためには、最初からひとつの事務所に絞らず、複数の法律事務所で無料相談を受けて比較検討するのがおすすめ。
それぞれの弁護士から現在の状況に対する見解や自己破産手続きの見通し、考えられるリスクなどの説明を受ければ、より客観的で多角的な視点から自身の状況を理解できます。
また、提示される弁護士費用や支払い方法、弁護士との相性を具体的に比較検討することが可能です。
無料相談におこなったからといって必ずしも契約する必要はないため、それぞれの相談内容を持ち帰り、じっくりと比較検討しましょう。
そのうえで、最も信頼できて自身に合っていると感じられる弁護士を選ぶことが、納得のいく結果につながります。
自己破産の無料相談へ行く前に準備しておくこと
無料相談を受ける際には、弁護士から聞かれる内容を想定して事前に準備をしておくと、相談時間をより有効活用できるだけでなく、弁護士から的確なアドバイスを引き出せます。
加えて、相談したいことや不安に思っていることを事前にメモにまとめておくと、聞き忘れを防げるでしょう。
自己破産の無料相談で聞かれる内容と必要なもの
弁護士は相談者の状況を正確に把握するために、以下のような点について質問します。
|
概要 |
聞かれる内容の詳細 |
関連する必要書類 |
|---|---|---|
|
借金の詳細 |
・借入先の会社名 |
・契約書 |
|
現在の生活状況 |
・収入(無職の場合はその旨と今後の見込み) |
・給与明細や源泉徴収票 |
|
財産 |
・不動産、自動車、預貯金、生命保険、有価証券などの有無や価値 |
・不動産の登記簿謄本 |
|
そのほか |
自己破産についての考え方や不安な点、希望 |
・不安点や疑問点をまとめたメモ |
借金の詳細から現在の生活状況、財産の有無、さらに自己破産以外の債務整理方法(任意整理や個人再生)についての考えや、自己破産手続きを進める上での不安な点などについても尋ねられることがあります。
これらの情報を整理し、関連する書類を持参してください。
また、身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)と印鑑も持参すると、スムーズに手続きの依頼へ進めます。
無料相談だけのつもりであっても、念のため持っていくとよいでしょう。
なお、弁護士に伝えるべきことは包み隠さず正直に話すのも重要。
特に借金の詳細、現在の苦しい生活状況、そして今後の生活で希望すること(たとえば、特定の財産を手元に残したい、保証人に迷惑をかけたくない)を具体的に伝えると、最適な解決策を提案してもらえます。
相談後は必ず依頼しなくても大丈夫
無料相談を受けたからといって、その場で必ず弁護士に依頼しなければならないということは決してありません。
相談の結果、自己破産以外の方法がよいと判断したり、他の弁護士の意見も聞いてみたいと考えたりすることもあるでしょう。
弁護士もその点は理解しているので、相談後に「少し考えさせてください」「家族と相談してから決めます」と伝えれば問題ありません。
もちろん、相談内容に納得し、この弁護士に任せたいと思えば、その場で依頼することも可能。
もし後日依頼することにした場合は、改めて電話などで連絡をとってください。
実際に依頼する際には、改めて弁護士費用の見積もりと支払い方法について書面で明確に提示してもらいましょう。
委任契約書の内容をしっかりと確認し、疑問点があれば納得いくまで質問してから契約することが大切です。
自己破産にかかる費用相場
自己破産は借金の支払い義務を免除してもらうための法的な手続きですが、まったく費用がかからないわけではありません。
手続きを進めるためには、裁判所に納める費用と弁護士に支払う費用が必要です。
自己破産にかかる費用の相場は20万円~80万円程度が一般的です。
裁判所費用(予納金)の相場:1万円~50万円以上
自己破産の手続きを裁判所に申し立てる際には、申立てに必要な手数料と、手続きを進めるための費用(予納金)を裁判所に納める必要があります。
|
|
同時廃止事件 |
少額管財事件 |
通常管財事件 |
|---|---|---|---|
|
申立手数料 |
1,500円 |
1,500円 |
1,500円 |
|
予納金 |
1万円~3万円 |
20万円~ |
50万円~ |
最も大きな負担となるのが「予納金」で、予納金は自己破産の手続きの種類によって金額が大きく異なります。
個人の自己破産で最も多いのが「同時廃止事件」と呼ばれる手続き。
申立人にめぼしい財産がなく、借金の経緯にも特に問題がない場合に選択されます。
この場合の予納金は1万円~3万円程度が相場となり、比較的低額です。
一方、一定以上の財産がある場合や借金の原因調査が必要な場合には「管財事件」となり、予納金は高額となります。
管財事件は、手続きが複雑で期間も長くなる「通常管財事件」(予納金50万円~)と、手続きを簡略化した「少額管財事件」(予納金20万円~)の2種類です。
どの手続きになるかは、個々の事案に応じて裁判所が判断します。
弁護士費用の相場:20万円~60万円以上
自己破産の手続きを弁護士に依頼する場合、別途弁護士費用が必要です。
弁護士費用は各法律事務所が独自に定めているため一律ではありませんが、一般的には「相談料」「着手金」「成功報酬」「実費」の4つで構成されています。
|
詳細 |
費用相場 |
|
|---|---|---|
|
相談料 |
弁護士に相談する際に発生する費用 |
30分5,000円~1万円程度 |
|
着手金 |
弁護士が事件に着手するときに支払うお金 |
10万円~50万円 |
|
成功報酬 |
裁判所から免責許可決定(借金の支払い義務が免除されること)が得られた場合に支払う費用 |
0円~30万円 |
|
実費 |
手続きを進める上で実際にかかった費用 |
1,000円以上 |
4つの費用を合計すると、弁護士に依頼した場合、裁判所費用とは別に20万円~60万円程度の費用がかかると考えておくのが一般的です。
ただし、費用体系は事務所によって異なるため、必ず事前に確認してください。
自己破産にかかる費用を抑えるコツ

裁判所費用や弁護士費用は決して安くはありませんが、これらの負担を軽減するための方法がいくつか存在します。
「お金がないから」という理由で自己破産を諦めてしまう前に、費用を抑えるためのコツを知っておいてください。
法テラスの民事法律扶助制度を利用する
自己破産にかかる費用を抑えるための最も代表的な方法のひとつが、法テラス(日本司法支援センター)が提供する「民事法律扶助制度」を利用すること。
経済的に余裕のない方を対象に、法テラスが一時的に弁護士費用および裁判所に納める予納金を立て替えてくれる制度です。
立て替え費用は自己破産終了後に分割して返済していくことになりますが、利息は発生せず、無理のない範囲で返済していけます。
ただし、制度利用には審査があり、結果が出るまでに一定の時間がかかる場合がある点には留意が必要。
また、利用するには収入や資産が一定の基準以下であることなどの要件を満たす必要があります。
弁護士費用を分割払い・後払いで支払う
弁護士費用の支払いが一括では難しい場合でも、多くの法律事務所では柔軟な支払い方法に対応しています。
特に債務整理を専門に扱っている事務所では、依頼者の経済状況に配慮し、費用の分割払いや後払いの相談に応じてくれるケースが一般的です。
分割払いであれば、月々の負担を抑えながら弁護士に依頼することが可能になります。
また後払いは、弁護士に依頼した時点で債権者からの取り立てがストップするため、それまで返済に充てていたお金を弁護士費用の支払いに充てることができるようになる、という仕組みを利用したもの。
すぐにまとまったお金を用意できなくても、まずは弁護士に依頼し、支払いの目途がついた段階で費用を支払うことが可能です。
無料相談の際には、分割払いが可能か、可能な場合は何回まで分割できるのか、月々の支払額はいくらになるのか、後払いに対応しているかなどを具体的に確認してみましょう。
生活保護の受給を検討する
収入がまったくない、あるいは著しく少なく生活していくこと自体が困難な状況にある場合は、生活保護の受給を検討するのも、結果的に自己破産費用の負担軽減につながる可能性があります。
生活保護を受給している方は、前述した法テラスの民事法律扶助制度で費用の立て替えを利用したとしても、事件終結後に返還免除の手続きをすれば原則としてその返済が免除されます。
つまり、生活保護の受給を続けている限り、事件終結後に返還免除の手続きをすれば立て替えてもらった費用を返還する必要がなくなるため、実質的に費用負担なく自己破産の手続きを進めることが可能です。
もちろん生活保護の受給には一定の要件があり、申請すれば必ず認められるものではありません。
しかし、もし受給の可能性がある状況であれば、自己破産の手続きと並行して、自治体の福祉事務所に相談してみる価値はあるでしょう。
なお、弁護士に相談する際に生活保護の申請についてもアドバイスを求めることができます。
自己破産を無料相談するなら「ベンナビ債務整理」

借金の返済に行き詰まり、日々の生活にも支障が出始めているのであれば、一人で悩み続ける必要はありません。
できるだけ早く借金問題の解決に詳しい法律の専門家、すなわち弁護士に相談することが、解決への最も確実な第一歩となります。
しかし、いざ弁護士を探そうとしてもどこに相談すればよいのか、どの弁護士が信頼できるのかと不安に思うかもしれません。
そのような時に役立つのが、弁護士検索ポータルサイト「ベンナビ債務整理」。
地域や相談内容(自己破産、任意整理など)、無料相談の可否、オンライン相談の対応など希望条件に合わせて、債務整理に強い弁護士を効率的に探すことができます。
まずは気軽に無料相談を利用して、専門家のアドバイスを受けてみませんか。
自己破産を弁護士に依頼するメリット
弁護士に依頼すると費用がかかるという側面はありますが、それを上回る多くのメリットがあります。
具体的には次のとおりです。
- 債権者からの取り立てがすぐに止まる
- 手続きがスムーズに進む
- 裁判所での対応も任せられる
- 免責が認められる可能性が高まる
- 精神的負担が軽減する
弁護士に依頼し、弁護士が債権者に対して受任通知を送付した時点で、消費者金融やクレジットカード会社などからの直接の取り立てや督促が法律上禁止され、すぐに止まります。
精神的なプレッシャーから解放され、落ち着いて手続きに臨むことができるでしょう。
また自己破産の手続きや書類作成は複雑なため、自分だけでおこなうのは極めて困難です。
書類の不備があれば手続きがなかなか進まないどころか、失敗に終わるリスクすらあります。
その点、弁護士は専門家のため、スムーズかつ正確に手続きを進めてくれます。
何より、自己破産や借金に関する不安や疑問をいつでも相談でき、精神的な負担が大幅に軽減されることが大きなメリットといえるでしょう。

無料相談できる弁護士一覧
自己破産を検討すべき状況と条件
自己破産を検討すべき主な状況は、自身の収入や資産では、抱えている借金の総額を返済していくことが客観的に見て不可能である場合。
自己破産が認められるための法律上の要件は、年齢や職業、借金の理由(一部例外を除く)ではなく、「支払不能の状態に陥っていること」です。
たとえば、以下のようなケースの場合、自己破産もやむを得ないと判断されやすいといえます。
- 退職金を受け取ったとしても、それで全ての借金を返済しきれない
- 安定した再就職の目処が立たず収入がない状態が続いている
- 年金収入だけでは日々の生活費を賄いつつ借金を返済していくことが到底不可能
借金をそのまま放置しておくと、遅延損害金が日々加算され、借金は雪だるま式に増え続けてしまいます。
また、いずれ給与や財産の差し押さえといった強制執行を受けるリスクも高まるでしょう。
自己破産をすることでこうしたリスクを回避し、借金の悩みから解放され、次の生活再建へのステップに進みやすくなる場合も少なくありません。
自己破産のメリット・デメリット
自己破産は、借金問題を根本的に解決し、人生を再スタートさせるための強力な法的手段です。
しかしメリットだけでなく、デメリットや注意すべき点も存在します。
自己破産のメリット
自己破産を選択する最大のメリットは、税金や養育費など一部の例外を除き、原則として全ての借金の支払い義務が法的に免除されること。
消費者金融からの借入れ、銀行のカードローン、クレジットカードの支払いなどどれだけ多額の借金を抱えていても、返済の必要がなくなります。
長年苦しんできた経済的な負担はもちろんのこと、「いつまで返済が続くのだろう」「取り立てが来るのではないか」といった精神的な苦痛からも解放され、新たな気持ちで生活を再スタートできるのです。
借金の返済に追われることがなくなるため、再就職などで収入を得られるようになった場合の収入を、借金返済ではなく自身や家族の生活費、将来のための貯蓄などに充てられます。
これは、経済的な再生を図る上で非常に大きな利点といえるでしょう。
自己破産のデメリット
自己破産のデメリットのひとつは、信用情報機関に事故情報として登録される点です。
登録期間は機関によって異なりますが、おおむね5年から10年間程度。
登録されている間は、新たにクレジットカードを作成したり、ローンを組んだりすることができなくなります。
また、一定以上の価値のある財産は、原則として処分しなければなりません。
たとえば、持ち家や土地などの不動産、自動車、解約した際に20万円以上の返戻金が見込める生命保険、99万円を超える現金などが対象です。
生活に必要な最低限の家財道具や仕事道具は手元に残せるものの、大切にしているものを手放さなくてはいけない可能性がある点は大きなデメリットといえます。
もし、どうしても持ち家を残したい場合は個人再生、特定の借金だけを整理したい場合は任意整理といった他の債務整理方法が適している場合もありますので、弁護士によく相談しましょう。
債務整理の選択肢:自己破産だけじゃない解決法があります
借金問題で悩んでいると、「自己破産しかない」と思いがちですが、実はほかにも道はあります。
あなたの状況に合った方法を選べば、将来への負担をぐっと減らせるかもしれません。
個人再生
個人再生は、借金を大きく減らしながらも少しずつ返済を続ける方法です。
借金が最大で10分の1になる可能性があり、マイホームを手放さなくても大丈夫なのが大きな特徴です。
毎月の収入がある程度あれば、返済計画が立てやすいですよ。
この方法は、次に挙げる条件に当てはまる方にとくにおすすめです。
安定した収入があれば、減額された借金を計画的に返済していくことができます。
- 借金の総額が5,000万円以下である
- 3~5年で返済の目処が立てられる
- 自宅を残したい
任意整理
任意整理は、お金を貸してくれた人と話し合って、将来の利息をカットしてもらう方法です。
裁判所に行かなくてもできる比較的シンプルな手続きで、過去に払いすぎた利息があれば取り戻せる可能性もあります。
また、持ち物を手放す必要がないのも大きなメリットです。
ただし、借りたお金自体(元本)は減らないので、借金が多い場合は負担軽減の効果が限られるかもしれません。
ただし、全ての貸し手が交渉に応じてくれるとは限らない点には注意が必要です。
さいごに
自己破産や借金問題について無料で利用できる相談窓口は多く存在し、経済的な負担を抑えながら適切なアドバイスや支援を受けられます。
たとえば各法律事務所では初回無料相談を受け付けているところが多く存在し、法テラスでは経済的に余裕のない方向けに無料法律相談や立替え制度を設けています。
各窓口は特徴がちがうため、状況に応じて、法律事務所・法テラス・自治体・各種協会などを上手に使い分けることが大切です。
無料相談を受けたからといって必ずしも依頼する必要はありません。
まずは気軽に相談し、自分にとって最善の方法を見つけましょう。
条件にあう弁護士を探す際には、「ベンナビ債務整理」が便利です。
初回無料相談や電話相談などに対応した弁護士を探せるので、ぜひ利用してみてください。

無料相談できる弁護士一覧

【東京メトロ『西新宿駅』2番出口、徒歩7分】【来所相談30分無料】【24時間予約受付】自己破産/個人再生/任意整理など、借金問題でお困りの方、ご相談いただければ最善の解決ができるように尽力いたします。まずは無料相談から!【秘密厳守】
事務所詳細を見る
【何度でも無料相談可】借金問題にお悩みの方、すぐにご相談ください!迅速・丁寧な対応で人生の再スタートをサポートします。電話・Web・休日夜間も対応【自己破産/個人再生/任意整理】
事務所詳細を見る
【初回相談30分無料】年間100件以上!の対応実績◎支払いの督促が来た/返済しきれず限界を感じているなど、早めにご相談ください!◆依頼者目線の丁寧かつ的確な対応には自信がございます【詳細は写真をクリック!】
事務所詳細を見る当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

自己破産に関する新着コラム
-
本記事では、自己破産における持ち家の取り扱いや、持ち家を手元に残しながら借金問題を解決する方法、弁護士に相談・依頼するメリットなどについてわかりやす...
-
生活保護受給中でも自己破産手続きは可能です。法テラスの弁護士費用立替制度を利用すれば、弁護士費用の自己負担なく借金を整理できます。生活保護と自己破産...
-
自己破産は借金の返済義務が免除される強力な手続きです。しかし、基本的には弁護士のサポートがなければ、手続きを進めることはできないので、弁護士費用を負...
-
自己破産後はクレジットカードが使えません。ブラックリストに載ることでもともとあるカードは強制解約になり、新規の作成もできなくなるためです。本記事では...
-
無条件で自己破産できるわけではなく、法律で定められた要件を満たさなくてはなりません。本記事では、自己破産ができないケースの具体例や、自己破産できない...
-
自己破産においては、債務者にとって有利なことばかりが起こるわけではありません。本記事では、自己破産のメリット・デメリット、自己破産をするときに弁護士...
-
自己破産をすると、多くの場合で携帯電話が強制解約となります。ただし、利用料金の滞納や分割払いの残債がなければこれまで通り利用できるほか、自己破産によ...
-
自己破産のデメリットには、ブラックリストに登録されることや職業・資格制限を受けることなどいくつかありますが、誤解されることも少なくありません。本記事...
-
自己破産をすると本人名義の持ち家や車などの財産が没収されるなど家族への影響も大きいです。ただし、家族名義の財産は没収されないうえ、将来の結婚や就職な...
-
自己破産は借金を帳消しにできる強力な手続きです。しかし、数多くのステップを踏む必要があるので、どの程度の期間がかかってしまうのか気になっている方も多...
自己破産に関する人気コラム
-
自己破産を検討されている方にとっては、破産後の生活は気になるところでしょう。この記事では、自己破産後に受ける制限や、生活を良くするために考えておきた...
-
廃課金とは、廃人と課金を合わせたネットスラングで、一般的に収入に見合わない金額を課金する人を指します。本記事では廃課金の定義や課金してしまう人の特徴...
-
自己破産では裁判所に支払う費用のほか、弁護士に依頼する場合は弁護士費用もかかります。状況により費用は異なり、弁護士費用は後払い可能な場合もあります。...
-
自己破産は、全ての借金の支払い義務を逃れ、所持する高価な財産を処分する法的手続きであり、生活をゼロから再建するための最終手段です。本記事では自己破産...
-
ブラックリストに掲載される期間はどの程度なのでしょうか。 よく、「ブラックリストに載るとカードが作れない」などという話を聞きますが、そもそもブラック...
-
破産宣告(はさんせんこく)とは何かを解説!手続きの流れや条件、かかる費用に加えて、自己破産を最短で進める為の方法をご紹介していきます。自己破産にはデ...
-
結論からいいますと、借金がある状態でも生活保護を受けることができます。そこで、生活保護と借金の関係を深堀していきたいと思います。
-
自己破産はできる条件があります。これに該当しない場合には自己破産が実現できず借金を免責することができません。この記事では、自己破産ができない4つのケ...
-
自己破産をする上で、破産管財人(はさんかんざいにん)が何をするのか、どのような人なのかを知っておくことで、免責を受けられる可能性が高まります。この記...
-
奨学金を借りたはいいものの、就職後も返済が厳しく破産に追い込まれる件数は1万件にのぼっています。ただし、破産にはリスクがあり、あなたの借金が免除され...
自己破産の関連コラム
-
自己破産をする上で、破産管財人(はさんかんざいにん)が何をするのか、どのような人なのかを知っておくことで、免責を受けられる可能性が高まります。この記...
-
カードローンの利用で借金がかさんでしまい、返済の目途が立たなくなってしまったら、自己破産について冷静に検討しましょう。本記事では、カードローンの借金...
-
同時廃止は自己破産の一種で、費用を抑えつつ、短期間で借金をゼロにできるものです。ただ、誰でも同時廃止できるとは限りません。この記事では、同時廃止する...
-
過去に自己破産をしたけれど、現在の交際相手とどうしても結婚したい。無事に結婚できるのか心配ですよね。この記事では自己破産をした人が果たして結婚できる...
-
自己破産と任意整理は、いずれも借金などの負担を解消・軽減できる「債務整理」の代表的な手法です。本記事では、自己破産と任意整理の違いや、債務整理手続き...
-
自己破産後でも事業再建や企業のために融資は必要不可欠でしょう。では自己破産者に融資をしてくれる機関はあるのでしょうか?この記事では自己破産者にも融資...
-
保証債務とは、債務者が債務の履行をしない場合、保証人が代わりに履行しなければならない債務のことです。砕いて説明すると、借金をしている本人が返済できな...
-
自己破産をしてもクレジットカードを利用したいですよね?クレジットカードは利用できませんが、代わりになる2枚の便利なカードをご紹介します。この2枚のカ...
-
不景気な昨今、少しでも将来の蓄えを増やすために株式投資を始める人が増えてきています。しかしながら、株式投資による成功する人は一握りであり、失敗により...
-
自己破産すると、官報(かんぽう)という国が発行する文書に氏名などが記載されます。ただ、これが原因で自己破産がバレてしまうことはほとんどありません。こ...
-
自己破産をすると、多くの場合で携帯電話が強制解約となります。ただし、利用料金の滞納や分割払いの残債がなければこれまで通り利用できるほか、自己破産によ...
-
自己破産した後にローンを組む場合、5~10年の期間を空ける必要があります。この記事では、自己破産後にローン審査に通るための条件やローン審査に通りやす...
弁護士・司法書士があなたの借金返済をサポート
債務整理では、債権者と交渉する任意整理や法的に借金を減額する、個人再生や自己破産などがあります。また、過去の過払い金がある方は、過払い請求を行うことも可能です。
ただ、どれもある程度の法的な知識や交渉力が必要になってきます。債務整理をしたくてもなかなか踏み切れないあなたをベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)の弁護士・司法書士がサポートいたします。
自己破産をもっと知りたいあなたに