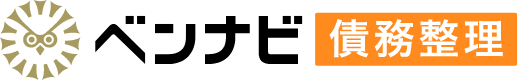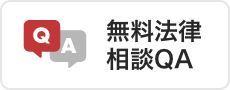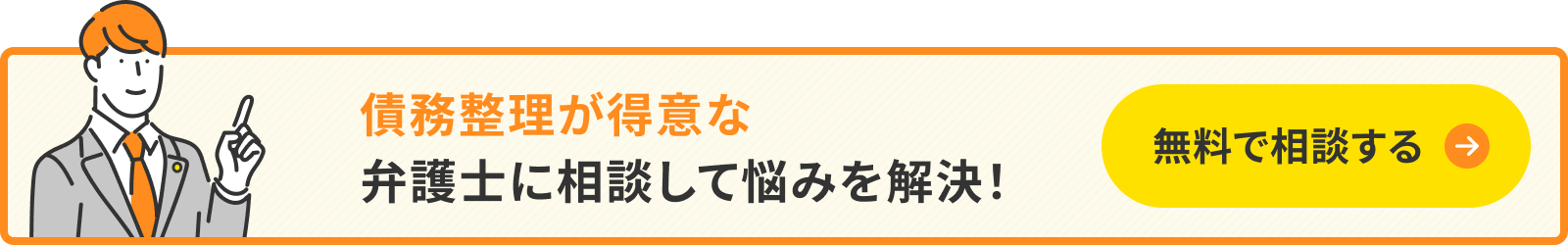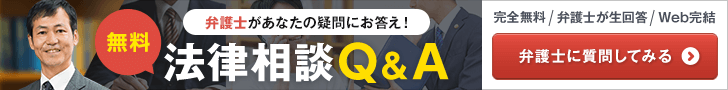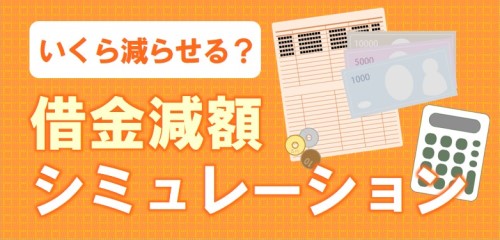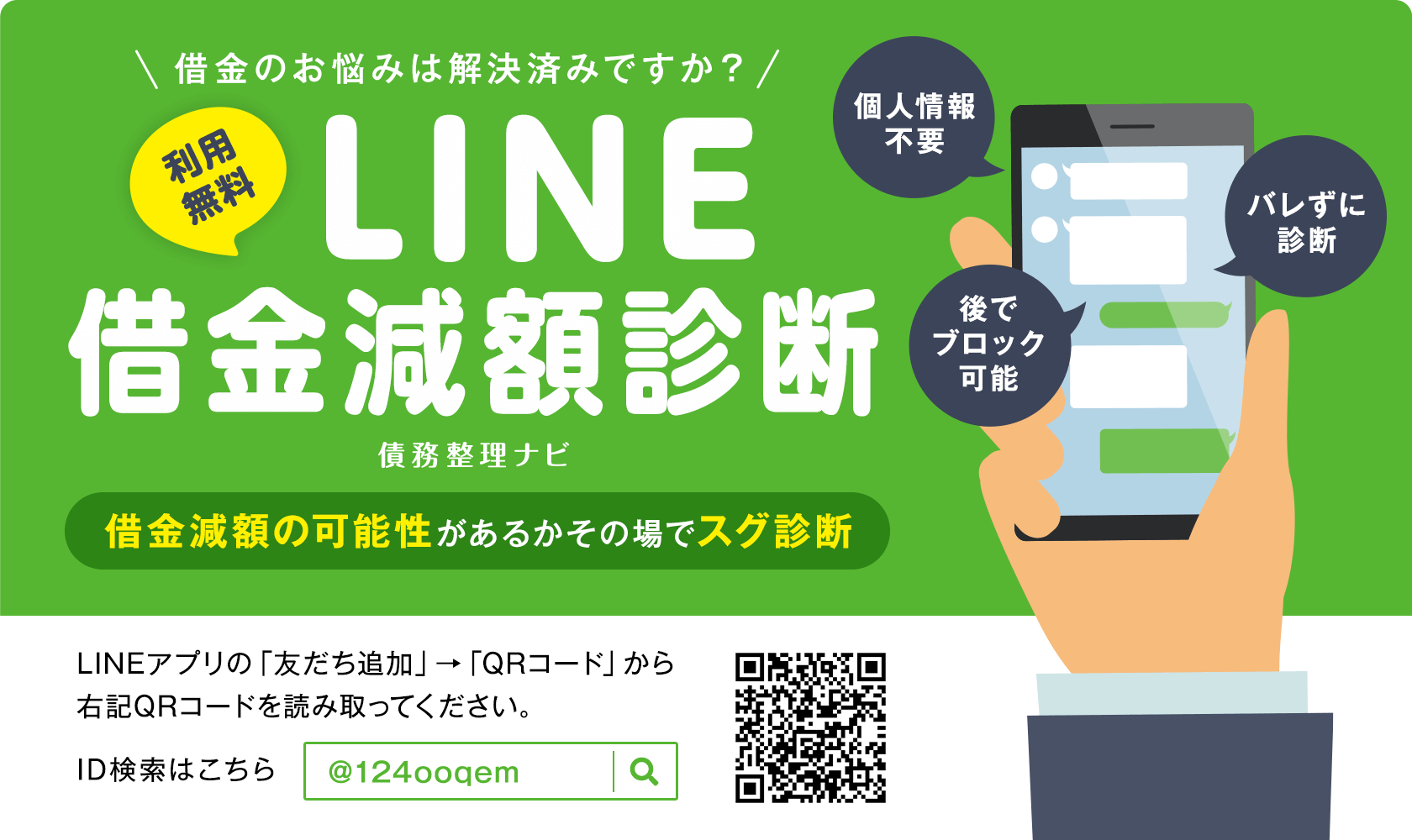国民健康保険を滞納するリスク|差し押さえ等の流れと滞納者がすべきこと


国民健康保険は国民皆保険と呼ばれるように、「20歳以上の社会保険未加入者は国民健康保険へ加入する義務」があるため、もし滞納をしている場合は必ず滞納分は支払わないといけません。
しかし、多額の借金を抱えている方や、自営業などで自分の保険のことまで頭が回らない方もいらっしゃると思います。
ですが、国民健康保険の滞納をそのままにしておくと、差し押さえのリスクもあり、最終的には健康保険がつかなくなってしまうため、今回は国民健康保険を滞納していた場合の対策をご紹介していきます。国民健康保険以外の借金問題に悩んでいる方へ
国民健康保険の滞納による借金は、税金や年金と同様に債務整理による解決ができません。
しかし、他の借金があるために国保の滞納が発生しているような場合、その借金問題を解決し、国保も分割払いなどで対応してもらうことで、滞納問題が解決するかもしれません。
初回相談が無料の弁護士事務所を多数掲載しているので、まずは相談してみましょう。
国民健康保険を滞納することによって生じるリスク
まず、最初に国民健康保険を滞納することによるデメリットについて紹介しますが、その前に多くの方が「国民健康は加入する必要があるのだろうか」という疑問を抱いているのではないでしょうか。
国民健康保険に加入しなかった場合どうなるのか?
そもそも国民健康保険は、病気や怪我などによる医療費を保険でまかなうための制度ですが、身体が丈夫な方など病院に行く機会があまりない人も当然います。
実際のところ、国民健康保険料の平均は、一人あたり8.3万円(年間)ですが、保険証を使用しない人にとってこの金額は決して安くありません。
国民健康保険への加入は国民の義務
しかしながら、国民健康保険への加入は国民全員の義務であり、いわば税金と同じだと思ってください。
そのため、国民健康保険に加入する必要性がない人でも、保健料を滞納することによるペナルティは平等に受けます。
滞納金に伴う延滞金
では、国民健康保険を滞納することによって生じるペナルティについて紹介していきますが、まず一点目に紹介できるのは、滞納金に伴う延滞金です。この延滞金とは、遅延損害金にあたるものですが、要は返済日を守らなかったことにより、滞納金に加算される罰金だと認識してください。
延滞金は、滞納料金×延滞金利率(年率)×延滞日数÷365日によって求められますが、東京都多摩市における延滞利率は以下の通りになります。
《延滞金率》
納期限の翌日から1ヶ月までの滞納
納期限の翌日から1ヶ月以降の滞納
平成11年まで
年7.3%
年14.6%
平成12年~13年まで
年4.5%
平成14年~18年まで
年4.1%
平成14年~18年まで
年4.4%
平成20年
年4.7%
平成21年
年4.5%
平成22年~25年
年4.3%
平成26年
年2.9%
年9.2%
平成27年
年2.8%
年9.1%
引用元:「国民健康保険の延滞金|多摩市」
管轄によって取り決めが異なるため、詳しくは最寄りの市(区)役所にてご確認ください。
保険証が使用できなくなる
国民健康保険料の滞納日数が重なるといずれ保険証が使用できなくなります。行政から保険証に代わる物が発行されますが、最終的には保険が適用されなくなり、医療費は全て自己負担です。保険証の使用の変化については、「滞納期間1年未満の場合」にて詳しく後述いたします。
差し押さえを受ける
国民健康保険を滞納することによる一番のリスクは、行政から滞納者の財産が差し押さえされることでしょう。
地方税法上において、保険料の納付期限後20日以内に滞納者へ督促状を発行することが定められていますが、法律上は督促状の発行日か10日経っても保険料の納付がなければ、差し押さえが可能となっております。
つまり、納付期限から30日が経てば、行政側は差し押さえすることができるわけなのですが、実務上、差し押さえ可能な保険料の滞納者の該当者全員に差し押さえを行うことは現実的でないとはいえ、いつでも差し押さえをすることができることを認識してください。
国民健康保険の滞納者は190万世帯
令和5年6月時点で、国民健康保険を一部でも滞納している世帯は190万世帯で、前年度と比較して0.1%増加しており、かなり多い数字になっています。
では、実際に差し押さえまでにどのような手順が踏まれていくのか、滞納者に対する行政側の対応について確認していきましょう。
国民健康保険を滞納における行政側の対応とその流れ
国民健康保険料を滞納し続けた場合、細かいところは各自治体によって対応は違いますが、まずは役所から滞納者に対して督促が行われます。
その際の方法はさまざまですが、文書、電話、自宅への直接訪問などで督促が行われるケースもあります。さらに滞納期間が長引くほど、あなたの保険証はどんどん使えなくなっていきます。
滞納期間1年未満|短期被保険者証の交付
国民健康保険の滞納が一年未満の場合、市区町村から通知書・電話などにより納付の催促が届き、それを無視していると「短期被保険者証」と呼ばれる、有効期間3ヶ月~6ヶ月程度の短い保険証が交付され、その都度支払いについて確認されることになります。
※各自治体によって異なる
滞納期間1年以上|被保険者資格証明書の交付
短期被保険者証の返還を求められ、代わりに「被保険者資格証明書」が交付されます。「被保険者資格証明書」とは、医者の診療を受けた際に、とりあえず窓口で全額負担し、後日申請により自己負担分以外を支給してもらうというものです。
ただ、実際は滞納している保険料と相殺され、戻ってこないことがほとんどです。
滞納期間1年6ヶ月以上|保険給付の停止
滞納期間が1年6ヶ月を超えると保険給付が停止され、病院で治療を受けた際も医療費は全額自己負担になり、本来還付されるお金の約7割が滞納分に充てられます。
滞納の催促に応じない場合|財産の差し押さえ
この時期、役所から差押予告の通知書が届いたら厳しい状況だと覚悟してください。この時期になると市区町村職員からの督促、納付相談のための連絡が頻繁になり、これ以降は「財産の差し押さえ」処分を受け、口座の凍結、給与差押えが起こるなどの事態になります。
差し押さえ執行の流れ
実際のところ差し押さえの対象となる資産は、滞納額によって異なりますが、預金と給与(1/4まで)が差し押さえられることがほとんどでしょう。
不動産や、動産(自宅にある滞納者の手持ち財産)は執行に高額な費用がかかる上、預金を差し押さえる際は銀行名と支店名、給与に関しては勤務先がわかっていれば差し押さえできるため、実務的な面で現実的なのです。
また、一般の差し押さえは裁判所へ申立手続きを行うため、差し押えが完了するまでにある程度の期間を要しますが、国民健康保険の滞納料金は行政への借金であるため、当然ながら申立手続きは必要ありません。
そのため、差し押さえの予告通知書が届いた段階で、いつ踏み込んでくるかわからないと思ってください。
国民健康保険の保険料納付にも時効がある
保険料の場合は2年、保険税の場合は3年〜5年となっていますが、「滞納を始めた日から時効成立日まで一度も請求が無かった場合」に時効が成立します。
途中で役所からの請求や差押え命令がくると、その時点で時効はストップしますので、現実的に時効を成立させることは不可能だと思って良いでしょう。
国民健康保険の滞納者が取るべき行動とは
国民健康保険料を滞納した人が行うべきことについて確認していきます。
滞納した国民健康保険について役所へ相談
国民健康保険の滞納を続けると、10割負担や差し押さえの可能性が高くなりますので、そうならないためにも、できるだけ早く役所へ相談に行きましょう。
担当者によっては国民健康保険の滞納分を分割や減免してくれる可能性があります。ここでは、「役所へ相談に行った際に減免を受ける為の対策」をまとめていきます。
保険料の減免が受けられる条件を確認する
役所に出向く前に一度、自分が減免を受けられるのかどうかを調べておきましょう。
例)大阪市の減免条件
-
・世帯所得の合計が基準額以下になった場合
-
・非自発的失業者(倒産・解雇など)になった場合
-
・退職・廃業・営業不振等になった場合
-
・災害にあった場合
-
・給付制限にあった場合
<7割・5割・2割軽減、3割軽減>
世帯人数 軽減の基準となる所得金額(単位 円) 7割軽減 5割軽減 2割軽減 3割軽減 1人 330,000 590,000
(575,000)800,000
(780,000)610,000 2人 850,000
(820,000)1,270,000
(1,230,000)890,000 3人 1,110,000
(1,065,000)1,740,000
(1,680,000)1,170,000 4人 1,370,000
(1,310,000)2,210,000
(2,130,000)1,450,000 引用元:国民健康保険料の減額・減免等
※( )内は、平成26年度の基準額
<非自発的失業者にかかる軽減>
軽減期間 離職年月日の翌日から翌年度末まで 軽減内容 ・所得割について給与所得を100分の30にして計算。
・平等割、均等割について、7、5、2割軽減及び3割軽減の判定の際は、給与所得を100分の30にして判定。すでに国民健康保険に加入している世帯に追加で加入の場合は、その年度の再判定は行なわない引用元:国民健康保険料の減額・減免等
<減免率表> ※左右にスライドします
前年中の所得金額 所得減少率 150万円 200万円 250万円 300万円 350万円 400万円 450万円 500万円 550万円 600万円 600万円 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 超 100% 100% 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 90%以上 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 80%以上 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 70%以上 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 60%以上 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 50%以上 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 40%以上 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 30%以上 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 引用元:国民健康保険料の減額・減免等
※所得減少率= 1-(平成27年中見込所得/平成26年中所得)
分割払いを申し出る
国民健康保険で滞納している分を分割払いにしてくれないかと申し出るのも有効な手です。また、「最低でも毎月●●●●円は払う」など、少額でも確実な計画を提示すると良いでしょう。
今の状況を正確に説明する
なぜ保険料を滞納する事態になっているのか、経済状況などを具体的説明しましょう。
-
・無職である
-
・借金返済に追われている
-
・自営業のため収入が安定しない など
やむをえない事情があれば、担当者も考慮してくれる可能性は少ないですがあると思います。
現在の状況を証明する証拠を揃える
より説得力や信憑性を高めるためには、その説明を裏付ける証拠を揃えておく必要があります。
-
・源泉徴収票や給与明細書
-
・住民税課税(非課税)証明書
-
・生活の実態をあらわす書類(家計簿など)
相談の最中に、話の進み具合に合わせて担当者に提示することで説得力が増します。
延滞金が発生していたら減免申請を申請する
保険料を延滞していると損害転勤や滞納料が発生している可能性もありますので、延滞金の減免申請も行ってみましょう。基本的に減免が認められることは少ないですが、場合によっては応じてくれる可能性もあります。
自身で保険料をまかなえない場合は家族の扶養に入る
もし自身で保険料の支払いが難しい減免措置が受けられない滞納者の方は、家族の扶養に入ることも解決方法の一つです。
扶養に入ることができれば、国民健康保険料を支払う必要がなくなりますが、同一世帯であれば3親等以内(親・兄弟・祖父母・叔母・甥・姪)までを扶養家族に含めることができます。また、扶養に関しては世帯の同一が条件であり同居の有無が問われないため、一人暮らしでも問題ありません。
扶養に入るための条件としては、自身の年収が130万円未満でありかつ、扶養家族の年収の1/2未満であることです。また、同一世帯でない場合、扶養家族からの援助金が自身の年収を上回っていることが条件になります。
債務整理で借金を大幅に減額できる可能性があります。
債務整理とは、借金返済を続けるのが難しい方のための救済制度です。

消費者金融や銀行のカードローン、クレジットカードのリボ払いなどの借金を大幅に減額することができます。
例えば、金利18%で150万円借り、毎月4万円を返済している人が任意整理した場合
【減額前】
月々の返済額:4万円
利息を含む総返済額:217万円
※小額でも追加で借入した場合、総返済額はもっと増えます。
【減額後】
月々の返済額:2.5万円
利息を含む総返済額:150万円
などのように、月々の返済額や、総返済額を減らせる可能性があります。
債務整理には『任意整理』の他に、借金総額を8割ほど減らせる『個人再生』や、借金をゼロにする『自己破産』もあります。
どの方法でも弁護士や司法書士があなたの代わりに手続きをしてくれるので、面倒な手間や複雑な手続きはありません。
弁護士・司法書士と相談し、あなたの状況に応じてベストな方法を選びましょう。
費用がいくらかかるかよく確認する
債務整理の手続きを弁護士・司法書士に依頼した場合、依頼費用がかかります。
依頼前に費用がいくらかかるかよく確認し、減額できる借金以上に依頼費用がかかる場合には、依頼を見合わせるなどの判断をしましょう。
分割払いや後払いに対応している事務所が多いため、今手持ちのお金がなくても、事務所によっては依頼可能なことがあります。
まずはお近くの事務所に無料相談しよう
まずはお近くの事務所に無料相談して、以下3点を確認しましょう。
・借金を減額できるか?いくら減らせるか?
・どの債務整理の方法が一番合うか?
・費用はいくらぐらいかかるか?
債務整理ナビでは、全国の事務所からお近くの事務所を簡単に探すことができます。借金問題の解決が得意な事務所のみを掲載しているので、どの事務所に相談してもOKです。
まずは、以下からお住まいの都道府県を選び、電話・メールで無料相談しましょう。
もちろんあなたの都合やプライバシーを配慮しますので、安心してご相談ください。
まとめ|とにかく早急に窓口へ相談!
国民健康保険を滞納していて良い事はひとつもありません。滞納を続けていると保険料の10割負担、給料の差し押さえなど、様々なリスクがあるのは今回お伝えした通りです。
まずは役所の窓口に相談に行き、現状の相談と少しでも減免できるように、話あう事が必要です。もし、借金などが理由で滞納をする事になっている場合は、下記の記事も参考にして頂ければ幸いです。

【借金の減額・免除で再スタート!】最短で催促ストップ◆家族や職場にバレにくい解決◆複数社から借り入れ、返済が苦しい等、当事務所へご相談ください【親身に対応◎】【秘密厳守】※個人間の金銭貸し借り・借金以外の一般法律相談に関する問い合わせは受け付けておりません。
事務所詳細を見る
「返済のために借入社数が増えてしまっている…」「借金総額が膨らんでわからなくなっている…」毎月の返済額の負担を軽減し、借金生活をやめたい方◆まずは最適な解決のために無料診断を◆
事務所詳細を見る
闇金問題の相談窓口【初回相談無料/分割払い・後払い対応】闇金問題に豊富な経験あり・月間400件以上の解決実績のある司法書士が違法な取り立てからお客様を解放します/任意整理・時効援用にも対応可<即日対応・24時間体制>
事務所詳細を見る当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

借金問題に関する新着コラム
-
基本的に、借金減額診断は危険なものではありません。信頼できる法律事務所が運営しているものなら、むしろ利用するメリットが大きいものです。 借金減額診...
-
LINE減額診断は、簡単な質問に答えるだけで借金の減額可能性を無料で診断できるサービスです。本記事では、診断の仕組みや利用方法、注意点を詳しく解説。...
-
リボ払いの借金がなかなか減らないと悩んでいませんか?本記事では、リボ払いを自力で完済する方法や、債務整理を活用して負担を軽減する方法を詳しく解説。高...
-
本記事では、時効援用で借金問題の解決を目指している方に向けて、時効援用について弁護士と相談できる窓口、弁護士に依頼するメリット、弁護士を選ぶときのポ...
-
催告書が届いたのに何の対応もしないままだと、民事訴訟を提起されたり、財産・給料などが差し押さえられたりするリスクが高まります。本記事では、催告書が届...
-
借金を長期間滞納していると債権者から裁判を起こされ給料が差し押さえられる恐れがあります。一度差し押さえを受けると解除するためには一括返済するか債務整...
-
本記事では、借金100万円の月々の返済額シミュレーション、借金100万円を自力で返済できるかどうかの判断ポイント、返済資金を工面したり金利を下げたり...
-
複数の借金を一つにまとめる「おまとめローン」で毎月の返済額を減らし、利息負担を軽減しませんか?メリット・デメリット、注意点、よくある質問などを詳しく...
-
本記事では、借金が返せないと悩んでいる方に向けて、借金が返せないときに相談できる窓口、借金が返せない緊急度別のおすすめ相談先、弁護士に相談して債務整...
-
借金の時効援用についてさまざまな疑問があると思います。そこで本記事では、時効援用と信用情報・事故情報について、信用情報機関別にわかりやすく解説します...
借金問題に関する人気コラム
-
借金の時効援用は、成功すればどれほど多額な借金でも返済を免除されます。しかし同時に、失敗すれば大きなリスクを背負う法律行為でもあります。 この記事...
-
専門家の助力があったとしても、今すぐブラックリストを削除することは難しいです。信用情報を回復させる方法、ブラックリストが消えるまでの期間、これ以上悪...
-
自己破産を検討されている方にとっては、破産後の生活は気になるところでしょう。この記事では、自己破産後に受ける制限や、生活を良くするために考えておきた...
-
債務者(さいむしゃ)とは、特定の債権者(さいけんしゃ)に対してお金を借りている、あるいは一定の給付義務を持つ人のことで、ローンの未払いや奨学金の滞納...
-
催告書(さいこくしょ)とは、滞納しているお金等を請求する際に送られてくる書類のことをいいます。この記事では、①催告書の意味②督促状との違い③すぐに払...
-
奨学金の返済額をしっかり把握していることで、利用後の返済計画が立てやすくなり、効率よく返済することができます。この記事では、返済額の相場とともに、返...
-
自分の知らない間に住民税を滞納しているケースは珍しくありません。この記事では、住民税を滞納するリスクや滞納した場合の対処法、支払いが困難な場合に活用...
-
自己破産は、全ての借金の支払い義務を逃れ、所持する高価な財産を処分する法的手続きであり、生活をゼロから再建するための最終手段です。本記事では自己破産...
-
国民健康保険は国民皆保険と呼ばれるように、「20歳以上の社会保険未加入者は国民健康保険へ加入する義務」があるため、もし滞納をしている場合は必ず滞納分...
-
奨学金が返せないとどうなるのか、皆さんはご存知でしょうか。今や大学生の約半数が利用している奨学金ですが、返せない人が増えていることが社会問題にもなっ...
借金問題の関連コラム
-
借金の返済に苦しみ、うつ病になってしまった。生活費、返済費用、社会復帰など日々の生活と将来への不安でいっぱいで切実な問題ですが、ひとつずつ解決してい...
-
090金融とは、固定電話・事務所を持たず携帯電話でのやり取りを行う金融会社のことです。ただ、固定電話を持たないことは貸金業法で禁止されているため、闇...
-
マイナンバー制度を介して、借金の事実が周りに知られるリスクがあるのか、またマイナンバーにおいて管理される個人情報についてまとめてみました。
-
買い物依存症とは、借金をしてまでも買い物を続けてしまう症状のことを言います。この記事では買い物依存症の特徴や対処法、すでに借金を作ってしまった人の解...
-
LINE減額診断は、簡単な質問に答えるだけで借金の減額可能性を無料で診断できるサービスです。本記事では、診断の仕組みや利用方法、注意点を詳しく解説。...
-
この記事では借金一本化のメリットやデメリット、どういった人が向いているか、任意整理や個人再生、自己破産などの他の債務整理を検討すべき人について解説し...
-
借金問題は早いうちに対処しておかなければ、家庭崩壊へと繋がる危険性もあります。自力での完済が難しい場合は、速やかに債務整理を行うのが良いでしょう。こ...
-
300万円の借金があっても、無理のない方法で完済することができます。この記事では、借金の支払回数や利息などを確認する方法、300万円の借金を無理なく...
-
ホストへの未収金は支払わなくてもいいケースがあります。弁護士に相談すれば支払い義務の有無を確認した上で適切な解決法を提案してもらえます。未収金に悩ん...
-
自己破産を検討されている方にとっては、破産後の生活は気になるところでしょう。この記事では、自己破産後に受ける制限や、生活を良くするために考えておきた...
-
自己破産は、全ての借金の支払い義務を逃れ、所持する高価な財産を処分する法的手続きであり、生活をゼロから再建するための最終手段です。本記事では自己破産...
-
専門家の助力があったとしても、今すぐブラックリストを削除することは難しいです。信用情報を回復させる方法、ブラックリストが消えるまでの期間、これ以上悪...
弁護士・司法書士があなたの借金返済をサポート
債務整理では、債権者と交渉する任意整理や法的に借金を減額する、個人再生や自己破産などがあります。また、過去の過払い金がある方は、過払い請求を行うことも可能です。
ただ、どれもある程度の法的な知識や交渉力が必要になってきます。債務整理をしたくてもなかなか踏み切れないあなたをベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)の弁護士・司法書士がサポートいたします。
借金問題の解決方法をもっと知りたいあなたに