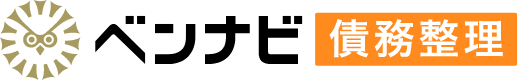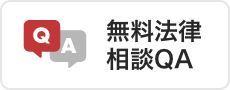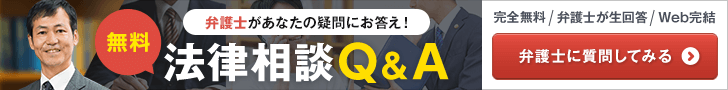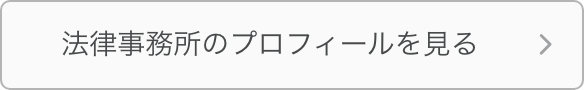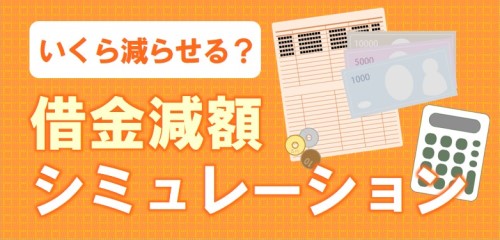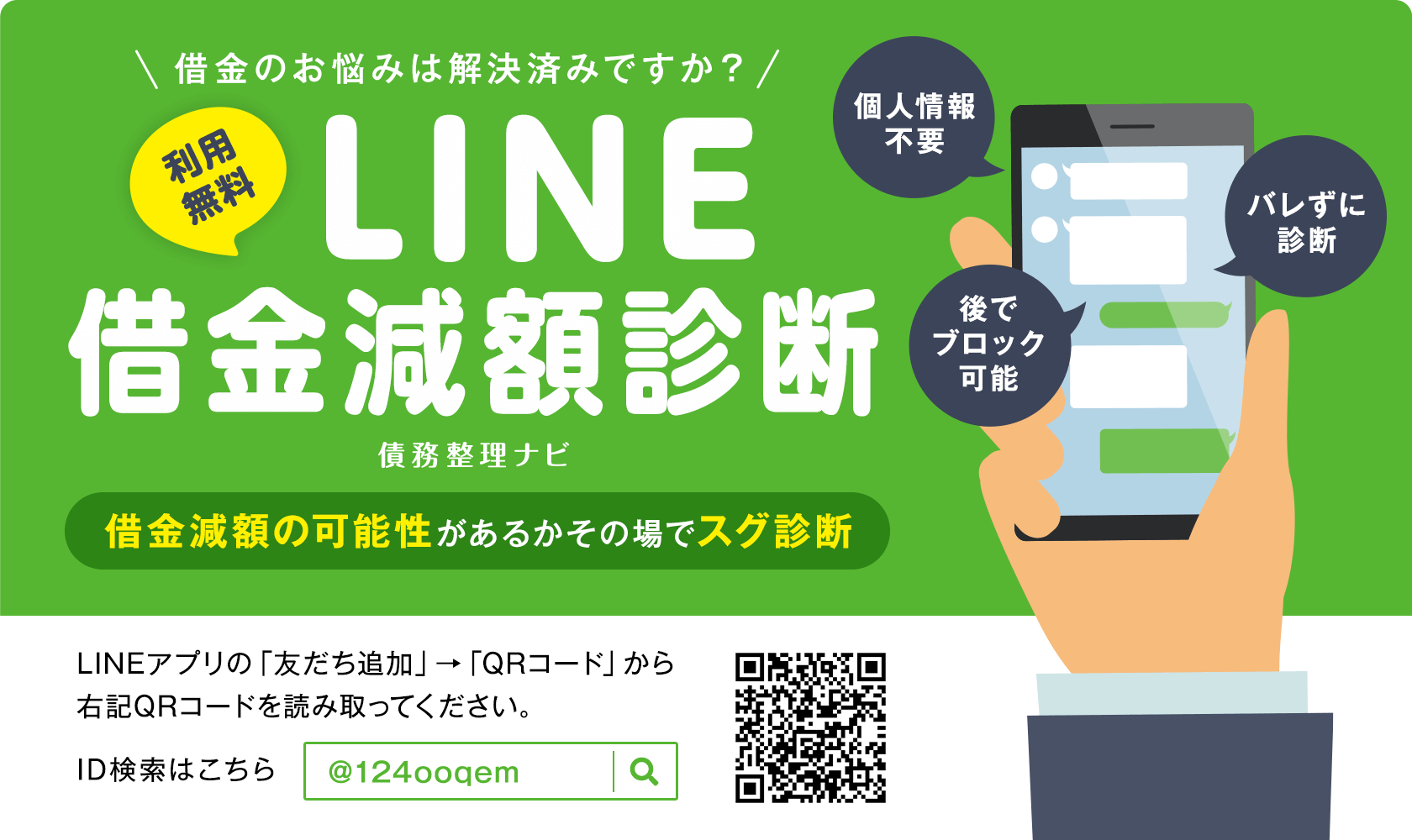過払い金の時効は10年?10年以上前の過払い金を請求する方法は?

過払い金請求は、借金を完済してから10年が経過すると時効となり、基本的には返還を求めることができなくなります。
しかし、全てのケースで請求が不可能になるわけではありません。
たとえば、過払い金請求対象の消費者金融から繰り返し借入をしている場合など、完済から10年以上経っている場合でも例外的に請求が認められるケースも存在します。
本記事では、過払い金請求の時効の仕組みを詳しく解説するとともに、10年経過後でも請求できる可能性があるケースについて紹介します。
「もう時効だから…」と諦める前に、ぜひ最後までチェックしてください。
過払い金は完済から10年以上経過で時効?それでも請求できるケースとは?
過払い金請求は借金の完済から10年が経過すると時効が成立する可能性があり、古い借金については返還請求に応じてもらえない恐れがあります。
ここでは、過払い金請求の時効の仕組みや、10年以上前に完済した借金についても過払い金請求ができる例外的なケースなどについて紹介します。
前提として過払い金請求の時効は最終取引日から10年
過払い金請求には消滅時効があり、完済から10年が経過すると請求ができなくなります。
過払い金請求権の時効は最終取引日を起算点とし、最後の返済や借入をした日から10年間です。
たとえば、2008年に借金を完済した場合、2018年には時効が成立し、原則として過払い金の請求はできなくなります。
民法改正により過払い金請求の時効が5年になる場合も
2020年4月1日に施行された改正民法により、過払い金請求の時効期間が従来の10年から5年に短縮されるケースが出てきました。
改正前の民法では、不法行為などによる金銭請求権の消滅時効は最終取引日から10年とされていましたが、改正後は債権者が請求できることを知った時点から5年、または最終取引日から10年のいずれか早いほうになったのです。
したがって、2020年4月1日以降に発生した過払い金については、請求できることを知った時点から5年が経過すると時効となる可能性があります。
また、2020年4月以降に完済した借金に関する過払い金請求権についても、2025年段階では裁判所による判例などが十分ではなく、民法改正後の基準である5年間が時効として適用される可能性がないとは言い切れません。
過払い金が発生しているかもしれない場合は、時効までの期間は必ずしも10年とは考えず、早めに弁護士に相談するのがおすすめです。
最終取引日がわからないときはどう確認すればよい?
過払い金請求の時効は最終取引日から起算されるため、この日付を正確に把握することが重要です。
最後の返済から長期間が経過している場合、取引明細書や契約書を紛失してしまい、最終取引日がわからないことも少なくありません。
その場合、まず取引していた貸金業者に取引履歴の開示請求をすることが有効です。
貸金業法19条により、金融業者には取引履歴の開示義務があるため、正規の業者であれば請求に応じるはずです。
ただし、金融業者は個人からの開示請求に対しては、後回しにしたり断片的な開示にとどめたりするなど好ましくない対応を取るケースも多いです。
そのため、取引履歴の開示に手間取っているあいだに時効が成立するといったリスクもあります。
過払い金請求をしたいが最終取引日がわからない場合は、弁護士などの専門家に依頼して取引履歴の開示をしてもらうのがおすすめです。
同じ貸金業者に別の借金があり「一連の取引」とみなされるなら請求が可能
原則として、過払い金の請求権は最終取引日から10年が経過すると時効が成立します。
しかし、10年以上過去に完済した借金であっても、同じ業者から新たに借入をしており、それが一連の取引とみなされる場合は、最終取引日が後ろ倒しになり、過払い金を請求できる場合があります。
たとえば、2005年に一度完済していたが、2008年に再び借入をし、2020年に完済した場合、最終取引日は2020年となり、2030年まで過払い金の請求ができる可能性があるのです。
「一連の取引」とみなされる条件
「過去に完済した借金であっても状況に応じて一連の取引とみなす」という考え方は、最高裁判所の判例に基づくものです。
業者との取引が継続的で、一体の契約と認められるかどうかが判断のポイントになります。
たとえば、以下のようなケースでは一連の取引と認められる可能性が高いでしょう。
- 借入と完済を繰り返している
- 返済後に短期間で再借入をしている
- 担保や保証人の変更がなく、同じ契約が続いている
ただし、以上の条件を満たしていたとしても、業者側が「過去の取引は完全に終了し、新たな契約として扱われる」と主張することもあります。
この場合、契約内容や借入の流れを確認し、裁判を通して一連の取引であると立証しなければなりません。
最終的な判断はケースバイケースとなるため、弁護士などの専門家に相談するのが望ましいでしょう。
貸金業者から不当行為を受けているときは、請求できる可能性がある
貸金業者が脅迫や不当な取り立てなどの違法行為をしていた場合、過払い金請求の時効が停止または延長される可能性があります。
なぜなら、借主が適切に権利を行使できなかった状況が考慮されるためです。
貸金業者からの不当行為としては、以下のような行為が該当します。
|
行為(根拠法) |
具体例 |
|
虚偽の説明による妨害(民法96条) |
「過払い金は返還されない」とウソをつかれた |
|
違法な取り立て(貸金業法21条) |
夜間・早朝に執拗な催促があった |
|
取引履歴の開示拒否(貸金業法19条) |
取引履歴の一部または全部について開示請求に応じず、過払い金請求を遅延させた |
このような不当行為を受けていた場合、録音やメールの記録など、証拠を集めることが重要です。
弁護士や司法書士に相談し、適切な対処をすれば、時効が成立していても過払い金を取り戻せる可能性があります。
令和以降も過払い金請求は数多くおこなわれている
令和時代に入ってからも、過払い金請求は多くの人によっておこなわれています。
前提として、過払い金が発生している可能性が高いのは、貸金業法改正の影響を受けない2007年以前の借入についてです。
過払い金の請求権は完済から10年で時効となるため、仮に2007年に借入をして3年で完済していた場合は、2020年には時効となっていることになります。
しかし、実際には完済まで時間がかかっていたり、完済後の借入が一連の取引とみなされ時効が適用されなかったりといった状況により、2025年現在でも過払い金請求は数多くおこなわれているのが実態です。
日本貸金業協会が公表しているデータによれば、過払い金の返還額は年々減少傾向にあるものの、以下のように高額な返還が続いています。
|
時期 |
過払い金(利息返還金)の総額 |
|
過払い金請求が多かった時期 |
平成18年:約2,936億円 |
|
近年 |
令和2年:約1,147億円 |
過払い金請求の時効が近づいている場合の対処法
過払い金請求は正当な権利ですが、多くのケースで借金の完済から10年間で時効となるため、少しでも早く行動するのが重要です。
ここでは、過払い金請求の時効が近づいている場合の対処法を紹介します。
「過払金返還請求書」を送付し、時効を一時的に停止させる
過払い金の返還請求が時効に差しかかっている場合、過払金返還請求書を業者に送付することが最も有効です。
過払金返還請求書とは「○○年の借金について過払い金が発生しているので返還してください」という内容の通知のことを指します。
請求書には、過払い金を返還してほしい旨を記載するだけでなく、根拠となる取引履歴を添付することが推奨されます。
過払金返還請求書を内容証明郵便で送ることにより、時効の進行を6ヵ月間停止させることが可能です。
時効が停止している期間を利用して業者と交渉したり、過払い金請求の準備を整えたりと、適切な対応を取りましょう。
なお、弁護士に相談すれば、過払金返還請求書の送付から、その後の手続きまでトータルでサポートしてくれます。
時効の完成を阻止するためにも、少しでも早く相談するのがおすすめです。
過払い金請求を裁判所に申し立て、時効を延長させる
貸金業者から過払い金請求に関して返答がない場合や交渉が難航する場合は、裁判所に過払い金請求の申し立てをおこなえます。
裁判所に訴訟を提起すると、民法147条に基づいて時効が一時的に中断されます。
裁判の判決が出るまで時効が延長されるため、過払い金を請求できる可能性が高まるでしょう。
ただし、裁判を起こすには法律知識が必要なので、やはり弁護士に相談するのがおすすめです。
過払い金請求についてよくある質問
ここでは、過払い金請求についてよくある質問についてまとめました。
過払い金請求を検討している人はぜひ参考にしてください。
20年前・30年前に借金を完済していても、過払い金請求ができますか?
20年前や30年前に完済している場合、通常は時効が成立しているため、過払い金請求はできません。
ただし、例外として請求が可能なケースもあります。
たとえば、借金の完済後も同じ貸金業者と長期間にわたり継続的に取引をしていた場合、それらが一連の取引とみなされると、最近の取引を基準に時効が計算される可能性があります。
また、業者が過払い金の存在を隠していたり、意図的に取引履歴を開示しなかったりした場合、不法行為と判断されることで、時効の起算点が変わるケースもあります。
まずは弁護士などの専門家に相談し、自分に過払い金請求の権利があるのか確認することが重要です。
過払い金請求にデメリットはありますか?
過払い金請求は、多くのケースで返還される可能性が高いものの、以下のようにいくつかのデメリットも考えられます。
- ブラックリストとなる可能性がある
- 一定の手間がかかる
とくに、返済中の借金について過払い金請求をおこなう場合はブラックリストになる可能性があるので注意しましょう。
ブラックリストになるとクレジットカードが解約になるほか、新たにローンなどを組むことができません。
「過払い金請求=ブラックリスト」ではありませんが、必ずリスクについて弁護士に確認してから手続きを進めましょう。
さいごに|過払い金請求の時効に不安がある場合は、まず弁護士へ相談を!
本記事では、過払い金請求の時効の仕組みや、10年以上前に完済している借金でも例外的に過払い金請求ができるケースについて詳しく解説しました。
過払い金請求の権利は、借金の完済から10年で時効となりますが、実際にはさまざまな事情によって例外的に時効とならず、過払い金請求ができるケースも多くあります。
2025年現在でも、多くの人が過払い金請求に成功しているので、2010年以前に消費者金融から借金をしていた人はぜひ一度弁護士に相談してください。
弁護士に相談すると、自分に過払い金請求の権利があるかどうかを確認できるうえ、過払い金請求まで依頼可能です。
また、時効が間近に迫っている場合でも、時効の完成を阻止するための適切な手続きをとってくれます。
弁護士への依頼は一定の費用がかかりますが、成功報酬は返還された過払い金から支払われることが多く、まとまった費用を用意しなくても依頼できる可能性が高いです。
ベンナビ債務整理では、過払い金請求をはじめとした借金問題の解決に注力している弁護士を多数紹介しています。
過払い金には時効があるため、少しでも早い行動が重要です。
初回相談は無料で対応している事務所も多いので、まずは話だけでも聞いてみましょう。

闇金問題の相談窓口【初回相談無料/分割払い・後払い対応】闇金問題に豊富な経験あり・月間400件以上の解決実績のある司法書士が違法な取り立てからお客様を解放します/任意整理・時効援用にも対応可<即日対応・24時間体制>
事務所詳細を見る
【周りにバレずに解決】【相談料・着手金0円・減額報酬無し】相談実績年間1500件以上!借金を本気で解決したい方、すぐにご相談を。人生の再出発を全力でサポートいたします【休日相談可】
事務所詳細を見る
【借金のご相談は何度でも無料!】【法人破産にも対応】経営が苦しいと感じる経営者の方はご相談を。返済に追われ、生活ができない/督促が来てしまったなど、個人の方からのご相談も歓迎◎【依頼後は最短即日で督促が止まります!】
事務所詳細を見る当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

過払い金請求に関する新着コラム
-
完済した借金の過払金、諦めていませんか?信頼できる弁護士に依頼すれば、戻ってくる金額が変わることも。費用は安心の後払いや分割払いが可能です。失敗しな...
-
「どうするアイフル?」のキャッチコピーのCMで一世を風靡したアイフルは株式会社として東証一部にも上場している大手の消費者金融です。「大手消費者金融な...
-
一時期のピークは過ぎましたが、過去( 2010年以前)に消費者金融から高い金利(グレーゾーン金利)で借り入れをしていた方は、過払い金が発生している可...
-
かつてプロミスは、消費者金融として高金利で貸付をおこなっていた経緯があり、過払い金請求の対象として多くの関心を集めています。本記事では、プロミスに過...
-
「丸井」でお馴染みのエポスカードですが、実は2007年頃まで、利息制限法の上限金利を超える27.0%の高金利で貸付をおこなっていたため、過払い金請求...
-
レイクは、かつて過払い金請求に対して前向きな業者でしたが、2016年以降はその姿勢が厳しくなり、満額の返還が難しくなってきています。本記事では、レイ...
-
過払い金請求のデメリットを知らずに手続きを進めると、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があります。信用情報への影響や新たな借入の制限、生活保護の停止...
-
過払い金請求はおかしい・怪しいと思われがちですが、法律に基づいた正当な手続きです。本記事では、過払金請求が疑われる理由や、過払い金が発生する仕組みに...
-
過払い金の請求権は基本的に借金の完済から10年で時効となります。一方で、完済後も繰り返し借入をしている場合などは例外的に10年以上前の借金でも過払い...
-
過払い金請求が住宅ローンの審査に影響しないか不安に思う方も多いのではないでしょうか。本記事では、過払い金請求によって住宅ローン審査で不利になるケース...
過払い金請求に関する人気コラム
-
自分の知らない間に住民税を滞納しているケースは珍しくありません。この記事では、住民税を滞納するリスクや滞納した場合の対処法、支払いが困難な場合に活用...
-
「過払い金がまだ戻ってくるのか知りたい」方に向けて、過払い金の時効の調べ方や過払い金の時効についてよくある誤解、時効が不成立となる3つのパターンを解...
-
過払い金がいくらになるかを知るには「引き直し計算」を行います。この記事では引き直し計算の方法を解説し、あなたが適切に過払い金を見積もれるようにサポー...
-
民事再生法とは、会社が抱える借金を減らし、会社の経営を立て直すための法的手続きです。また。破産と違い、民事再生法なら事業を継続することができます。会...
-
過払い金の対象になる人と対象にならない人、過払い金の請求で注意すべきポイントと、実際に過払い金を請求する際の流れについて解説します。
-
金利(きんり)とは、貸借した金銭などに一定率で支払われる対価のことです。利息(りそく)と同じ意味合いで使われます。お金を貸すもしくは、預ける場合、金...
-
時効の援用をすることで、時効が成立し借金の返済義務が消滅します。ただ誰でも利用できるわけではありません。この記事では、時効を狙っている人や時効間近の...
-
今回の記事では過払い金請求にかかる費用の中でも、仕組みが複雑な成功報酬金を中心に解説していきます。成功報酬金の種類や上限から、具体的な見積事例、成功...
-
総量規制(そうりょうきせい)とは、貸金業法によって定められた「本人の年収の3分の1以上の借り入れ総額を上回ってはいけない」という決まりです。この記事...
-
グレーゾーン金利は、過払い金(利息の払い過ぎ)と密接な関係を持っています。過払い金の請求をする前に、グレーゾーン金利のこと、自分にどれだけの過払い金...
過払い金請求の関連コラム
-
出資法が改正されて2010年以降グレーゾーン金利が撤廃されたことにより、新たに過払い金が発生することはなくなりました。それでも、現在も過払い金を請求...
-
過払い金返還請求訴訟(かばらいきんへんかんせいきゅうそしょう)とは、その名の通り過払い金の返還を求めるための裁判です。
-
貸金業者に払いすぎた利子「過払い金」の払い戻しを請求する方法をご存じでしょうか?この記事では、過払い金請求において必要となる、過去の取引明細や引き直...
-
これまでライフカードを利用したことがあれば、過払い金が発生している可能性があります。時効を迎えてしまう前に、速やかに請求手続きを進めましょう。本記事...
-
過払い金の請求権は基本的に借金の完済から10年で時効となります。一方で、完済後も繰り返し借入をしている場合などは例外的に10年以上前の借金でも過払い...
-
最近「国が認めた借金救済制度」というフレーズを耳にする機会も多いのではないでしょうか。本記事では、借金救済制度とは、どのような仕組みなのか、メリット...
-
過去に消費者金融やクレジットカードを利用して借金をした方は、払いすぎた利息(過払い金)が戻ってくる可能性があります。本記事では、過払い金請求の対象と...
-
過払い金請求をする際、弁護士選びは非常に大事です。せっかく過払い金を請求できたとしても、多額の弁護士費用を支払ってしまっては意味がありません。ここで...
-
レイクは、かつて過払い金請求に対して前向きな業者でしたが、2016年以降はその姿勢が厳しくなり、満額の返還が難しくなってきています。本記事では、レイ...
-
今回の記事では法律上の観点、また判例を元に過払い金請求における悪意の受益者がどういったものなのか、また過払い金請求する上での注意点についてまとめまし...
-
金利(きんり)とは、貸借した金銭などに一定率で支払われる対価のことです。利息(りそく)と同じ意味合いで使われます。お金を貸すもしくは、預ける場合、金...
-
かつてプロミスは、消費者金融として高金利で貸付をおこなっていた経緯があり、過払い金請求の対象として多くの関心を集めています。本記事では、プロミスに過...
弁護士・司法書士があなたの借金返済をサポート
債務整理では、債権者と交渉する任意整理や法的に借金を減額する、個人再生や自己破産などがあります。また、過去の過払い金がある方は、過払い請求を行うことも可能です。
ただ、どれもある程度の法的な知識や交渉力が必要になってきます。債務整理をしたくてもなかなか踏み切れないあなたをベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)の弁護士・司法書士がサポートいたします。