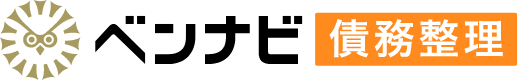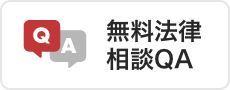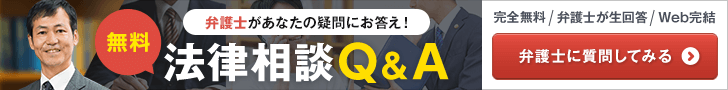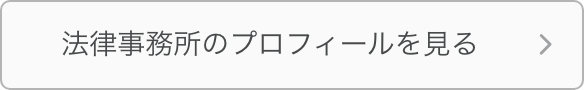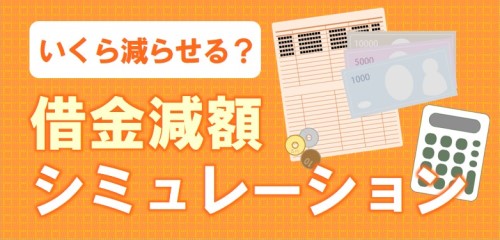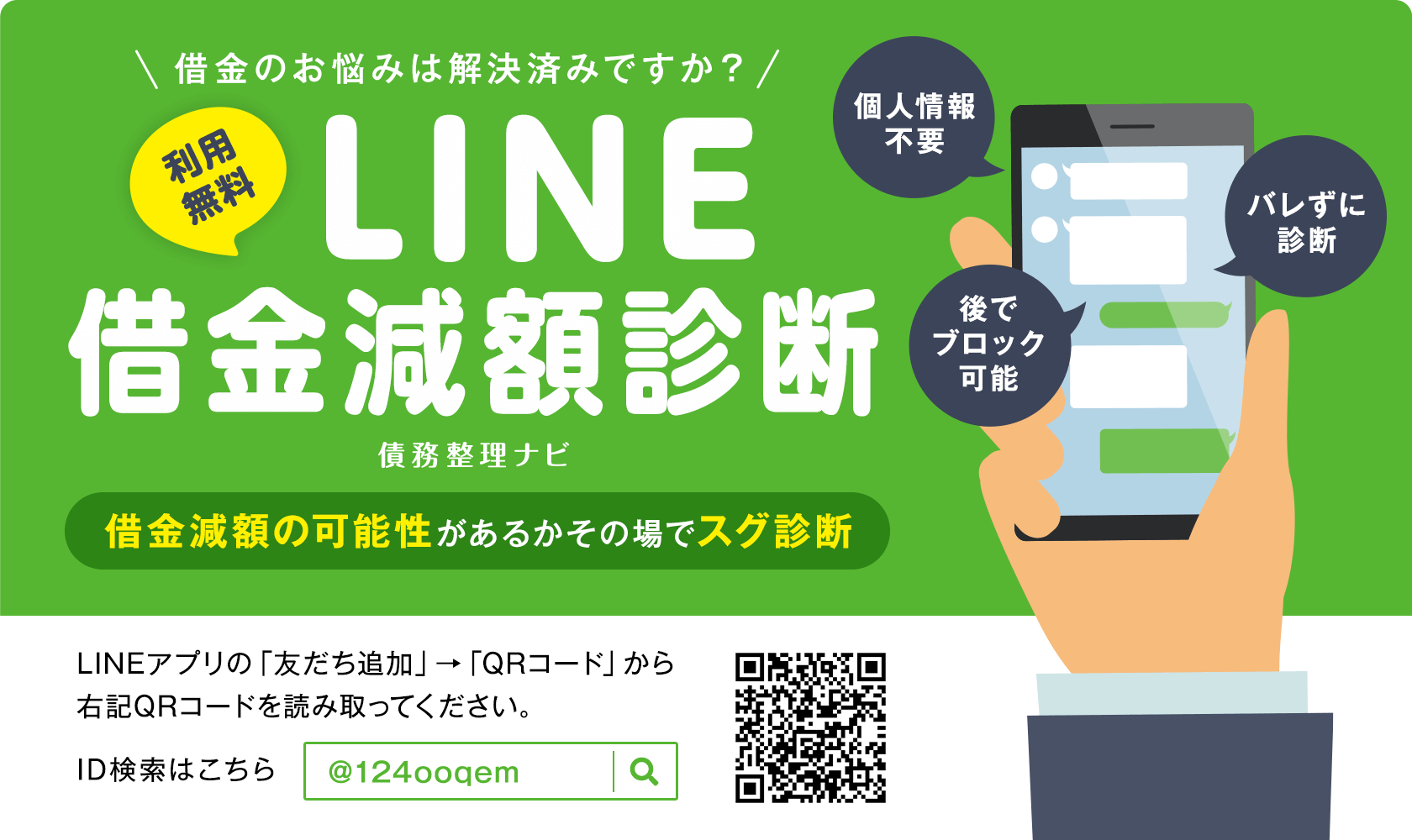【弁護士監修】借金の消滅時効とは?成立のための4つの条件や時効か調べる方法を解説

借金には「消滅時効」という制度があり、一定期間が経過すれば法的に返済義務がなくなる可能性があります。
借金の時効は原則5年。
ただし借入日が2020年4月1日以前の場合、時効は10年の可能性もあります。
また、単に期間が経てば時効が自動で成立するわけではなく、法律で定められた条件や手続きが必要です。
当記事では、借金の消滅時効の基本から時効成立の条件、具体的な期間、手続きの注意点までわかりやすく解説。
自分の借金が時効をむかえているかどうかを調べる方法も解説するので、ぜひ参考にしてください。
|
何年も前の借金を発見した 請求されてお困りの方へ! |
| 弁護士や司法書士に相談するメリットとは? |
|
専門家に時効の相談をして対応してもらえることは、主に以下の4つです。
【ベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)】では、無料相談できる債務整理が得意な弁護士や司法書士を探すことができます。ひとりで悩まず、まずはご相談ください。 |
借金の消滅時効とは?何年で時効になる?
借金の消滅時効とは、一定期間請求がない場合に、借りた側が「時効なので払いません」と主張することで返済義務がなくなる法的な制度です。
たとえば過去に消費者金融から借り入れたお金を返済できないまま長年経過し、その間、業者からの連絡や請求が一切なかった場合には、返済義務がなくなる可能性があります。
ただし、時効期間が過ぎただけで自動的に借金が消えるわけではなく、必ず「時効を援用します」という手続きが必要です。
借金は5年もしくは10年で時効が成立する
借金の時効は5年もしくは10年で成立します。
法改正がおこなわれた2020年4月1日を境に、時効が完成するまでの期間が5年となるか10年となるかの判断が変わります。
|
借入日:2020年3月31日以前 |
借入日:2020年4月1日以降 |
|
|
銀行や消費者金融からの借金 |
原則5年 |
原則5年 |
|
個人間の借金 |
原則10年 |
原則5年 |
銀行や消費者金融からの借金:5年
銀行、信用金庫、消費者金融、クレジットカード会社といった金融機関や貸金業者からの借り入れは、消滅時効の期間が原則として5年です。
2020年の民法改正前後で変更はありません。
- 2015年に消費者金融から借り入れた場合…5年
- 2024年に銀行から新たにカードローンを組んだ場合…5年
最後の返済日や返済期日の翌日から数えて5年間が経過すれば、時効成立の可能性があります。
個人間の借金:5年もしくは10年
友人や親、家族などからの個人間での借金の消滅時効期間は、借り入れの時期によって異なります。
2020年3月31日以前の契約に基づく借金は、原則として10年で時効が成立します。
一方、2020年4月1日以降の契約に基づく借金は、原則として時効は5年です。
- 2015年に友人からお金を借りた場合…10年
- 2024年に親族からお金を借りた場合…5年
ただし、個人間の貸し借りでは、明確な返済期日が定められていないケースも少なくありません。
そのような場合で、かつ債権者(貸した側)が「いつから請求できるかを知らなかった」という特別な事情がある場合に限り、10年が経過した時点で時効が成立します。
借金の時効が成立するための4つの条件

借金の返済義務が消滅する「消滅時効」が認められるためには、単に時間が経てばよいというわけではありません。
具体的には、「①一定期間の経過」「②時効の更新がないこと」「③時効の完成猶予がないこと」「④時効の援用をおこなうこと」の4つの条件を全て満たす必要があります。
条件1:時効に必要な期間が経過している
借金の消滅時効が成立するための大前提として、法律で定められた一定の期間が経過している必要があります。
現行の民法では、原則として以下のいずれか短い方の期間が経過したときに時効が完成すると定められています。
- 債権者が権利を行使できることを知った時から5年間行使しないとき
- 権利を行使できる時から10年間行使しないとき
通常、お金の貸し借りにおいては契約時に返済期日などが定められるため、債権者(貸主)はいつから請求できるか(権利を行使できるか)を知っているとみなされます。
そのため、多くの場合、「知った時から5年」という短い方の期間が適用されることになります。
なお、時効期間のカウントは原則として「最後の返済日」または「返済期日」の翌日からスタートします。
条件2:時効が更新(中断)していない
時効に必要な期間(5年もしくは10年)が経過していても、期間中に「時効の更新」にあたる事由が発生していると、時効成立になりません。
時効の更新とは、それまで経過した時効期間が全てリセットされ、ゼロから新たにカウントし直しになることを意味します。
せっかく長期間経過していても、更新事由が一度でも発生すれば、その時点から再び5年または10年が経過しなければ時効は完成しないのです。
具体的には、時効の更新にあたるのは次のような場合です。

裁判上の請求・支払督促があった場合
時効期間の進行中に債権者が裁判所に対して訴訟を提起したり、簡易裁判所に支払督促の申立てをおこなった場合は「裁判上の請求」にあたり、時効の更新事由となります。
最終的に判決が確定したり、支払督促が確定したりすると、その時点でそれまでの時効期間はリセットされます。
さらに、判決や確定した支払督促によって認められた権利の消滅時効期間は、確定の時から10年です。
元の時効期間が5年であったとしても新たに10年となるため、一度裁判を起こされてしまうと時効の成立によって借金から逃れるのは極めて難しいでしょう。
強制執行がおこなわれた場合
債権者が裁判所の判決や支払督促などの債務名義に基づいて、債務者の財産を差し押さえる「強制執行」の手続きをおこなった場合も、時効は更新されます。
強制執行の具体例は以下のとおりです。
- 給与の差押え
- 預貯金口座の差押え
- 不動産などの財産の差押えと競売 など
強制執行手続きが終了した(たとえば差押えが完了した、または取り下げられた)時点で、時効期間はリセットされ、そこから新たに10年の時効期間がスタートします。
債務の承認をした場合
時効期間の進行をリセットさせるもうひとつの重要な事由が「債務の承認」。
債務者自身が借金の存在を認める言動をとると、時効は更新されます。
たとえば「少しだけでも支払います」「今は払えないので、もう少し待ってください」と債権者に伝えたり、実際に借金の一部を返済したりした場合は全て債務の承認とみなされるので注意してください。
口頭での約束だけでなく、借金の存在を認める内容の念書や和解書などにサインした場合も同様です。
無意識のうちに、あるいは良かれと思って取った行動が、法的には「借金を認めた」ことになり時効の成立を妨げてしまうケースは少なくありません。
条件3:時効の完成猶予がない
時効の成立には、期間の経過と更新事由がないことに加え、「時効の完成猶予」にあたる事由がないことも必要です。
完成猶予とは、特定の事由が発生している間、一時的に時効期間の進行がストップすること。
猶予される期間が終了すると、停止していた時点から時効期間のカウントが再開されます。

具体的には、時効の完成猶予にあたるのは次のようなケースです。
内容証明郵便が届いた場合
債権者が内容証明郵便などを用いて、借金の返済を求める通知(法律上は「催告」といいます)を送ってきた場合、時効の完成猶予事由にあたります。
催告があったときから6ヶ月間は時効の完成が猶予されます。
つまり、催告状が届いた時点で時効完成が間近だったとしても、そこから6ヶ月間は時効が成立しません。
6ヶ月の猶予期間内に、債権者が裁判上の請求や支払督促、強制執行といった法的な手続きを取れば、時効は更新(リセット)されることになります。
逆に債権者が催告をしただけで、その後6ヶ月以内にこれらの法的措置をとらなかった場合は、猶予期間が終了した翌日から再び時効期間のカウントが再開されます。
協議をおこなう合意がした場合
債権者と債務者の間で、借金の支払いに関する権利について協議をおこなう旨の合意が書面でなされた場合も、時効の完成猶予事由となります。
具体的には、「借金の返済方法について話し合いましょう」といった内容で、当事者双方が合意し、その合意を書面に残した場合です。
書面による合意があると、原則として合意があった時から1年間は時効の完成が猶予され、たとえ本来の時効期間が満了しても時効は成立しません。
ただし、合意の中で1年より短い期間が定められた場合はその期間、または当事者の一方が協議の終了を書面で通知した時から6ヶ月を経過するまでのいずれか短い期間が適用されます。
なお話し合いが不調に終わったとしても、合意に基づいて協議がおこなわれている間は時効のカウントはストップしている状態となります。
仮差押えや仮処分があった場合
債権者が裁判所に「仮差押え」や「仮処分」といった保全処分を申し立て、認められた場合も、時効の完成が猶予されます。
仮差押えは金銭債権の保全のために債務者の財産を仮に差し押さえる手続き、仮処分は金銭債権以外の権利の保全や、争いがある権利関係について暫定的な措置を求める手続きです。
本格的な裁判や強制執行の前段階としておこなわれることが多く、債権者が権利実現に向けて動いている証拠とみなされます。
そのため、これらの手続きが効力を有している間は、時効の完成が猶予されることになります。
条件4:消滅時効の「援用」手続きをおこなう
借金の時効が成立するための最後の条件が、消滅時効の「援用」手続きをおこなうこと。
たとえ法律で定められた時効期間(原則5年または10年)が経過し、その間に時効の更新や完成猶予にあたる事由がなかったとしても、自動的に借金の返済義務がなくなるわけではありません。
債務者(借りた側)が債権者(貸した側)に対して、「時効によって利益を受けます」という意思表示、すなわち「援用」を明確におこなう必要があると定められています。
時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
引用元:民法第145条
援用をするには、時効援用通知書を作成し、内容証明郵便で債権者に送付するのが最も確実で一般的な方法です。
自分の借金が時効かどうか調べる4つの方法

「もしかしたら借金が時効になっているかもしれない」と考えたとき、本当に時効の条件を満たしているのかを正確に確認することが非常に重要。
単なる思い込みや記憶違いで行動してしまうと、かえって状況が悪化しかねないため、正しい方法で「時効かどうか」を調べましょう。
契約書・借用書・利用明細を確認する
借金の時効を確認する上で最も基本的な方法は、手元に残っている関連書類を確認すること。
次の書類には、時効期間の計算や援用手続きに不可欠な情報が含まれている可能性が高いです。
- お金を借りた際の契約書や借用書
- クレジットカードの利用明細書
- 銀行ローンの返済予定表
客観的な資料によって、どの債権者に対していつ発生した債務なのかを正確に把握することが、時効判断の出発点です。
特に「最終返済日」や「返済期日」を確認すれば、時効期間がいつからカウントされるか(起算点)を特定するための重要な手がかりとなります。
債権者からの督促状・請求書・催告書を調べる
過去に債権者から送られてきた郵便物、特に督促状、請求書、催告書といった書類が残っていないかを確認しましょう。
単に返済を求めるだけでなく、時効の成否に関わる重要な情報が記載されている場合があります。
確認すべきポイントは次の4つ。
- 債権者の名称(債権譲渡などにより当初の借入先から変わっている可能性もあり)
- 書類の発行日
- 請求されている金額の内訳(元金、利息、遅延損害金など)
- 「最終取引日」や「最終弁済期日」といった日付に関する記載
また「訴訟等法的手続きの準備に入らざるを得ません」といった裁判手続きを予告する文言や、実際に裁判所からの通知(支払督促など)に関する言及がないかも注意深くチェックしてください。
これらの記載や日付は、時効の起算点や、時効の更新・完成猶予事由の有無を判断する上で有力な証拠となり得ます。
信用情報機関に情報開示請求をする
金融機関や貸金業者からの借入は、信用情報機関に自身の信用情報を開示請求することで、契約内容や返済状況に関する客観的な記録を確認できます。
個人のローンやクレジットに関する取引情報が、法律に基づいてこれらの機関に登録・管理されているためです。
主な信用情報機関は3つ。
|
銀行系 |
全国銀行個人信用情報センター(KSC) |
|
消費者金融系 |
株式会社日本信用情報機構(JICC) |
|
信販会社・クレジットカード会社系 |
株式会社シー・アイ・シー(CIC) |
郵送またはインターネット経由で開示請求ができるため、各機関に問い合わせてみましょう(通常500円から1,000円程度の手数料が必要)。
開示された情報からは、契約日、最終返済日、現在の残高などを確認でき、時効期間の計算に役立ちます。
ただし、個人間の借金や一部の小規模な業者からの借金は信用情報機関に登録されていないため、この方法では確認できません。
裁判所からの通知履歴を確認する
借金の時効を考える上で、過去に裁判所から何らかの通知を受け取ったことがあるかどうかは、極めて重要なポイント。
債権者による訴訟の提起や支払督促の申立てがあると時効が更新(リセット)し、さらに判決などが確定すると新たに10年という長い時効期間が始まってしまうためです。
具体的には、裁判所から「特別送達」という特殊な郵便で、訴状や支払督促といった書類が自宅に届いていなかったか、記憶をたどってみてください。
自分では受け取った記憶がなくても、同居している家族が受け取っていた可能性もあります。
もし、裁判所からの通知を受け取った記憶が曖昧で不安が残る場合は、弁護士に相談して事件記録の調査を依頼することも可能です。
借金の時効援用は「ベンナビ債務整理」!
借金の消滅時効は、長年返済できずに悩んでいた借金の支払い義務から解放される法的手段。
しかし時効が成立するための条件は厳格であり、その判断や必要な「援用」の手続きは非常に複雑です。
法律の専門知識がない一般の方が時効の計算を正確におこなうのは容易ではありません。
もし自己判断で誤った対応をしてしまうと、取り返しのつかない事態を招きかねないでしょう。
「もしかしたら自分の借金も時効かもしれない」と思ったら、まずは借金問題に詳しい法律の専門家、特に弁護士に相談することが最も安全かつ確実な方法です。
借金問題に強い弁護士や司法書士を探す際には、弁護士検索ポータルサイト「ベンナビ債務整理」を活用しましょう。
借金返済や過払い金請求など、債務整理が得意な弁護士を全国から検索できます。
時効援用を弁護士に依頼するメリット
借金の時効援用手続きを弁護士に依頼すると、多くのメリットがあります。
まず最大の利点は、個別の状況に応じて時効が完成しているかどうかを正確に判断してくれる点です。
複雑な時効期間の計算や、過去の経緯の中に時効の更新・完成猶予事由がないかを調査し、法的な観点から確実な見通しを立ててくれます。
また弁護士が代理人として債権者とのやり取りを全て引き受けてくれるため、債権者からの直接の連絡や督促が止まり、精神的な負担から解放されるという点も大きなメリットです。
弁護士の名前で通知を送ることで、債権者側も不当な請求をしにくくなるという心理的な効果も期待できます。
さらに弁護士に依頼すると、うっかり債務を承認してしまうような言動をとってしまうリスクも回避できます。
費用は発生しますが、時効援用に失敗した場合に負うかもしれない借金全額(遅延損害金含む)の返済リスクと比較すれば、弁護士に依頼する価値は十分にあると言えるでしょう。
時効援用にかかる弁護士費用
時効援用にかかる弁護士費用は、債権者1社(または個人1人)あたり3万円から10万円程度が相場目安です。
複数の借入先に対して時効援用をおこなう場合は、その社の数に応じて費用が加算されていきます。
弁護士費用には、時効調査、援用通知書の作成・送付、債権者とのやり取りなどが含まれるのが一般的です。
また、正式な依頼の前に法律相談をおこなう場合には相談料が発生する場合もありますが、借金問題に関する初回無料相談をおこなっている法律事務所も多くあります。
まずは気軽に相談してみましょう。
借金の時効を完成させる援用手続きの具体的な方法
前述の通り、援用は時効によって利益を受けるという意思表示であり、援用をしなければ借金の返済義務はなくなりません。
援用の意思表示は、法律上は口頭でおこなうことも可能ですが、確実に意思表示をした証拠を残すために書面でおこなうのが通常です。
最も確実な方法は、「時効援用通知書」と題した書面を作成し、「内容証明郵便」で債権者に送付すること。
時効援用通知書には「貴社に対する以下の債務については、消滅時効が完成しておりますので、本書面をもって時効を援用します」といった内容と、対象となる債務を特定する情報(契約番号、借入日など)を記載します。
弁護士に依頼せず自分でおこなう場合は、文面に不備がないよう注意深く作成し、同じものを3部(債権者送付用、郵便局保管用、自身保管用)用意して郵便局の窓口で手続きをおこなってください。
時効援用手続きに必要な費用
借金の時効援用手続きを弁護士などに依頼せず、自分でおこなう場合、費用は1,500円~5,000円ほどで済みます。
費用の内訳は、内容証明郵便の料金と、信用情報機関への情報開示請求費用です。
|
内容証明郵便の料金 |
1通あたり 1,500円程度 |
|
信用情報機関への情報開示請求費用 |
1社あたり 500円~1,000円 |
内容証明郵便の料金は、文書の枚数やオプション(速達や配達証明の有無など)によって変動しますが、通常は1通あたり1,500円程度が目安です。
さらに、時効の成否を判断するため事前に「信用情報機関」へ情報開示請求をおこなう場合は、開示請求費用がかかります。
信用情報機関は主に3つあり、手数料は1社あたり500円~1,000円程度です。
これらを合わせると、自身で手続きをおこなう場合の実費は概ね1,500円~5,000円程度。
弁護士費用が3万円~10万円のため、コストを抑えたい方は自分で手続きをおこなうのもおすすめです。
ただし、費用を抑えられる一方で、自身での手続きには時効判断の誤りや手続きの不備といったリスクが伴う点には十分な注意が必要です。
借金の時効援用におけるデメリットと注意点
借金の時効援用は、返済義務から解放される可能性がある有効な手段ですが、メリットばかりではありません。
いくつかのデメリットや注意すべき点が存在します。
時効が更新される可能性がある
時効援用における最も重大なリスクのひとつが、意図せず時効期間をリセット(更新)させてしまう可能性です。
まだ時効が完成していない、あるいはすでに過去に更新事由が発生していたにもかかわらず、それに気づかずに「時効が成立したはずだ」と思い込み、債権者に対して時効援用通知を送ってしまった場合に起こり得ます。
時効を援用するという行為自体が、裏を返せば「借金の存在を認識している」ことの表明と受け取られかねません。
もし時効完成前に援用通知を送ってしまった場合、その時点で時効期間はゼロにリセットされ、そこから新たに5年または10年のカウントが始まってしまいます。
結果的に、時効の完成がさらに遠のくばかりか、債権者を不必要に刺激し、訴訟などの強硬な手段を誘発してしまうリスクも高まります。
借金が増えるリスクがある
もし、時効が成立していると判断して援用手続きをしたものの、実際には時効の条件を満たしていなかった場合、請求される借金の総額が想定以上に膨れ上がる可能性があります。
借金の返済が滞っている期間には、元金に対して「遅延損害金」が発生し続けているためです。
遅延損害金の利率は通常の利息よりも高く設定されていることが多く、長期間にわたって返済が滞っている場合、総額は元金を大きく上回ることも珍しくありません。
たとえば、100万円の借金を10年間放置していた場合、遅延損害金だけで数百万円に達しているケースもあります。
時効の援用に失敗するということは、元金と高額な遅延損害金の全額について、法的な支払い義務が依然として残っていることを意味します。
債権者からすれば、時効援用通知を受け取ったことで債務者の所在が判明し、改めてこれらの全額を一括で請求してくる可能性が高まるでしょう。
過払い金請求ができなくなる
借金の時効援用は借金の存在そのものを「なかったこと」にすることになるため、結果として、その契約に基づいて発生していたはずの過払い金を請求する権利も同時に失ってしまいます。
過去に消費者金融と長期間にわたって取引があり、利息制限法の上限を超える利率で返済を続けていた場合、本来支払う必要のなかったお金、すなわち「過払い金」が発生している可能性があります。
時効援用によって消滅する借金の額よりも、発生している可能性のある過払い金の額の方が大きい場合は、時効を援用せずに過払い金請求の手続きを優先するのもひとつの手。
どちらの手続きが有利かは個別の状況によるため、判断に迷う場合は弁護士に相談するのが最善です。
信用情報が回復するには時間がかかる
借金の時効援用が無事に成功して法的な返済義務がなくなったとしても、すぐに信用情報がきれいになり、新たにクレジットカードを作成したり、ローンを組んだりできるようになるわけではありません。
信用情報が完全に回復するまでには、ある程度の時間がかかるのが一般的です。
時効援用が成功した場合、通常は債権者が信用情報機関に対して契約終了の情報を申請し、それに基づいて延滞情報や契約情報が削除されることになります。
信用情報機関のルールでは、契約が終了した(時効成立も含む)場合、その情報が登録から削除されるまでの期間は5年程度。
したがって、時効援用後も最低でも数ヶ月から数年間は信用情報に影響が残る可能性があると考えてください。
時効援用が難しい場合の借金解決策
時効の援用が難しい場合でも、借金問題を解決する道が閉ざされたわけではありません。
法的に認められた「債務整理」という手続きを利用することで、借金の負担を軽減したり、返済義務そのものを免除してもらったりすることが可能です。
債務整理には3種類の方法があります。
任意整理:利息カットと分割返済の交渉
任意整理は、弁護士や司法書士が代理人となって、債権者(貸金業者など)と直接交渉をおこない、借金の返済条件を見直してもらう手続き。
主な交渉内容としては、今後発生する利息をカットしてもらい、残った元金を無理のない範囲で分割して返済していくことを目指します。
返済期間は、通常3年から5年程度で設定されることが一般的です。
裁判所を通さずに当事者間の話し合いで解決を目指すため、他の債務整理手続きに比べて手続きが比較的簡易で、期間も短く済むことが多いというメリットがあります。
また、整理する借金を選ぶことが可能。
たとえば保証人がついている借金や、住宅ローン、自動車ローンなどを除外して、他の借金だけを整理するといった柔軟な対応もできます。
ただし、任意整理はあくまで元金の返済が前提となるため、安定した収入があり、交渉で合意した内容に従って3年~5年程度で返済を続けられる見込みがある場合に適した方法です。
任意整理について詳細を知りたい方は以下の記事も参考にしてください。
個人再生:借金を大幅に減額する裁判手続き
個人再生は、裁判所に申立てをおこなうことで、借金の総額を大幅に減額してもらう法的な手続き。
減額の幅は借金の総額や保有資産によって異なりますが、法律で定められた基準に基づき、元の借金額の5分の1から10分の1程度まで圧縮される可能性があります。
そして、減額された後の金額を原則として3年間で分割して返済していくことになります。
個人再生の特徴は、借金の理由(浪費やギャンブルなど)が原則として問われにくい点や、住宅ローン返済中の持ち家を手放さずに他の借金だけを減額できる可能性がある点です。
ただし、個人再生を利用するためには、将来にわたって継続的に収入を得る見込みがあることなど一定の条件を満たす必要があります。
個人再生の条件は以下記事で解説しているので、参考にしてください。
自己破産:返済義務を免除してもらう最終手段
自己破産は、裁判所に申立てをおこない、現在の収入や財産では借金を返済することが不可能であると認めてもらうことで、原則として全ての借金の支払い義務を免除してもらう法的な手続き。
収入が途絶えてしまった、病気で働けなくなった、あるいは借金の額が大きすぎて任意整理や個人再生といった他の手続きを利用しても返済の目処が立たない、といった場合に選択されることが多い方法です。
自己破産をすると、一定以上の価値のある財産(持ち家や車など)は原則として処分されますが、生活に必要な最低限の財産(現金99万円まで、生活必需品など)は手元に残すことが認められています。
手続き後は借金の返済から解放され、経済的な再スタートを切ることが可能です。
ただし、税金や養育費など一部の非免責債権は自己破産しても免除できません。
自己破産で借金をゼロにしたい方は以下の記事が参考になります。
借金の時効に関するよくある質問
借金の時効に関して特によく寄せられる質問とその回答をいくつか紹介します。
時効の援用を検討する際の参考にしてください。
亡くなった人の借金を相続した場合に時効援用できる?
「死んだ親の借金を引き継いだ」など、亡くなった方が遺した借金についても、消滅時効の条件を満たしていれば、その借金を相続した方が時効を援用することは可能です。
亡くなる前にすでに時効期間が経過していた場合や、亡くなった後に時効期間が満了した場合には、相続人が時効の援用手続きをおこなえば、借金の返済義務を免れることができます。
時効は「亡くなった方が本来返済すべきだった最終返済日や返済期日の翌日」からカウントされます。
相続が発生した日(亡くなった日)からではないので、間違えないようにしましょう。
時効援用の手続きは弁護士か司法書士どちらがいい?
基本的には弁護士への相談・依頼がおすすめ。
弁護士、司法書士ともに、時効が成立しているかの調査、時効援用通知書の作成・送付、債権者との交渉など、時効援用に関する手続きを代行してもらうことが可能です。
ただし、司法書士が扱える業務には法律上の制限があります。
具体的には、認定司法書士であっても、代理人として交渉や法的な手続きをおこなえるのは、個別の借金の元金の額が140万円以下の場合に限られます。
そのため、時効を援用したい借金の元金の残額が正確にわからない場合や、明らかに140万円を超えていることがわかっている場合には、扱える金額に制限のない弁護士に相談・依頼するのが無難でしょう。
弁護士であれば、金額に関わらず、万が一訴訟に発展した場合でも代理人として対応することが可能です。
さいごに
借金の消滅時効は、法律で認められた「返済義務をなくす」ための重要な制度で、5年もしくは10年で成立します。
時効が成立するための条件は次の4つ。
- 時効に必要な期間(5年か10年)が経過している
- 時効が更新していない
- 時効の完成猶予がない
- 消滅時効の「援用」手続きをおこなう
時効は期間の経過だけで成立するものではなく、更新や猶予の有無、そして「援用」の意思表示が必要不可欠です。
「借金の時効を成立させたい」と思ったら、時効が成立しているかを正確に確認しましょう。
むやみに債権者へ連絡をしたり、少しでも返済したりすると時効期間がリセットされる危険があるため、債務整理に強い弁護士に依頼するのがおすすめです。

【自宅・資産を守りながら借金を解決】個人再生で新たなスタートを切るお手伝いをします!借金減額・月々の支払いの軽減で負担の少ない返済を/オンライン相談・分割払い可◎/まずは無料相談から!任意整理・自己破産・法人破産にも対応
事務所詳細を見る
【借金のご相談は何度でも無料!】【法人破産にも対応】経営が苦しいと感じる経営者の方はご相談を。返済に追われ、生活ができない/督促が来てしまったなど、個人の方からのご相談も歓迎◎【依頼後は最短即日で督促が止まります!】
事務所詳細を見る
【全国65拠点以上】【問い合わせ件数1日1,000件以上】【周りに知られずに相談OK】はじめの一歩は弁護士への無料相談!あなたの街のアディーレに、何でもお気軽にご相談ください ※ 2024年1月~12月の平均受電数より問い合わせ件数算出
事務所詳細を見る当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

借金問題に関する新着コラム
-
どこからもお金を借りられない理由と、お金が今すぐ必要なときに検討したい22の対処法、お金がなくてもしてはいけない6つのNG行動、お金を借りられないと...
-
本記事では、返済支援として受けられるサポートや、無料で相談できる窓口について詳しく解説します。記事後半では、借金問題を根本から解決できる債務整理につ...
-
LINE減額診断は、簡単な質問に答えるだけで借金の減額可能性を無料で診断できるサービスです。本記事では、診断の仕組みや利用方法、注意点を詳しく解説。...
-
リボ払いの借金がなかなか減らないと悩んでいませんか?本記事では、リボ払いを自力で完済する方法や、債務整理を活用して負担を軽減する方法を詳しく解説。高...
-
本記事では、時効援用で借金問題の解決を目指している方に向けて、時効援用について弁護士と相談できる窓口、弁護士に依頼するメリット、弁護士を選ぶときのポ...
-
催告書が届いたのに何の対応もしないままだと、民事訴訟を提起されたり、財産・給料などが差し押さえられたりするリスクが高まります。本記事では、催告書が届...
-
借金を長期間滞納していると債権者から裁判を起こされ給料が差し押さえられる恐れがあります。一度差し押さえを受けると解除するためには一括返済するか債務整...
-
本記事では、借金100万円の月々の返済額シミュレーション、借金100万円を自力で返済できるかどうかの判断ポイント、返済資金を工面したり金利を下げたり...
-
複数の借金を一つにまとめる「おまとめローン」で毎月の返済額を減らし、利息負担を軽減しませんか?メリット・デメリット、注意点、よくある質問などを詳しく...
-
本記事では、借金が返せないと悩んでいる方に向けて、借金が返せないときに相談できる窓口、借金が返せない緊急度別のおすすめ相談先、弁護士に相談して債務整...
借金問題に関する人気コラム
-
借金の時効援用は、成功すればどれほど多額な借金でも返済を免除されます。しかし同時に、失敗すれば大きなリスクを背負う法律行為でもあります。 この記事...
-
専門家の助力があったとしても、今すぐブラックリストを削除することは難しいです。信用情報を回復させる方法、ブラックリストが消えるまでの期間、これ以上悪...
-
自己破産を検討されている方にとっては、破産後の生活は気になるところでしょう。この記事では、自己破産後に受ける制限や、生活を良くするために考えておきた...
-
債務者(さいむしゃ)とは、特定の債権者(さいけんしゃ)に対してお金を借りている、あるいは一定の給付義務を持つ人のことで、ローンの未払いや奨学金の滞納...
-
催告書(さいこくしょ)とは、滞納しているお金等を請求する際に送られてくる書類のことをいいます。この記事では、①催告書の意味②督促状との違い③すぐに払...
-
奨学金の返済額をしっかり把握していることで、利用後の返済計画が立てやすくなり、効率よく返済することができます。この記事では、返済額の相場とともに、返...
-
自分の知らない間に住民税を滞納しているケースは珍しくありません。この記事では、住民税を滞納するリスクや滞納した場合の対処法、支払いが困難な場合に活用...
-
自己破産は、全ての借金の支払い義務を逃れ、所持する高価な財産を処分する法的手続きであり、生活をゼロから再建するための最終手段です。本記事では自己破産...
-
国民健康保険は国民皆保険と呼ばれるように、「20歳以上の社会保険未加入者は国民健康保険へ加入する義務」があるため、もし滞納をしている場合は必ず滞納分...
-
奨学金が返せないとどうなるのか、皆さんはご存知でしょうか。今や大学生の約半数が利用している奨学金ですが、返せない人が増えていることが社会問題にもなっ...
借金問題の関連コラム
-
この記事では仮想通貨で借金が起こる原因とその対処法についてまとめました。借金を背負ってしまった方はもちろん、これから仮想通貨を購入してみたいと考えて...
-
総量規制(そうりょうきせい)とは、貸金業法によって定められた「本人の年収の3分の1以上の借り入れ総額を上回ってはいけない」という決まりです。この記事...
-
妻がサラ金で借金をしていた、夫の名義でカードをつくっていたなど、自分は節制していたはずなのに借金を抱えることになるケースは珍しくありません。この記事...
-
個人再生では家計簿を提出します。この記事では、家計簿を提出する理由、いつからいつまで書くのか、家計簿の作成方法・注意点、裁判所のチェックポイント、家...
-
リボ払いが終わらないのには訳があります。この記事では、リボ払いの仕組み、リボ払いについて相談できる相手、返済を終わらせる方法(一括払いなど)、債務整...
-
携帯料金を滞納すると、約2週間から1ヵ月で携帯・スマホは使えなくなります。本記事では、携帯代・スマホ代えお滞納した場合の利用停止や解約までの流れ、延...
-
借金減額の相談ができる窓口はいくつかあり、電話相談に対応しているところや無料相談可能なところなど、窓口によって対応内容が異なります。本記事では、借金...
-
パチンコで借金を作ってしまったことに後悔しているのであれば、債務整理することでやり直すことができるでしょう。この記事では、パチンコでできた借金でお悩...
-
国民健康保険は国民皆保険と呼ばれるように、「20歳以上の社会保険未加入者は国民健康保険へ加入する義務」があるため、もし滞納をしている場合は必ず滞納分...
-
借金問題の弁護士費用、いくら?任意整理・個人再生・自己破産、手続き別の費用目安や内訳をわかりやすく解説。弁護士費用が用意できない場合の対処法、費用倒...
-
借金地獄に陥る原因は人それぞれです。そのため、脱出方法も個々で最適な方法が変わります。この記事では、あなたの原因に合わせて最適な脱出方法をご紹介しま...
-
家賃も「借金」に含まれる為、借金の時効の制度が適用されます。これは意外と知られていないのですが、事実この時効によって数年分の家賃を一切払わなくてもよ...
弁護士・司法書士があなたの借金返済をサポート
債務整理では、債権者と交渉する任意整理や法的に借金を減額する、個人再生や自己破産などがあります。また、過去の過払い金がある方は、過払い請求を行うことも可能です。
ただ、どれもある程度の法的な知識や交渉力が必要になってきます。債務整理をしたくてもなかなか踏み切れないあなたをベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)の弁護士・司法書士がサポートいたします。
借金問題の解決方法をもっと知りたいあなたに