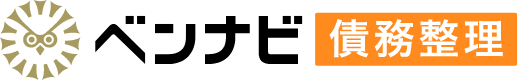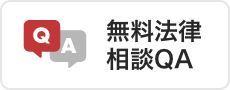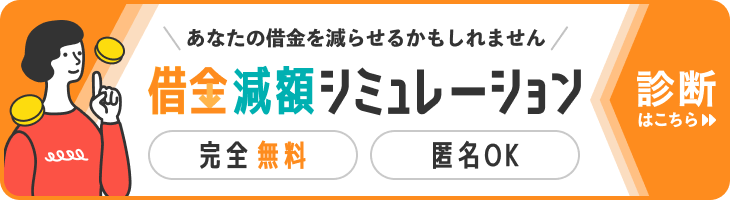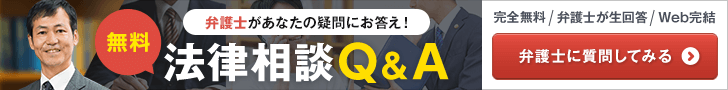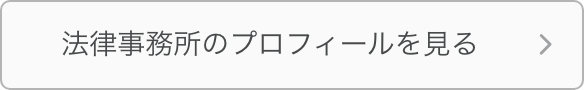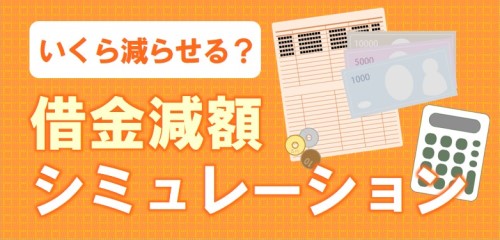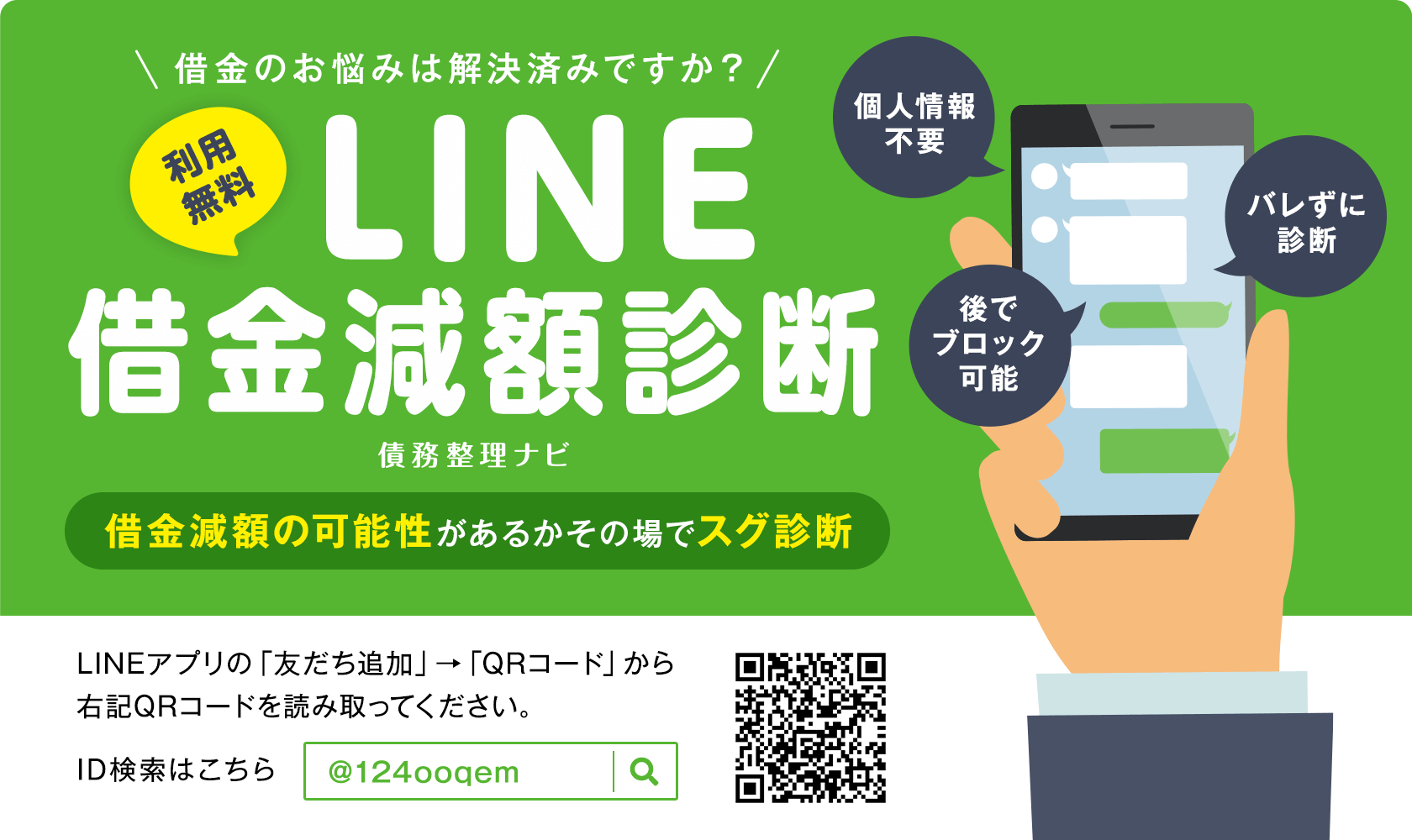債務不履行とは?種類や不法行為との違いやリスクをわかりやすく解説!

債務不履行(さいむふりこう)とは、正当な理由なく自分の債務を履行しないことをいいます。
債務不履行を大きく分けると、履行遅滞・履行不能・不完全履行の3種類があります。
債務者が金銭の支払いを怠った場合、債権者は強制履行・契約解除・損害賠償請求などが可能です。
しかし、債務を抱えている方の中には、これらの用語の意味や定義、債務不履行を起こした際にどうするべきかなど、よくわからない方も多いでしょう。
本記事では、債務不履行の定義や種類、債務不履行を起こした場合のリスクや対処法などを解説します。
|
借金を滞納し 債務不履行になってしまった人へ |
|
借金の滞納は、「債務不履行」に該当します。そのせいで返済を催促さてれている場合、できるだけ早い段階で弁護士や司法書士といった借金問題の解決が得意な専門家に依頼することが解決への近道です。 専門家への依頼では、以下のようなことが望めます。
借金原因は問われませんので、ひとりで悩まず、まずは専門家に気軽にご相談ください。 |
債務不履行とは
まず、債務とは借金返済などの「相手に対して何らかの行為をする義務」であり、債権とは「相手に対して何らかの行為を請求できる権利」のことを指します。
民法上、債務不履行には履行遅滞・履行不能・不完全履行の3種類あり、簡単に言えば「債務不履行とは債務者が約束事を守らないこと」と考えてください。
ここでは、債務不履行の種類について解説します。
履行遅滞
履行遅滞とは「債務者が履行可能にもかかわらず、履行期を経過しても履行しないこと」を指します。
たとえば、「金銭の支払い期日が決められているのに、これを過ぎてしまった」「引き渡し日を忘れていて引き渡しが遅れた」などのケースが該当します。
(履行期と履行遅滞)
第四百十二条 債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
2 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。
3 債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
引用元:民法 | e-Gov 法令検索
履行遅滞の条件
以下のような要件を満たした場合、履行遅滞が認められます。
- 履行期に履行が可能であった
- 債務の履行がないまま履行期が過ぎている
- 債務者に帰責事由がある
- 履行しないことについて違法性がある
履行遅滞で請求可能なこと
債務者による履行遅滞があった場合、債権者側は以下のような対応が可能です。
- 強制履行
- 損害賠償請求
- 契約の解除
定期行為というものもある
定期行為とは、「特定の日時または一定の期間内に履行をしなければ、契約をした目的を達成できない行為」を指します。
たとえば「通販などで商品の配達日を指定したのに来なかった」というようなケースが該当します。
履行不能
たとえば「著者のサイン入りで1点ものの書籍を購入しようと金銭を支払ったが、契約後に店舗の書籍が火事などで滅失してしまい届けられなくなった」というようなケースが該当します。
(履行不能)
第四百十二条の二 債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能であるときは、債権者は、その債務の履行を請求することができない。
2 契約に基づく債務の履行がその契約の成立の時に不能であったことは、第四百十五条の規定によりその履行の不能によって生じた損害の賠償を請求することを妨げない。
引用元:民法 | e-Gov 法令検索
履行不能の条件
以下のような要件を満たした場合、履行不能が認められます。
- 契約成立後に履行が不能になった
- 債務者に帰責事由がある
履行不能で請求可能なこと
債務者による履行不能があった場合、債権者側は以下のような対応が可能です。
- 損害賠償請求
- 契約の解除
不完全履行
たとえば「書籍を購入しようと金銭を支払って店舗側が書籍を郵送したが、注文したものと異なる書籍が届いた」というようなケースが該当します。
(債務不履行による損害賠償)
第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。
一 債務の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。
引用元:民法 | e-Gov 法令検索
不完全履行における債権者側の対応としては、強制履行・損害賠償請求・契約の解除などがあります。
債務不履行と不法行為の違い
債務不履行と似たものとして「不法行為」というものもあります。
不法行為とは「故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害する行為」です。
たとえば「交通事故を起こして相手に損害を負わせた」などのケースが該当します。
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
引用元:民法 | e-Gov 法令検索
上記のとおり、不法行為についても損害賠償請求などの対応が可能です。
たとえば「結婚式で必要な花嫁の衣装が時間までに届かない」というようなケースでは、注文者に損害を発生させたことになり、業者には不法行為が成立します。
契約関係がある状態で損害が生じた場合には、債務不履行と不法行為が成立することもあります。
債務不履行と不法行為の時効
債務不履行や不法行為には時効があり、それぞれの時効期間は以下のとおりです。
- 債務不履行:債権者が権利を行使できることを知ったときから5年、権利を行使できるときから10年
- 不法行為:被害者が損害および加害者を知ったときから3年、不法行為のときから20年
借金を返済できずに債務不履行を起こした場合のポイント
「借金を抱えているのに返済しない」という場合は債務不履行とされます。
借金を返さない場合や支払えない場合のいずれにしても、金銭消費貸借契約上の問題になります。
ここでは、借金問題で債務不履行を起こした場合の扱いや、対応方法などについて解説します。
借金を返済できない場合は履行遅滞として扱われる
「お金がなくて返せないというのは履行不能ではないか」と思う方もいるかもしれませんが、このようなケースでは履行遅滞として扱われます。
なぜなら、お金そのものがこの世からなくなったわけではないからです。
たとえば1,000万円の借金が返せない場合でも、借金の返済自体が不可能とはいえずに「債務者が支払いや返済を忘れている」あるいは「遅れていて履行遅滞の状態」と考えられる、ということです。
1,000万円というような多額の借金でも、毎月1万円ずつ支払っていけば84年ほどで返済できます。
少々気の遠くなるような話ですが、時間がかかっても返済できる可能性があるものに関しては、原則として「履行不能にはならない」ということになります。
借金問題の解決方法
借金問題を解決するためには債務整理が有効です。
債務整理をすると一定期間ブラックリストに登録されて、クレジットカードの新規作成やローンの利用などができなくなるというデメリットがあります。
しかし、少しでも早く借金生活から抜け出すためには、債務整理を検討することをおすすめします。
主な債務整理としては任意整理・個人再生・自己破産などがあり、ここではそれぞれの手続きについて解説します。
任意整理
任意整理とは、裁判所を通さずに債務者と債権者で直接交渉する手続きのことです。
任意整理では、主に返済期間の延長や利息の減額などについて話し合い、3年~5年ほどでの完済を目指します。
裁判所を通さない手続きのため、個人再生や自己破産よりも手間や費用をかけずに進められるのがメリットですが、減額効果が比較的低いという特徴もあります。
任意整理の流れやメリット・デメリットなど、詳しくは以下の記事で解説しています。
個人再生
個人再生とは、裁判所を介して借金の減額を求める手続きのことです。
個人再生では、再生計画案などの書類を準備して裁判所とやり取りする必要があり、裁判所に認可された場合は再生計画に従って返済をおこなっていきます。
場合によっては借金を最大10分の1にまで減額できるなどのメリットがありますが、手続きが複雑で利用条件が定められているなどの特徴もあります。
個人再生の必要書類や利用条件など、詳しくは以下の記事で解説しています。
自己破産
自己破産とは、裁判所を介して借金の返済義務の免除を求める手続きのことです。
自己破産では、必要書類を準備して裁判所とやり取りする必要があり、成立すれば税金などの一部例外を除く全ての借金が免除されます。
最も減額効果が大きい手段であり、自己破産をすれば借金生活から解放されるなどのメリットがありますが、価値のある財産が処分されるなどの特徴もあります。
自己破産の手続き方法や家族への影響など、詳しくは以下の記事で解説しています。
なお、任意整理・個人再生・自己破産は自力でも可能です。
しかし、素人では書類作成に手間取ったり交渉が難航したりするおそれがあります。
また、重大な不備を見逃して裁判所への申立てが却下されたりすることもあります。
債務整理に強い弁護士であれば、どの債務整理が適しているか的確にアドバイスしてくれますし、自分の代わりに手続きを一任することもでき、心強い味方になってくれるでしょう。
初回相談無料の法律事務所も多くあるので、まずは一度相談してみましょう。
家賃を滞納して債務不履行を起こした場合のポイント
なかには「家賃が支払えなくなっている」という方もいるでしょう。
このようなケースでも履行遅滞として扱われます。
ここでは、家賃滞納時の対応方法や、大家・保証会社に家賃の受け取りを拒否された場合の対処法などを解説します。
家賃滞納トラブルの解決方法
家賃について債務不履行があるということは、借金をしている場合と同様に「金銭債務がある」という状態になります。
このような場合も債務整理することができ、それぞれの基本的な流れとしては以下のとおりです。
任意整理の場合
任意整理の場合には、対象となる債権者を選んで交渉をおこないます。
家賃の滞納分も交渉の対象とすることはできますが、その場合は大家側から退去を求められることもあるため注意が必要です。
ほかにも債務を抱えている場合は、まずそちらを任意整理することをおすすめします。
自己破産の場合
自己破産では、全ての債権者を対象に手続きをおこないます。
そのため、大家も貸金業者などと同様に債権者として手続きに参加します。
もし財産がある場合は配当がおこなわれ、残った分については免責されることになります。
個人再生の場合
個人再生についても、基本的には全ての債権者を対象に手続きをおこないます。
自己破産手続きと同様に、大家も債権者として手続きに参加してもらい、家賃を減額できたら分割で弁済することになります。
家賃の受け取りを拒否された場合の対処法
家賃を滞納したのち入金する際、大家・保証会社との関係性などによっては受け取りを拒否されることもあります。
支払いができなければ家を退去することになるおそれもありますが、その場合には「供託」という方法が有効です。
供託とは、債権者が債務者からの支払いを拒絶している場合などに、お金を受け取らない相手に対して「金銭の支払いをした」ということにしてくれる制度です。
詳しい手続きの流れや必要書類などについては「供託|法務省」をご覧ください。
債務不履行を起こした場合のリスク
借金などについて債務不履行を起こした場合、以下のようなリスクがあります。
遅延損害金が発生する
金銭債務の債務不履行に対しては、債権者側から遅延損害金を請求されるリスクがあります。
借金の残額を一括請求される
たとえば、貸金業者から100万円の借り入れをして毎月3万円の支払いをしている場合、きちんと返済を続けていれば、残っている分を一括請求されても「まだ期限が来ていません」などと断ることができます。
このような、債務者側にとっての利益のことを「期限の利益」と呼びます。
契約内容次第では、債務不履行が一定期間続くと期限の利益を喪失する場合があり、その場合は一括請求を受ける可能性があります。
担保権を実行される
債務に担保がついているような場合には、担保権が実行される恐れがあります。
車などの引き上げ
たとえば、自動車ローンを組んで車を購入する場合、目的物である車に担保がついている状態(厳密には債権者に車の所有権が留保されている状態)になっていることが一般的です。
このような場合に債務不履行を起こすと、債権者が車を引き上げて売却し、売却金をローン残高に充てたりするリスクがあります。
家からの立ち退き要求
通常、住宅ローンを組んで家を購入するときには、目的物となる住宅に「抵当権」という担保権が設定されます。
住宅ローンの債権者は、住宅ローンについて債務不履行があった場合、抵当権を実行して住宅を競売にかけることができます。
その場合、競売での売却代金を債務不履行となっている債権に充てることになります。
競売をされた場合には、当然退去を求められるでしょう。
連帯保証人に請求される
債務不履行があって連帯保証人がついている場合、債権者は連帯保証人に対して請求することができます。
連帯保証人は「主たる債務者に請求してください」という抗弁(催告の抗弁)ができない、ということになっています。
なお、現実には、債権者は主たる債務者に請求してから連帯保証人に請求することが通常です。
強制履行される
強制履行とは「債務者に対して強制的に履行させること」で、直接強制・代替執行・間接強制などに大きく分けられます。
以下ではそれぞれについて解説します。
直接強制
直接強制とは、債務者が任意に債務の履行をしない場合、裁判所に請求することで債務者の意思に関係なく債務内容を実現させる方法のことです。
代替執行
代替執行とは、債務の内容が代替的作為義務(他人が代わりにおこなえる義務)の場合、債権者が第三者(通常は執行官)に債務の内容を実現させて、その費用を債務者から取り立てる方法のことです。
間接強制
間接強制とは、債務を履行しない債務者に対し、一定の期間内に履行しなければその債務とは別に金銭の支払いを課すことを警告し、心理的圧迫を与えて自発的な支払いを促す方法のことです。
契約解除される
債務不履行を起こすことで、契約解除されて関係を解消される場合もあります。
(解除の効果)
第五百四十五条 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。
2 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
3 第一項本文の場合において、金銭以外の物を返還するときは、その受領の時以後に生じた果実をも返還しなければならない。
4 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。
引用元:民法 | e-Gov 法令検索
賃貸借契約の場合
賃貸借契約についても、債務不履行による解除の対象となります。
ただし、賃貸借契約については「1日でも債務不履行があったら契約解除できる」というものではありません。
「債務不履行によって信頼関係が破壊された」というような状態になって、はじめて契約を解除できるとされています。
どの程度の債務不履行があったら信頼関係が破壊されたといえるかはケースバイケースですが、一般的には3ヵ月分程度の債務不履行があると、信頼関係が破壊されたとして契約が解除されることになります。
これによって、自宅から退去をしなければならなくなります。
損害賠償請求される
場合によっては、債権者から損害賠償請求されることもあります。
たとえば「届いた野菜が腐っていて食中毒になった場合」や「旅行券の発送が遅れたことで目的の飛行機に乗れなかった場合」などが該当します。
まとめ
借金などの支払いができずに債務不履行を起こしてしまうと、場合によっては契約解除や損害賠償請求などの対応を取られるおそれがあります。
金銭的に生活が苦しい方は、一度債務整理を検討してみることをおすすめします。
当サイト「ベンナビ債務整理」では、債務整理が得意な全国の弁護士を掲載しています。
「初回相談無料」「何度でも相談無料」などの法律事務所も多く掲載しているので、まずは近くの法律事務所を探してみましょう。

【借金の減額・免除で再スタート!】最短で催促ストップ◆家族や職場にバレにくい解決◆複数社から借り入れ、返済が苦しい等、当事務所へご相談ください【親身に対応◎】【秘密厳守】※個人間の金銭貸し借り・借金以外の一般法律相談に関する問い合わせは受け付けておりません。
事務所詳細を見る
「返済のために借入社数が増えてしまっている…」「借金総額が膨らんでわからなくなっている…」毎月の返済額の負担を軽減し、借金生活をやめたい方◆まずは最適な解決のために無料診断を◆
事務所詳細を見る
闇金問題の相談窓口【初回相談無料/分割払い・後払い対応】闇金問題に豊富な経験あり・月間400件以上の解決実績のある司法書士が違法な取り立てからお客様を解放します/任意整理・時効援用にも対応可<即日対応・24時間体制>
事務所詳細を見る当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

その他に関する新着コラム
-
「本当にお金がない」「誰からも借りられない」と困っている方必見。お金がない際の対処法を、メリットや対象者などを徹底解説します。金融機関からお金を借り...
-
長期間にわたって家賃滞納をした場合は、強制退去のリスクを想定しておかなければなりません。本記事では家賃滞納から強制退去までの流れやその後どうなるかを...
-
本記事では、法人破産について相談する弁護士をどこで見つけたらよいのか、どのような弁護士に法人破産を相談すべきか、弁護士に依頼することでどんなメリット...
-
本記事では、ブラックリストに精通した弁護士の特徴・探し方・手続きを依頼する流れなどについて詳しく解説します。ブラックリストが原因で新たな借り入れがで...
-
ブラック状態でも携帯分割できる可能性があるのは、10万円以下の端末を購入する・審査が緩い携帯電話会社を選ぶといった方法です。本記事では、ブラックでも...
-
時効の援用とは、一定期間が経過した借金について債権者に返済しない旨を伝えることで、借金の支払い義務を消滅させることができる制度です。本記事では、時効...
-
家賃滞納から強制執行までの流れ、回避方法、強制執行決定時の対応をわかりやすく解説しています。督促や内容証明郵便、支払督促、訴訟、強制執行など、それぞ...
-
連帯保証人と保証人は名称こそ似ているものの、生じる責任に大きな違いがあります。本記事では、連帯保証人と保証人の違いについてわかりやすく解説しています...
-
代位弁済とは、滞納した借金を保証会社などの第三者が代わりに支払ってくれることを指します。代位弁済後は保証会社への一括返済が必要となり、支払いを怠ると...
-
消費者金融の時効は5年です。最終返済日や返済期日、最終借入日から5年経ち、時効を援用することで借金は消滅します。時効の完成だけでは、借金が消えない点...
その他に関する人気コラム
-
ブラックリストとは、クレジットカードやカードローンの返済遅延・滞納や債務整理などにより、信用情報機関に事故情報が記録されることを指します。本記事では...
-
専門家の助力があったとしても、今すぐブラックリストを削除することは難しいです。信用情報を回復させる方法、ブラックリストが消えるまでの期間、これ以上悪...
-
スマホを購入する際に、分割払いに利用する方も多いのではないでしょうか。しかし場合によってはその審査に落ちてしまうことがあるのです。ここの記事では、ど...
-
債務者(さいむしゃ)とは、特定の債権者(さいけんしゃ)に対してお金を借りている、あるいは一定の給付義務を持つ人のことで、ローンの未払いや奨学金の滞納...
-
催告書(さいこくしょ)とは、滞納しているお金等を請求する際に送られてくる書類のことをいいます。この記事では、①催告書の意味②督促状との違い③すぐに払...
-
廃課金とは、廃人と課金を合わせたネットスラングで、一般的に収入に見合わない金額を課金する人を指します。本記事では廃課金の定義や課金してしまう人の特徴...
-
債務不履行とは、故意又は過失によって自分の債務を履行しないことをいいます。債務不履行には、履行遅滞、履行不能、不完全履行の3種類があります。債務不履...
-
国民健康保険は国民皆保険と呼ばれるように、「20歳以上の社会保険未加入者は国民健康保険へ加入する義務」があるため、もし滞納をしている場合は必ず滞納分...
-
買い物依存症とは、借金をしてまでも買い物を続けてしまう症状のことを言います。この記事では買い物依存症の特徴や対処法、すでに借金を作ってしまった人の解...
-
債権者とは、特定の人に対し、一定のお金を請求する権利を持つ人です。要するに、金貸し業者や慰謝料を受け取る人などが該当します。この記事では、債権者が有...
その他の関連コラム
-
時効の援用とは、一定期間が経過した借金について債権者に返済しない旨を伝えることで、借金の支払い義務を消滅させることができる制度です。本記事では、時効...
-
夫の借金が発覚した場合、まずは落ち着いて状況を確認しましょう。本記事では、妻が確認すべきことや返済義務が誰にあるのか、借金を放置するリスクや解決方法...
-
債務整理を依頼していた弁護士が業務停止になった場合、案件はどのような取り扱いになるのでしょうか。この記事では、弁護士における業務停止の効果やもし担当...
-
債務超過とは負債が資金を超え、資金を全て売却しても返済しきれない状況を指します。即倒産ではありませんが、倒産のリスクが非常に高いといえるでしょう。こ...
-
代位弁済とは、滞納した借金を保証会社などの第三者が代わりに支払ってくれることを指します。代位弁済後は保証会社への一括返済が必要となり、支払いを怠ると...
-
借金50万円を「甘く」「軽く」考えないでください。今すでに返済に困っていれば、すぐに膨れ上がります。借金50万円を無理なく確実に返済する方法を紹介し...
-
住宅ローンの連帯保証人には、さまざまなリスクが伴います。また、一度連帯保証人になってしまうと、簡単に解約することができません。この記事では、住宅ロー...
-
債務名義(さいむめいぎ)とは、債権者に対して、裁判所又は執行官が強制執行することを許可した公文書のことを言い、強制執行によって実現される「請求権の存...
-
キャッシングとは、クレジットカードやキャッシュカードを用いて、ATMや現金自動貸出機などからお金を引き出して借りることを言います。 この記事では、キ...
-
個人再生で偏頗弁済をおこなうと、最悪の場合、再生計画案が認可されず失敗に終わる可能性があります。本記事では、個人再生を成功させるために、注意すべき偏...
-
債務者(さいむしゃ)とは、特定の債権者(さいけんしゃ)に対してお金を借りている、あるいは一定の給付義務を持つ人のことで、ローンの未払いや奨学金の滞納...
-
妻がサラ金で借金をしていた、夫の名義でカードをつくっていたなど、自分は節制していたはずなのに借金を抱えることになるケースは珍しくありません。この記事...
弁護士・司法書士があなたの借金返済をサポート
債務整理では、債権者と交渉する任意整理や法的に借金を減額する、個人再生や自己破産などがあります。また、過去の過払い金がある方は、過払い請求を行うことも可能です。
ただ、どれもある程度の法的な知識や交渉力が必要になってきます。債務整理をしたくてもなかなか踏み切れないあなたをベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)の弁護士・司法書士がサポートいたします。