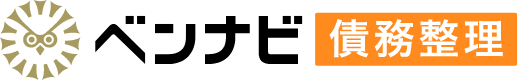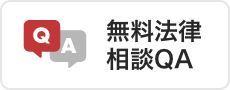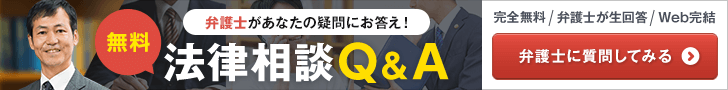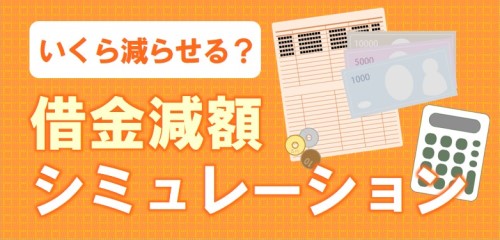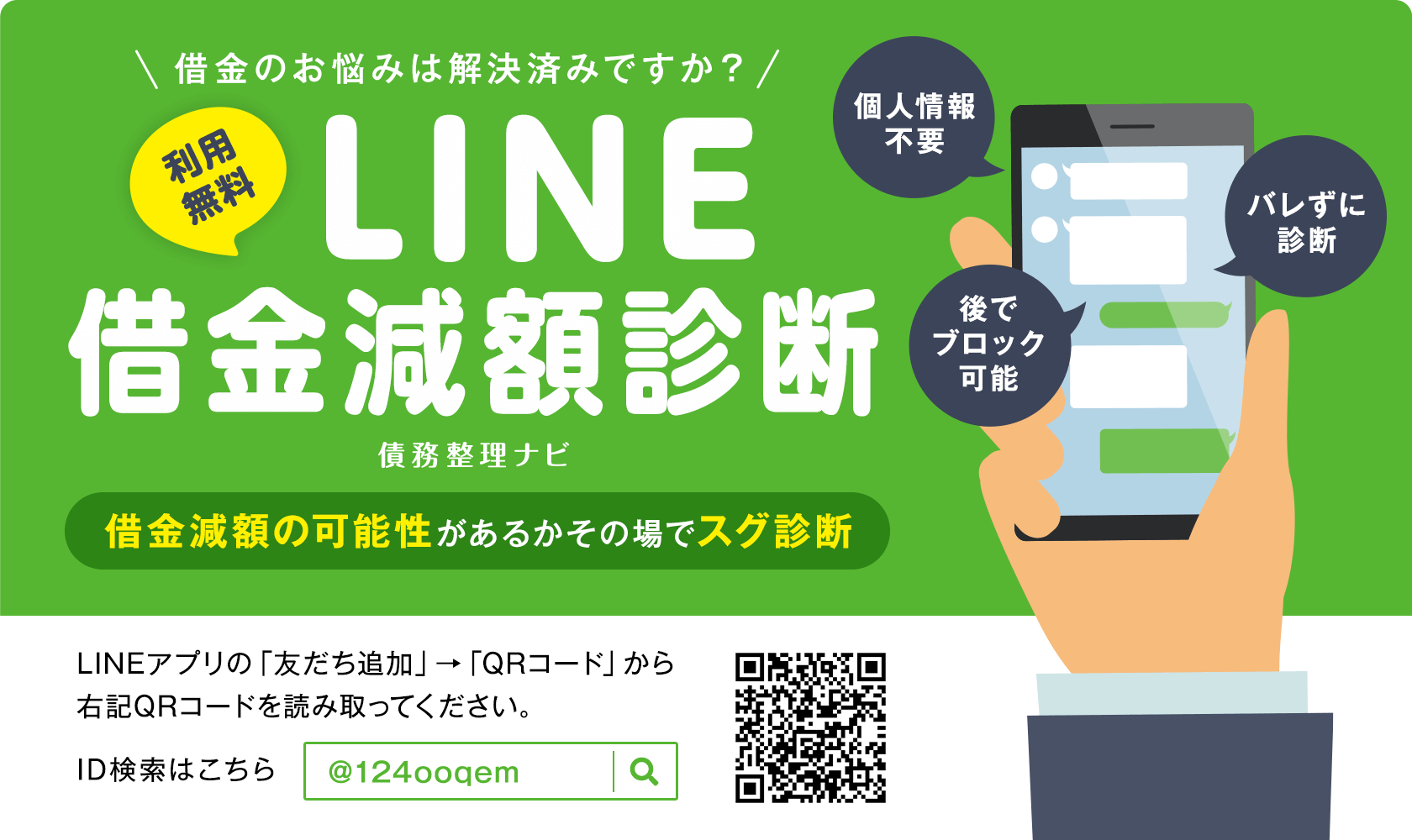担当弁護士が業務停止した場合にすべき3つのこと|依頼案件はどうなる?



これからどうすれば…
このように、債務整理を依頼していた弁護士が、なんらかの理由で業務停止されてしまった場合、処分を受けた弁護士は業務を継続することができません。そのため、同じ事務所の別の弁護士に依頼するか、別の事務所に依頼するなどの対応が必要です。
この記事では、実際に依頼先の弁護士が業務停止を受けた場合の対処法など、弁護士の業務停止の基礎知識とともにご紹介します。
|
担当弁護士が業務停止処分を受けてお困りの方へ |
|
担当弁護士が業務停止処分を受けると、自分が依頼した案件は事実上放置されることになります。 依頼先の弁護士が業務停止処分を受けた方は、下記の3つの対応をしましょう。
下記からたくさんの弁護士事務所を比較検討することができます。 初回相談が無料の弁護士事務所も多数掲載しているので、まずはお気軽にご相談ください。 |
※今すぐ弁護士に相談したい方は、以下よりお住まいの地域ご選択ください。
後払い/分割払い対応可能な弁護士事務所も多数掲載!

無料相談できる弁護士一覧
弁護士の「業務停止」とは
弁護士は、他社の法律事務という重要な問題を取り扱うため、一定以上の信頼が確保されなければなりません。
このような信頼確保の措置は弁護士自治の問題として、日本弁護士連合会(日弁連)や各地域の弁護士会により監督されています。弁護士会が、弁護士の職務が不適正と認めた場合にペナルティとして行うのが「懲戒」です(弁護士法56条)。
弁護士及び弁護士法人は、弁護士法又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受けることになっています(弁護士法56条)。
弁護士及び弁護士法人に対する懲戒には、戒告・2年以内の業務の停止・退会命令・除名の4種類があります(弁護士法57条)。
業務停止の効果
弁護士及び弁護士法人が業務の停止の処分を受けると、弁護士としての活動を一定期間一切行えなくなります。
例えば、弁護士法人が業務の停止の処分を受けた場合、その法律事務所を弁護士法人の業務を行うために利用することができなくなります。それだけに限らず、法律事務所であることを表す表札などの看板を除去しなければなりません。
この結果、法律事務所に電話しても誰も出ず、また、直接法律事務所に出向いたとしても誰もいない、ウェブサイトも全部削除されてしまい、連絡をとる術も分からないなどのトラブルになってしまうことがあります。
業務停止になった場合、依頼していた案件はどうなる?
業務停止になった場合、当該弁護士は依頼された案件について何の職務も遂行することができません。そのため、依頼していた案件は、事実上放置されることになります。
業務停止になる具体的な行為

業務停止になる具体的な行為としては、以下の行為があります。
過大広告・景品表示法違反
法律事務所のウェブサイトやテレビCMなどで、「4月まで無料」「今だけ無料」など、あたかも期間限定で着手金などの一定費用が無料であるかの装い、実は常に当該費用は無料で案件を受任しているようなケースがあります。
依頼者が依頼するかどうか判断をするにあたって重要な事実を虚偽の情報で隠したものといえます。このような行為をした弁護士または弁護士法人は業務停止の処分の対象となることがあります。
非弁連携
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができないと定められています。
そのため、弁護士である自分の名前を貸して弁護士資格のない者に、訴訟の代理人などをさせてしまうと、弁護士に資格制限を設けている意味がなくなってしまいます。
このような弁護士以外の者に弁護士のみができる業務をさせることを非弁連携といいます。このような行為は、業務停止の処分の対象となり得ます。
双方代理
弁護士が、一方の当事者だけでなく、相手側の当事者の意向を汲むなど、双方の利益になるように活動してしまうことを双方代理といいます。
弁護士は、依頼された当事者の利益のみを考慮して職務も遂行しなければならないところ、それを歪めてしまう行為は、業務停止の処分の対象となり得ます。
例えば、弁護士が債務整理において、債権者に対して明らかに過剰な譲歩をする、相手側当事者である債権者から利益を供与されるなどの行為が対象です。
反社会的勢力とのつながり
弁護士が、暴力団などの反社会的勢力の活動を促進するような活動を意図的にした場合、弁護士の品位を著しく害するものとして、懲戒の対象となり得ます。
依頼先の弁護士が業務停止を受けた場合にすべきこと
依頼先の弁護士が業務停止を受けた場合にするべきことは、以下の3つです。

1:依頼先の弁護士サイトなどから現状の確認
依頼先の弁護士サイトなどから、まずは本当に懲戒を受けているのか、懲戒を受けたのは弁護士本人か、それとも弁護士の所属する法律事務所なのかを確認しましょう。
ただし、業務停止を受けている場合、依頼先の弁護士サイトが既に閉鎖されており、何が起こっているかを確認することが困難な場合があります。このような場合には、当該弁護士が所属する弁護士会などの相談窓口などに連絡して、今後の対応を相談してみましょう。
2:誰と契約しているか委任契約書で確認する
弁護士に案件を依頼した場合には、弁護士との委任契約書を作成しているはずです。その委任契約書から、誰が依頼を受任した弁護士になっているのか、法人名義なのか弁護士個人名義なのかなどを確認しましょう。
もし、事務所の契約であれば、同じ事務所の弁護士に案件を引き継いでもらえるかもしれません。個人との契約の場合、同じ事務所の弁護士に依頼することは可能ですが、新規契約として再度着手金などが発生する恐れがあります。
3:別の事務所に依頼するか検討する
別の事務所に依頼するかどうかを検討しましょう。
依頼している案件が急いでやらなければならないものか、比較的期間がかかっても良いものなのか、業務の停止期間が1ヶ月など短いのか、1年を超える長期のものなのかなど、色々な事情を総合的に考慮して、別の事務所に依頼するかどうかを決めましょう。

無料相談できる弁護士一覧
弁護士に支払っていた費用はどうなる?
弁護士に支払っていた費用はどうなるのでしょうか。
着手金
着手金は着手するための費用になりますので、原則として戻ってくることはありません。
裁判所へ納めた費用
代理人が業務停止となったことで手続が直ちに失効するわけではないため、個人再生や自己破産で裁判所に納めた手数料は当然に返金などはされません。
本人が手続遂行困難を理由に取り下げれば、法律で定める範囲内で精算されて返金されると思われますが、どの程度返金されるかはケース・バイ・ケースでしょう。
その他費用
実費は、その都度発生した費用なので、基本的に返金されることはありません。費用の返金などの対応は事務所ごとに異なります。
まとめ
弁護士の「業務停止」とは、弁護士会から弁護士や弁護士法人に対して行われる懲戒のうちの一つです。弁護士の職務を適正にするために行われています。
業務停止を受けた弁護士は、一切弁護士としての活動をすることができなくなります。弁護士の生活を脅かす、非常に強力な処分であるといえるでしょう。
依頼先の弁護士が業務停止を受けた場合には、依頼先の弁護士サイトなどから現状の確認、誰と契約しているか委任契約書で確認する、別の事務所に依頼するか検討するなどが必要です。何か困ったことがあれば、弁護士が所属する弁護士会の相談窓口などにも相談してみましょう。

無料相談できる弁護士一覧
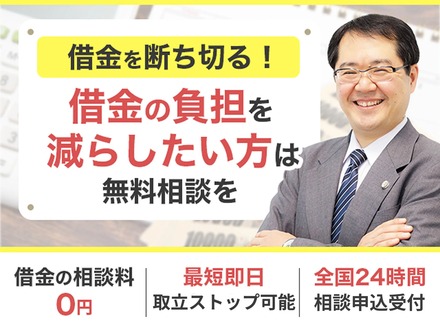
【借金の減額・免除で再スタート!】最短で催促ストップ◆家族や職場にバレにくい解決◆複数社から借り入れ、返済が苦しい等、当事務所へご相談ください【親身に対応◎】【秘密厳守】※借金とは、元本及び利息等を併せた金額をいいます
事務所詳細を見る
「返済のために借入社数が増えてしまっている…」「借金総額が膨らんでわからなくなっている…」毎月の返済額の負担を軽減し、借金生活をやめたい方◆まずは最適な解決のために無料診断を◆
事務所詳細を見る
【借金の減額・免除で再スタート!】最短で催促ストップ◆家族や職場にバレにくい解決◆複数社から借り入れ、返済が苦しい等、当事務所へご相談ください【親身に対応◎】【秘密厳守】※個人間の金銭貸し借り・借金以外の一般法律相談に関する問い合わせは受け付けておりません。
事務所詳細を見る当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

その他に関する新着コラム
-
本記事では、カードローンの滞納を解決できる債務整理である任意整理・個人再生・自己破産について、それぞれの違いを詳しく解説します。カードローンの返済が...
-
本記事では、カードローンを返済できずに困っている方に向けて、カードローンの返済に間に合わない場合の対応、カードローンの返済日に間に合わせるための対処...
-
リボ払いが「やばい」と言われる4つの理由を徹底解説!手数料が高くて残高が減らない仕組みに心当たりはありませんか?返済が困難になる危険なサインや、生活...
-
スーパーブラックでも借りられる?とお悩みの方へ。残念ながら正規の金融機関は皆無です。ですが闇金に頼らず安全にお金を作る方法はあります。公的融資や債務...
-
楽天カードの支払いを滞納すると翌日から遅延損害金の発生や利用停止などのリスクが発生し、滞納が長引くとブラックリスト入りや強制解約など重い措置を取られ...
-
実は、親のせいでローンが組めないというケースは限られており、本人の収入状況や信用情報に問題があることがほとんどです。本記事では、ローンの審査に落ちる...
-
本記事では、借金問題で困っている方に向けて、日本クレジットカウンセリング協会の基本情報と主な特徴、任意整理をする際の流れ(カウンセリングの申し込みか...
-
本記事では、携帯料金を滞納しそうな人や滞納している人に向けて、携帯料金を滞納することによって生じる6つのペナルティ、滞納することがわかった場合に取れ...
-
「本当にお金がない」「誰からも借りられない」と困っている方必見。お金がない際の対処法を、メリットや対象者などを徹底解説します。金融機関からお金を借り...
-
長期間にわたって家賃滞納をした場合は、強制退去のリスクを想定しておかなければなりません。本記事では家賃滞納から強制退去までの流れやその後どうなるかを...
その他に関する人気コラム
-
ブラックリストとは、クレジットカードやカードローンの返済遅延・滞納や債務整理などにより、信用情報機関に事故情報が記録されることを指します。本記事では...
-
専門家の助力があったとしても、今すぐブラックリストを削除することは難しいです。信用情報を回復させる方法、ブラックリストが消えるまでの期間、これ以上悪...
-
携帯料金を滞納したりするとブラックリスト入りしてしまい、携帯電話・スマホの契約を拒否されたり強制解約されたりする可能性があります。本記事では、ブラッ...
-
債務者(さいむしゃ)とは、特定の債権者(さいけんしゃ)に対してお金を借りている、あるいは一定の給付義務を持つ人のことで、ローンの未払いや奨学金の滞納...
-
催告書(さいこくしょ)とは、滞納しているお金等を請求する際に送られてくる書類のことをいいます。この記事では、①催告書の意味②督促状との違い③すぐに払...
-
廃課金とは、廃人と課金を合わせたネットスラングで、一般的に収入に見合わない金額を課金する人を指します。本記事では廃課金の定義や課金してしまう人の特徴...
-
国民健康保険は国民皆保険と呼ばれるように、「20歳以上の社会保険未加入者は国民健康保険へ加入する義務」があるため、もし滞納をしている場合は必ず滞納分...
-
債務不履行とは、故意又は過失によって自分の債務を履行しないことをいいます。債務不履行には、履行遅滞、履行不能、不完全履行の3種類があります。債務不履...
-
買い物依存症とは、借金をしてまでも買い物を続けてしまう症状のことを言います。この記事では買い物依存症の特徴や対処法、すでに借金を作ってしまった人の解...
-
債権者とは、特定の人に対し、一定のお金を請求する権利を持つ人です。要するに、金貸し業者や慰謝料を受け取る人などが該当します。この記事では、債権者が有...
その他の関連コラム
-
便利なクレジットカードですが、支払いを滞納してしまった場合、延滞によるリスクは1日目から発生します。この記事では、滞納するリスクやまずすべきこと、カ...
-
家賃滞納から強制執行までの流れ、回避方法、強制執行決定時の対応をわかりやすく解説しています。督促や内容証明郵便、支払督促、訴訟、強制執行など、それぞ...
-
携帯料金を滞納したりするとブラックリスト入りしてしまい、携帯電話・スマホの契約を拒否されたり強制解約されたりする可能性があります。本記事では、ブラッ...
-
夫の借金が発覚した場合、まずは落ち着いて状況を確認しましょう。本記事では、妻が確認すべきことや返済義務が誰にあるのか、借金を放置するリスクや解決方法...
-
繰り上げ返済の大きなメリットは利息を減らし、返済への負担を軽くすることです。もちろん、他にもメリットはある繰り上げ返済ですが、注意すべきこともありま...
-
スーパーブラックでも借りられる?とお悩みの方へ。残念ながら正規の金融機関は皆無です。ですが闇金に頼らず安全にお金を作る方法はあります。公的融資や債務...
-
突然の解雇・病気・事故などで住宅ローンが払えない状況になる方も少なくありません。せっかく手に入れたマイホームも住宅ローンが払えないことで手放さなくて...
-
任意整理をすると、場合によっては口座凍結が起こります。この記事では、任意整理で口座凍結が起こるケース、口座凍結の期間・対策、口座凍結以外の注意点(ク...
-
ブラックリストとは、クレジットカードやカードローンの返済遅延・滞納や債務整理などにより、信用情報機関に事故情報が記録されることを指します。本記事では...
-
本記事では、ブラックリストに精通した弁護士の特徴・探し方・手続きを依頼する流れなどについて詳しく解説します。ブラックリストが原因で新たな借り入れがで...
-
実は、親のせいでローンが組めないというケースは限られており、本人の収入状況や信用情報に問題があることがほとんどです。本記事では、ローンの審査に落ちる...
-
デビットカードとは、後払いではないクレジットカードと言っても過言ではありません。なじみのある言葉ですが、その仕組みを理解できている人は少ないようです...
弁護士・司法書士があなたの借金返済をサポート
債務整理では、債権者と交渉する任意整理や法的に借金を減額する、個人再生や自己破産などがあります。また、過去の過払い金がある方は、過払い請求を行うことも可能です。
ただ、どれもある程度の法的な知識や交渉力が必要になってきます。債務整理をしたくてもなかなか踏み切れないあなたをベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)の弁護士・司法書士がサポートいたします。