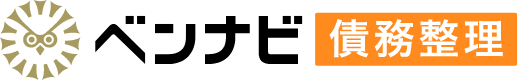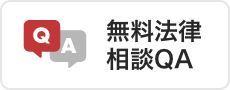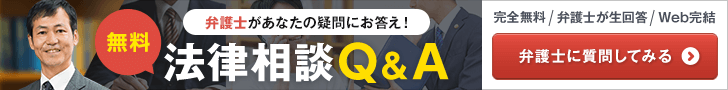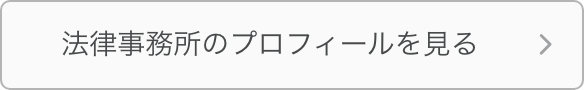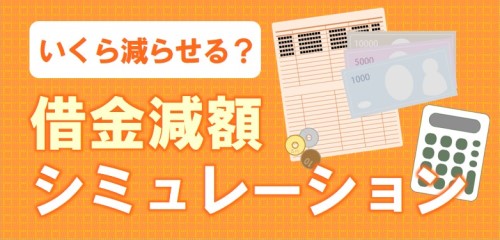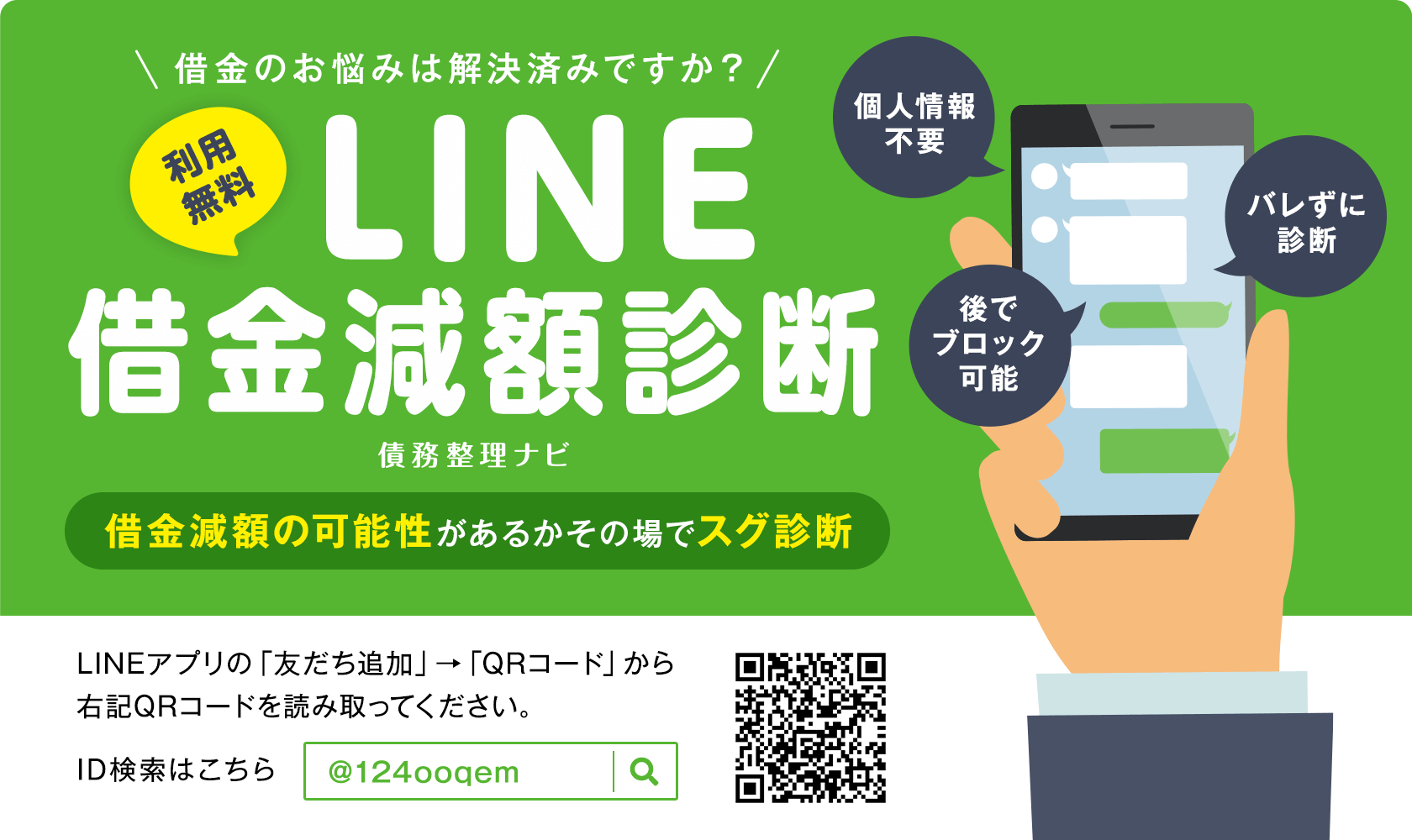携帯料金を滞納した!今すぐできる3つの対処法と支払い遅れを回避する2つの対策

- 「携帯料金を滞納するとどうなるのか?」
- 「携帯料金の滞納状態をどうすれば解消できるのか?」
普段から携帯電話やスマートフォンを使っている人は多く、携帯料金の滞納に関する悩みを持つ人もいるでしょう。
携帯料金を滞納した場合のペナルティはさまざまありますが、すぐに支払いをすればそこまで悪影響はありません。
しかし、滞納状態が続く場合は強制解約や法的措置のリスクがあるため、適切な対応を取ることが重要になります。
本記事では、携帯料金を滞納しそうな人や滞納してしまっている人に向けて、以下の内容について説明します。
- 携帯料金を滞納することによって生じる6つのペナルティ
- 携帯料金を滞納することがわかった場合に取れる2つの対策
- すでに携帯料金を滞納している場合に取るべき3つの対処法 など
本記事を参考に、携帯料金を滞納した場合のペナルティと状況ごとの適切な対処法について理解しましょう。
【大手キャリアごと】携帯料金の滞納タイミングはそもそもいつから?
携帯料金の支払い期限と滞納タイミングは、以下のように携帯会社ごとに異なります。
- ドコモ:原則として月末締め翌月末払い
- KDDI:原則として月末締め翌月25日払い
- ソフトバンク:20日締め翌月16日払い、月末締め翌月26日払い
ここでは、ドコモ・KDDI・ソフトバンクの支払い期限と滞納タイミングについて説明します。
1.ドコモ|原則として月末締め翌月末払い(支払い方法で異なる)
ドコモの利用料金の支払い期限は、原則として月末締め・翌月末払いとなっています。
ただし、以下のように口座振替やクレジットカード払いによって支払い期限は異なります。
|
支払い方法 |
支払い期限 |
|
口座振替の場合 |
翌月末(休日の場合は翌営業日) |
|
クレジットカード払い(dカード)の場合 |
翌月10日(休日の場合は翌営業日) |
|
クレジットカード払い(dカード以外)の場合 |
クレジットカード会社により異なる |
|
請求書払いの場合 |
翌月末(休日の場合は翌営業日) |
ドコモの滞納状況については、「Webビリング」にログインしてから確認することが可能です。
2.KDDI|原則として月末締め翌月25日払い(契約状況で異なる)
KDDIの利用料金の支払い期限は、月末締め・翌月25日払いが基本です。
ただし、契約状況や支払い方法などによって期限は異なるので注意しましょう。
|
契約状況・支払い方法 |
支払い期限 |
|
携帯電話の単独利用の場合 |
翌月25日(休日の場合は翌営業日) |
|
2021年9月1日以前からUQ mobile利用者の場合 |
翌月末(休日の場合は翌営業日) |
|
KDDIまとめて請求の場合 |
翌月末(休日の場合は翌営業日) |
|
クレジットカード払いの場合 |
クレジットカード会社により異なる |
KDDIの滞納状況については、「専用の確認ページ」からログインすることで確認できます。
3.ソフトバンク|20日締め翌月16日払い、月末締め翌月26日払い
ソフトバンクの支払い期限は、原則として「20日締め・翌月16日払い」または「月末締め・翌月26日払い」です。
また、支払い方法にはクレジットカード払いやデビットカード払いがあり、以下のようにタイミングが異なります。
|
契約内容・支払い方法 |
支払い期限 |
|
20日締め契約の場合 |
翌月16日(休日の場合は翌営業日) |
|
月末締め契約の場合 |
翌月26日(休日の場合は翌営業日) |
|
クレジットカード払いの場合 |
クレジットカード会社により異なる |
|
デビットカード払いの場合 |
原則は契約どおり(ただし、指定日より早く引き落としされることがある) |
ソフトバンクの滞納状況については、「My Softbank」の画面などから確認することができます。
携帯料金を滞納するとどうなる?支払い遅れによって生じる6つのリスク
携帯料金を滞納したり、滞納状態が続いたりすると、以下のようなリスクが生じます。
- 電話やSMSで督促を受ける
- 延滞利息や手数料が発生する
- 回線の利用停止がおこなわれる
- 強制解約となり、滞納金額を一括請求される
- 信用情報機関などに滞納状況や事故情報が記録される
- 支払い督促や強制執行などの法的手続きがおこなわれる
ここでは、携帯料金を滞納した場合のリスクやペナルティなどについて説明します。
1.電話やSMSで督促を受ける
携帯料金を滞納すると、早ければ支払期限の翌日から督促を受けます。
最初のうちはSMSや電話などで「〇日までにお支払いください」という連絡があります。
それでも滞納状態が続いていると、「契約解約予告」といった書面が届くことになります。
携帯会社からの督促が続いた場合は、精神的なプレッシャーを感じることになるでしょう。
2.延滞利息や手数料が発生する
滞納状態が続くと、元々の利用料金に加えて延滞利息が発生します。
延滞利息のルールは携帯会社ごとに異なり、以下のようになっています。
【大手携帯会社ごとの延滞利息に関するルール】
|
携帯会社 |
延滞利息のルール |
|
ドコモ |
・携帯料金の延滞利息は年利14.5%である ・端末の分割代金の遅延損害金は年利3%である ・支払い期限から16日以降に延滞利息が発生する |
|
KDDI |
・携帯料金の延滞利息は年利14.5%である ・支払い期日の翌日から延滞利息が発生する |
|
ソフトバンク |
・携帯料金の延滞利息は年利14.5%である ・支払い期日の翌日から延滞利息が発生する |
携帯料金の延滞利息は、いずれの携帯会社も年利14.5%です。
たとえば、1万円の携帯料金を1ヵ月(30日)間滞納した場合は、119円程度の延滞利息が発生します。
また、延滞利息とは別に、回収事務手数料や後日料金支払手数料などが数百円程度かかることも多いです。
契約どおりに支払えたときに比べると、滞納したときのほうが携帯料金の負担は重くなってしまうでしょう。
3.回線の利用停止がおこなわれる
滞納期間が一定日数を超えると、回線停止の対応を取られます。
大手携帯会社ごとの、滞納から回線停止までの目安は以下のとおりです。
- ドコモ:支払い期限の20日〜30日後に利用停止になる
- KDDI:支払い期限の翌月中旬ごろから利用停止になる
- ソフトバンク:支払い期日から1週間〜10日で払込用紙が届き、その後順次利用停止になる
回線が停止されると、通話やインターネット通信などの基本サービスが一切利用できなくなります。
また、滞納金を支払ってもすぐに利用を再開されるわけではないため、不便な状況が続いてしまうでしょう。
4.強制解約となり、滞納金を一括請求される
2〜3ヵ月程度滞納が続いた場合は強制解約となり、滞納金などを一括請求されます。
強制解約をされると、その後は電話やインターネット通信などの機能が全て使えなくなって不便になります。
また、端末代金の残額や携帯料金の滞納分が一括請求され、場合によっては数万円の支払いが必要になります。
5.信用情報機関などに滞納状況や事故情報が記録される
携帯会社は以下のような業界団体や信用情報機関に加盟しており、他社と滞納状況や事故情報を共有しています。
- 電気通信事業者協会(TCA)
- テレコムサービス協会(TELESA)
- 株式会社日本信用情報機構(JICC)
- 株式会社シー・アイ・シー(CIC) など
携帯料金の滞納状況はTCAやTELESAで共有されており、滞納が続いている場合は新規の回線契約が難しいです。
また、携帯端末の未払い情報については、JICCやCICといった信用情報機関に「異動情報」として登録されます。
異動情報が登録されると、端末の分割払いが難しくなるほか、クレジットカードやローンの契約でも不利になります。
なお、信用情報機関に異動情報が登録されるデメリットなどについては、以下のページで詳しく説明します。
6.支払い督促や強制執行などの法的手続きがおこなわれる
強制解約後も支払いがない状態が続くと、支払い督促や少額訴訟といった法的手続きが取られます。
- 支払い督促:簡易裁判所の書記官が支払いを命じる手続きのこと
- 少額訴訟:60万円以下の金銭の支払いを求める簡易な裁判手続きのこと
支払い督促や少額訴訟は債務名義になるため、その後に強制執行がおこなわれる可能性が高いです。
強制執行の手続きが取られた場合は、給料や銀行口座などの財産を差し押さえされることになるでしょう。
携帯料金を滞納することがわかった場合に取れる2つの対策
携帯料金を滞納しそうな場合は、以下の対応を取るのがおすすめです。
- 支払い日までに余裕がある場合…携帯料金を工面する
- 支払い日までに余裕がない場合…携帯会社に相談する
ここでは、支払い日までの期間に応じて取れる2つの対処法を紹介します。
1.支払い日までに余裕がある場合|携帯料金を工面する
支払い日までに数日程度の猶予がある場合は、以下のような方法でお金を工面するとよいでしょう。
- 親や兄弟姉妹などから一時的に借りる
- 日雇いバイトや短期バイトで稼ぐ
- 不用品をリサイクルショップで売る
- ブランド品などを質屋に入れてお金を借りる など
お金を工面する場合には、できる限り即日で資金を調達できる方法を選択することが重要になります。
たとえば、通常のアルバイトやフリマサイトの利用では、即日でお金を工面できない可能性があります。
「携帯料金の支払い期限までにどの程度の余裕があるか」で、選択すべき方法は変わってくるでしょう。
2.支払い日までに余裕がない場合|携帯会社に相談する
支払い日までにお金を用意できない場合は、携帯会社へ連絡してみましょう。
携帯会社に事情を伝えることで、以下のようなサポートを受けられる可能性があります。
- 必要なアドバイスを受けられる
- 支払い期限を延長してくれる
- 分割払いなどに応じてくれる
携帯会社のカスタマーセンターに問い合わせたり、専用のチャットシステムを利用したりするとよいでしょう。
【ケース別】すでに携帯料金を滞納している場合に取るべき3つの対処法
すでに携帯料金を滞納している場合の対処法は、以下のようにケースごとに異なります。
- うっかり忘れの場合…携帯会社からの連絡に従って支払う
- 慢性的に滞納している場合…プランを見直す、格安スマホに変更する
- 借金も多く支払いの見込みがない場合…弁護士に相談して債務整理を進める
ここでは、3つのケースに分けて、それぞれの場合に取るべき具体的な対処法について説明します。
1.うっかり忘れの場合|携帯会社からの連絡に従って支払う
単純な支払い忘れや口座の残高不足などの場合は、早急に携帯会社からの督促連絡に応じて支払いましょう。
通常はSMSやメール、ハガキなどで連絡が来ることが多いため、その内容に従って支払うようにしてください。
すぐに支払った場合は、通信回線の停止や信用情報機関への登録といったペナルティを回避することができます。
なお、今後の滞納を防止するために、以下のような対策をおこなっておくこともおすすめです。
- 請求書払いから、口座引き落とし・クレジットカード払いなどに変更する
- 毎月の携帯料金の支払い日をカレンダーに登録し、リマインダーを設定する など
2.慢性的に滞納している場合|プランを見直す、格安スマホに変更する
携帯料金の滞納が続いている場合は、現状の契約プランが自分の経済状況に見合っていない可能性が高いです。
このような場合は、たとえば、料金が安いプランへの見直しや、格安SIMへの乗り換えなどを検討しましょう。
経済状況によって異なりますが、月々の携帯料金の見直しは、滞納の根本的な解決につながることが多いです。
3.借金も多く支払いの見込みがない場合|弁護士に相談して債務整理を進める
携帯料金だけでなく、ほかの借金も膨らんでおり、今後の支払いが現実的に難しい場合もあるでしょう。
このようなときには任意整理、個人再生、自己破産などの債務整理の手続きを検討することをおすすめします。
- 任意整理:債権者と直接交渉して、支払い期間を調整したり、遅延損害金をカットしたりする手続きのこと
- 個人再生:裁判所の許可を得て、借金額を最大10分の1まで減額してもらう手続きのこと
- 自己破産:裁判所の許可を得て、借金の返済義務を免除してもらう手続きのこと
なお、債務整理ごとにメリット・デメリットが異なるため、自分に合った手続きを選ぶことが重要になります。
借金問題が得意な弁護士に相談をしつつ、自分に合った債務整理の手段を見つけて対応するのがよいでしょう。
携帯料金を滞納している場合に知っておくべき3つの注意点
携帯料金を滞納している人が注意すべきポイントは、以下のとおりです。
- 少額であっても回線停止などはおこなわれる
- カードローンなどの利用はおすすめできない
- 時効による支払いの免除を目指すのは難しい
ここでは、滞納している人向けに知っておくべき3つの注意点について説明します。
1.少額であっても回線停止などはおこなわれる
「滞納額が多い」「滞納額が少ない」など、滞納額の大小はペナルティには影響しません。
仮に携帯料金の滞納額が少額であっても、滞納状態が続けば回線停止や強制解約などはおこなわれます。
「利用額は少ないからまだ大丈夫」などと思わずに、できる限り早く滞納状態の解消を目指しましょう。
2.カードローンなどの利用はおすすめできない
カードローンなどを利用して携帯料金を支払うことは、おすすめできません。
カードローンを利用すれば一時的には携帯料金の支払いに間に合うでしょう。
しかし、新たな借金で支払いをしたに過ぎず、根本的な解決にはなっていないことが多いです。
今度はカードローンへの返済が必要になってしまい、多重債務へとつながるリスクがあるでしょう。
3.時効による支払いの免除を目指すのは難しい
未払い状態になっている携帯料金は、一定期間が過ぎれば消滅時効の援用ができます。
しかし、携帯会社が法的措置を取る可能性は高く、時効援用による免除を目指すのは現実的ではありません。
「そのうち借金は消滅する」などと安易な考えをしていると、より厳しい対応を迫られることになるでしょう。
さいごに|携帯料金以外にも滞納や借金があるなら弁護士に相談しよう
携帯料金を滞納すると、督促がおこなわれたり、延滞利息や遅延損害金が発生したりします。
また、それでも滞納状態が続くと回線停止や強制解約がおこなわれて、法的措置が取られる可能性もあります。
そのため、携帯料金の滞納状態が続いている場合は、できる限り早く解消に向けた対応をすることが重要です。
単なる支払い忘れであれば深刻度は低いですが、もし支払いの見込みがない場合は非常に深刻な問題といえます。
その場合は携帯料金以外の滞納や借金がある場合も多いので、債務整理による解決を検討するのが望ましいです。
多重債務や自転車操業などの借金問題で困っているなら、まずは債務整理が得意な弁護士に相談してみましょう。

【全国65拠点以上】【問い合わせ件数1日1,000件以上】【周りに知られずに相談OK】はじめの一歩は弁護士への無料相談!あなたの街のアディーレに、何でもお気軽にご相談ください ※ 2024年1月~12月の平均受電数より問い合わせ件数算出
事務所詳細を見る
【全国65拠点以上】【問い合わせ件数1日1,000件以上】【周りに知られずに相談OK】はじめの一歩は弁護士への無料相談!あなたの街のアディーレに、何でもお気軽にご相談ください ※ 2024年1月~12月の平均受電数より問い合わせ件数算出
事務所詳細を見る
【自宅・資産を守りながら借金を解決】個人再生で新たなスタートを切るお手伝いをします!借金減額・月々の支払いの軽減で負担の少ない返済を/オンライン相談・分割払い可◎/まずは無料相談から!任意整理・自己破産・法人破産にも対応
事務所詳細を見る当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

その他に関する新着コラム
-
本記事では、カードローンの滞納を解決できる債務整理である任意整理・個人再生・自己破産について、それぞれの違いを詳しく解説します。カードローンの返済が...
-
本記事では、カードローンを返済できずに困っている方に向けて、カードローンの返済に間に合わない場合の対応、カードローンの返済日に間に合わせるための対処...
-
リボ払いが「やばい」と言われる4つの理由を徹底解説!手数料が高くて残高が減らない仕組みに心当たりはありませんか?返済が困難になる危険なサインや、生活...
-
スーパーブラックでも借りられる?とお悩みの方へ。残念ながら正規の金融機関は皆無です。ですが闇金に頼らず安全にお金を作る方法はあります。公的融資や債務...
-
楽天カードの支払いを滞納すると翌日から遅延損害金の発生や利用停止などのリスクが発生し、滞納が長引くとブラックリスト入りや強制解約など重い措置を取られ...
-
実は、親のせいでローンが組めないというケースは限られており、本人の収入状況や信用情報に問題があることがほとんどです。本記事では、ローンの審査に落ちる...
-
本記事では、借金問題で困っている方に向けて、日本クレジットカウンセリング協会の基本情報と主な特徴、任意整理をする際の流れ(カウンセリングの申し込みか...
-
本記事では、携帯料金を滞納しそうな人や滞納している人に向けて、携帯料金を滞納することによって生じる6つのペナルティ、滞納することがわかった場合に取れ...
-
「本当にお金がない」「誰からも借りられない」と困っている方必見。お金がない際の対処法を、メリットや対象者などを徹底解説します。金融機関からお金を借り...
-
長期間にわたって家賃滞納をした場合は、強制退去のリスクを想定しておかなければなりません。本記事では家賃滞納から強制退去までの流れやその後どうなるかを...
その他に関する人気コラム
-
ブラックリストとは、クレジットカードやカードローンの返済遅延・滞納や債務整理などにより、信用情報機関に事故情報が記録されることを指します。本記事では...
-
専門家の助力があったとしても、今すぐブラックリストを削除することは難しいです。信用情報を回復させる方法、ブラックリストが消えるまでの期間、これ以上悪...
-
携帯料金を滞納したりするとブラックリスト入りしてしまい、携帯電話・スマホの契約を拒否されたり強制解約されたりする可能性があります。本記事では、ブラッ...
-
債務者(さいむしゃ)とは、特定の債権者(さいけんしゃ)に対してお金を借りている、あるいは一定の給付義務を持つ人のことで、ローンの未払いや奨学金の滞納...
-
催告書(さいこくしょ)とは、滞納しているお金等を請求する際に送られてくる書類のことをいいます。この記事では、①催告書の意味②督促状との違い③すぐに払...
-
廃課金とは、廃人と課金を合わせたネットスラングで、一般的に収入に見合わない金額を課金する人を指します。本記事では廃課金の定義や課金してしまう人の特徴...
-
国民健康保険は国民皆保険と呼ばれるように、「20歳以上の社会保険未加入者は国民健康保険へ加入する義務」があるため、もし滞納をしている場合は必ず滞納分...
-
債務不履行とは、故意又は過失によって自分の債務を履行しないことをいいます。債務不履行には、履行遅滞、履行不能、不完全履行の3種類があります。債務不履...
-
買い物依存症とは、借金をしてまでも買い物を続けてしまう症状のことを言います。この記事では買い物依存症の特徴や対処法、すでに借金を作ってしまった人の解...
-
債権者とは、特定の人に対し、一定のお金を請求する権利を持つ人です。要するに、金貸し業者や慰謝料を受け取る人などが該当します。この記事では、債権者が有...
その他の関連コラム
-
連帯保証人と保証人は名称こそ似ているものの、生じる責任に大きな違いがあります。本記事では、連帯保証人と保証人の違いについてわかりやすく解説しています...
-
国民年金を未納のまま放置していると差押えを受ける可能性があります。ただし、差押えの実行には条件があるほか、差押えの対象にならない財産などもあります。...
-
この記事では仮想通貨で借金が起こる原因とその対処法についてまとめました。借金を背負ってしまった方はもちろん、これから仮想通貨を購入してみたいと考えて...
-
廃課金とは、廃人と課金を合わせたネットスラングで、一般的に収入に見合わない金額を課金する人を指します。本記事では廃課金の定義や課金してしまう人の特徴...
-
催告書(さいこくしょ)とは、滞納しているお金等を請求する際に送られてくる書類のことをいいます。この記事では、①催告書の意味②督促状との違い③すぐに払...
-
本記事では、カードローンの滞納を解決できる債務整理である任意整理・個人再生・自己破産について、それぞれの違いを詳しく解説します。カードローンの返済が...
-
「ブラックでもお金を借りることができますか?」答えは「イエス」です。「キャッシング審査に通りやすい業者ってないですか?」答えは「イエス」です。ブラッ...
-
リボ払いが「やばい」と言われる4つの理由を徹底解説!手数料が高くて残高が減らない仕組みに心当たりはありませんか?返済が困難になる危険なサインや、生活...
-
債権者とは、特定の人に対し、一定のお金を請求する権利を持つ人です。要するに、金貸し業者や慰謝料を受け取る人などが該当します。この記事では、債権者が有...
-
任意売却をして残っている住宅ローンや借金を返済したいと考えても、差し押さえられてしまった場合はどのようにすればいいのでしょうか?この記事では、差し押...
-
多重債務者とは、2件以上の貸金業者から借り入れがある人のことをいいます。この記事では、多重債務者の特徴と現状をお伝えした上で、多重債務者になりやすい...
-
ブラックリストに掲載される期間はどの程度なのでしょうか。 よく、「ブラックリストに載るとカードが作れない」などという話を聞きますが、そもそもブラック...
弁護士・司法書士があなたの借金返済をサポート
債務整理では、債権者と交渉する任意整理や法的に借金を減額する、個人再生や自己破産などがあります。また、過去の過払い金がある方は、過払い請求を行うことも可能です。
ただ、どれもある程度の法的な知識や交渉力が必要になってきます。債務整理をしたくてもなかなか踏み切れないあなたをベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)の弁護士・司法書士がサポートいたします。