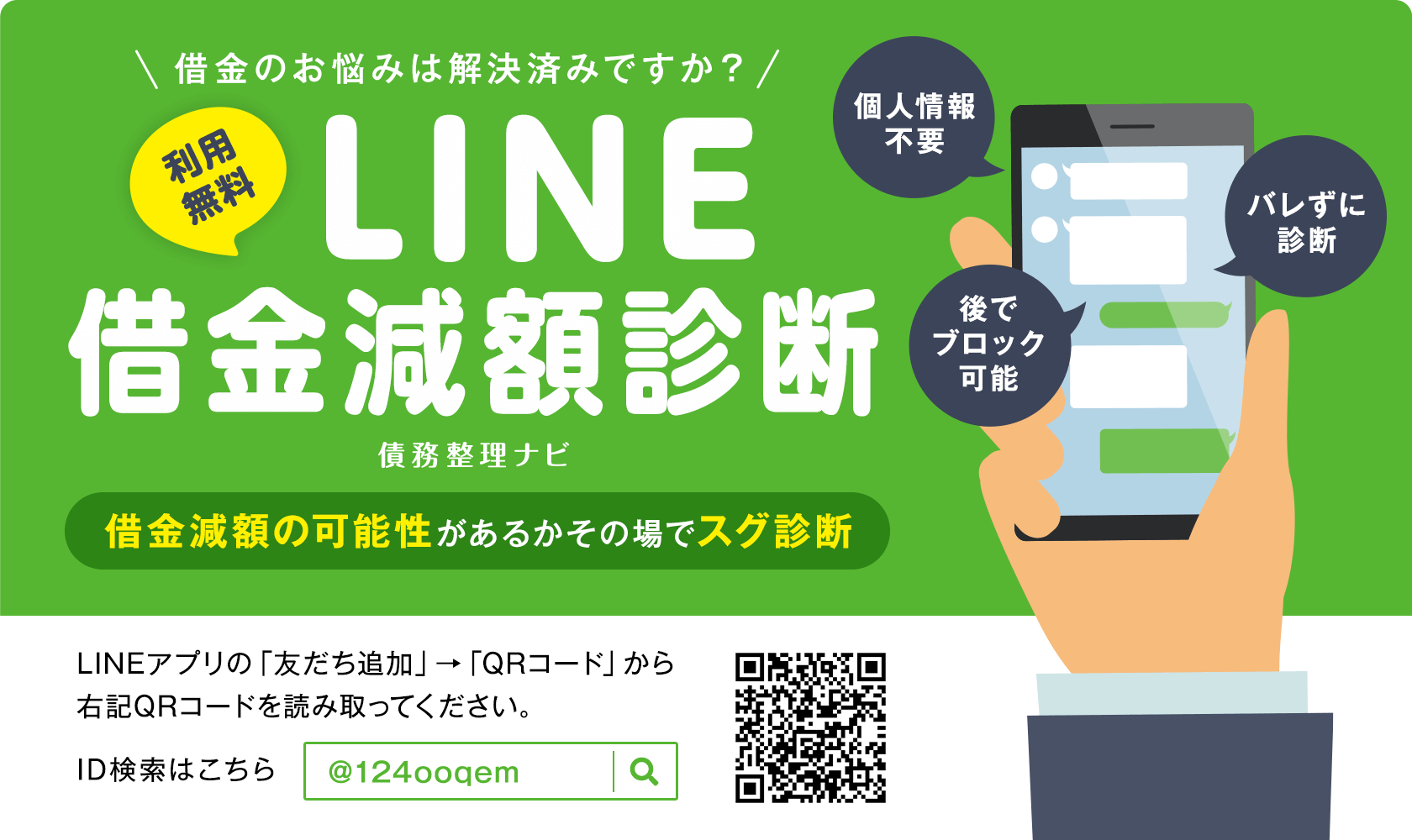滞っている
知りたい
止めたい…
相談したい?

国民年金は、原則として日本国内に住む20歳以上60歳未満の全ての人に加入義務があります。
自身の老後のために積み立てるのではなく、現在では保険料を支払っている人が年金をもらっている人達を支えるという世代間扶養の仕組みとなっています。
少子化問題や消えた年金問題などで年金に関する不安があっても、国民には納付義務があるので年金について真剣に考えなければいけません。
「支払い忘れや意図的な滞納では差し押さえのリスクがある」ということもきちんと把握しておく必要があります。
本記事では、年金未納で差押えを受ける場合の流れや、差押えの条件などを解説します。
国民年金を滞納した場合、財産の差押えを受ける可能性があります。
ここでは、実際の未納率や差押え件数などについて解説します。
厚生労働省の公表資料によると、2023年度の国民年金の納付率は83.1%となっています。
納付率は右肩上がりの状態が続いている一方、未納者は約79万人で前年度よりも10万人ほど減少しており、それでもまだ一定数の未納者がいるという状態にあります。
厚生労働省の公表資料によると、2023年度に実施された年金未納による差押え件数は3万789件となっています。
また、年金未納者に対する最終催告状の送付件数は17万6,779件、督促状の送付件数は10万2,238件となっており、これらにも応じなかった場合に最終手段として差押えが実行されます。
国民年金の支払いには時効があり、納付期限から2年を過ぎると支払義務が消滅します(国民年金法第102条4項)。
ただし、実際には滞納状態が続くと督促状などが届き、その時点で時効はリセットされるため、基本的に時効で逃げ切ることは困難です。
国民年金を滞納しているからといって、全てのケースで差押えが実行されるわけではありません。
差押えの対象となるのは以下のようなケースです。
所得とは「収入から各種控除や必要経費などを差し引いた金額」のことを指します。
たとえば「月収40万円・必要経費10万円」という場合、1ヵ月あたりの所得額は30万円、年間取得額は360万円で300万円を超えているため、差押えの対象となります。
「国民年金の未納期間が7ヵ月以上」ということも差押えの条件です。
すでに滞納状態が続いており、もうすぐ7ヵ月経ちそうな場合は、速やかに分割納付や免除申請などをおこないましょう。
国民年金を滞納して差押えがおこなわれる場合、基本的には以下のような流れで進行します。
はじめのうちは電話や書面などで支払いを求める通知がおこなわれます。
通知を受けても無視していると「特別催告状」という書類が届いて支払いを催促され、それでも支払わない場合は「最終催告状」が届きます。
最終催告状には、支払い期限のほか、期限を過ぎても支払わない場合は差押えを実行する旨などが記載されています。
なお、ここまでの段階であれば、納付猶予の申請などをおこなっても認めてもらえる可能性があります。
最終催告状が届いても無視していると「督促状」が届きます。
督促状には、支払い期限や差押えの実行などについて記載されているほか、期限を過ぎても支払わない場合はペナルティとして延滞金なども発生します。
督促状が届いても無視していると「差押予告通知書」が届きます。
これは差押え前に送られる最後の書類であり、この段階で滞納者に対する財産調査などもおこなわれています。
差押予告通知書が届いても無視していると、財産の差押えがおこなわれます。
具体的にどのような財産が差押えられるのかについては「国民年金の未納で差押えの対象になる財産・ならない財産」で後述します。
国民年金の未納によって差押えがおこなわれる場合、主に以下のような財産が対象となります。
一方、例外として以下のような財産は差押えの対象外となります。
失業中や病気などの理由でどうしても支払えない場合は、以下のような対応を検討しましょう。
国民年金保険料には納付猶予や免除などの制度があります。
学生・生活保護受給者・失業者・前年所得が一定額以下の方・産前産後期間中の方など、さまざまな方が対象となり、免除については全額・4分の3・半額・4分の1の4種類あります。
納付猶予や免除を受けることで将来の受給額は減ってしまいますが、10年以内であれば追納することで受給額を増やすこともできます。
なお、これらの制度を利用するには申請書などを作成して申請する必要があり、具体的な流れや必要書類などについては「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」をご確認ください。
債務整理とは借金問題を解決する手続きの総称のことで、具体的には以下のような方法があります。
手続きによってそれぞれメリット・デメリットがあり、たとえば任意整理の場合は減額効果が比較的小さく、自己破産の場合は価値のある財産を処分する必要があります。
どれが向いているのかは状況によって異なるうえ、特に個人再生や自己破産では裁判所とのやり取りなども必要であるため、債務整理を検討する際は弁護士や司法書士に相談しましょう。
事務所によっては「何度でも相談無料」というところもあり、依頼はせずに相談だけ利用することも可能ですので、依頼するかどうか悩んでいる方も一度利用してみることをおすすめします。
ここでは、年金未納時の差押えに関するよくある質問について解説します。
年金未納のまま放置していると、財産の差押えを受ける可能性があります。
督促状に記載されている支払い期限を過ぎてしまうと延滞金なども発生するため、なるべく早いうちに対応しましょう。
「国民年金の未納期間が7ヵ月以上」「年間所得額が300万円以上」などの条件を満たしている場合、差押え対象となります。
具体的な期間は不明ですが、国民年金の未納期間が7ヵ月以上になると差押えに向けた手続きが進められます。
最終的には、差押予告通知書に記載された期限内に支払えないと差押えが実行されるため、差押えを回避するためには無視せず期間内に支払いましょう。
国民年金法第88条2項・3項に基づき、国民年金の未納については配偶者などの同居家族の財産も差押え対象になります。
国民年金の支払いは国民の義務であるため、当然ですが滞納などはせずに支払うようにしましょう。
もし失業中や病気などの理由で支払いが難しい場合は、納付猶予や免除などが認められる可能性があるため、差押えを受ける前に速やかに申請手続きをおこないましょう。
借金を抱えている場合は債務整理が効果的ですが、状況によって取るべき対応は異なるため、債務整理が得意な弁護士や司法書士に相談してみることをおすすめします。
当サイト「ベンナビ債務整理」では、「初回相談無料」「何度でも相談無料」などの事務所を多数掲載しているので、まずは一度利用してみましょう。

闇金問題の相談窓口【初回相談無料/分割払い・後払い対応】闇金問題に豊富な経験あり・月間400件以上の解決実績のある司法書士が違法な取り立てからお客様を解放します/任意整理・時効援用にも対応可<即日対応・24時間体制>
事務所詳細を見る
◆相談実績10万件以上◆【月々の返済額を減らしたい】【利息分しか返済が出来てない】【家族に知られずに解決したい】という方はぜひご相談を!【リーズナブルな料金体系|分割払い対応】
事務所詳細を見る
【ご相談は何度でも無料】【分割払可】債務整理のデメリットが不安で、依頼を迷っていませんか?借金でお困りの方は早期にご相談ください!丁寧に説明した上で、依頼者様に最善の方法をご提案します。
事務所詳細を見る
本記事では、カードローンの滞納を解決できる債務整理である任意整理・個人再生・自己破産について、それぞれの違いを詳しく解説します。カードローンの返済が...
本記事では、カードローンを返済できずに困っている方に向けて、カードローンの返済に間に合わない場合の対応、カードローンの返済日に間に合わせるための対処...
リボ払いが「やばい」と言われる4つの理由を徹底解説!手数料が高くて残高が減らない仕組みに心当たりはありませんか?返済が困難になる危険なサインや、生活...
スーパーブラックでも借りられる?とお悩みの方へ。残念ながら正規の金融機関は皆無です。ですが闇金に頼らず安全にお金を作る方法はあります。公的融資や債務...
楽天カードの支払いを滞納すると翌日から遅延損害金の発生や利用停止などのリスクが発生し、滞納が長引くとブラックリスト入りや強制解約など重い措置を取られ...
実は、親のせいでローンが組めないというケースは限られており、本人の収入状況や信用情報に問題があることがほとんどです。本記事では、ローンの審査に落ちる...
本記事では、借金問題で困っている方に向けて、日本クレジットカウンセリング協会の基本情報と主な特徴、任意整理をする際の流れ(カウンセリングの申し込みか...
本記事では、携帯料金を滞納しそうな人や滞納している人に向けて、携帯料金を滞納することによって生じる6つのペナルティ、滞納することがわかった場合に取れ...
「本当にお金がない」「誰からも借りられない」と困っている方必見。お金がない際の対処法を、メリットや対象者などを徹底解説します。金融機関からお金を借り...
長期間にわたって家賃滞納をした場合は、強制退去のリスクを想定しておかなければなりません。本記事では家賃滞納から強制退去までの流れやその後どうなるかを...
ブラックリストとは、クレジットカードやカードローンの返済遅延・滞納や債務整理などにより、信用情報機関に事故情報が記録されることを指します。本記事では...
専門家の助力があったとしても、今すぐブラックリストを削除することは難しいです。信用情報を回復させる方法、ブラックリストが消えるまでの期間、これ以上悪...
携帯料金を滞納したりするとブラックリスト入りしてしまい、携帯電話・スマホの契約を拒否されたり強制解約されたりする可能性があります。本記事では、ブラッ...
債務者(さいむしゃ)とは、特定の債権者(さいけんしゃ)に対してお金を借りている、あるいは一定の給付義務を持つ人のことで、ローンの未払いや奨学金の滞納...
催告書(さいこくしょ)とは、滞納しているお金等を請求する際に送られてくる書類のことをいいます。この記事では、①催告書の意味②督促状との違い③すぐに払...
廃課金とは、廃人と課金を合わせたネットスラングで、一般的に収入に見合わない金額を課金する人を指します。本記事では廃課金の定義や課金してしまう人の特徴...
国民健康保険は国民皆保険と呼ばれるように、「20歳以上の社会保険未加入者は国民健康保険へ加入する義務」があるため、もし滞納をしている場合は必ず滞納分...
債務不履行とは、故意又は過失によって自分の債務を履行しないことをいいます。債務不履行には、履行遅滞、履行不能、不完全履行の3種類があります。債務不履...
買い物依存症とは、借金をしてまでも買い物を続けてしまう症状のことを言います。この記事では買い物依存症の特徴や対処法、すでに借金を作ってしまった人の解...
債権者とは、特定の人に対し、一定のお金を請求する権利を持つ人です。要するに、金貸し業者や慰謝料を受け取る人などが該当します。この記事では、債権者が有...
楽天カードの支払いを滞納すると翌日から遅延損害金の発生や利用停止などのリスクが発生し、滞納が長引くとブラックリスト入りや強制解約など重い措置を取られ...
買い物依存症とは、借金をしてまでも買い物を続けてしまう症状のことを言います。この記事では買い物依存症の特徴や対処法、すでに借金を作ってしまった人の解...
結論からいいますと、借金がある状態でも生活保護を受けることができます。そこで、生活保護と借金の関係を深堀していきたいと思います。
ブラックリストとは、クレジットカードやカードローンの返済遅延・滞納や債務整理などにより、信用情報機関に事故情報が記録されることを指します。本記事では...
廃課金とは、廃人と課金を合わせたネットスラングで、一般的に収入に見合わない金額を課金する人を指します。本記事では廃課金の定義や課金してしまう人の特徴...
水道料金を滞納してしまうと、水を使えなくなるだけではなく、ブラックリスト入りしたり給料の差し押さえなどのリスクがあります。この記事では、滞納から給水...
個人再生は裁判所を介して借金の返済計画手続きを申立てることで借金を大幅に減額することができますが、一方で、車を手放すことになるとも言われています。本...
代位弁済とは、滞納した借金を保証会社などの第三者が代わりに支払ってくれることを指します。代位弁済後は保証会社への一括返済が必要となり、支払いを怠ると...
本記事では、自己破産をする前の注意点から実際に自己破産を進める方法をお伝えしたいと思います。また、費用をかけずに自己破産をする方法も解説します。自己...
本記事では、借金問題で困っている方に向けて、日本クレジットカウンセリング協会の基本情報と主な特徴、任意整理をする際の流れ(カウンセリングの申し込みか...
便利なクレジットカードですが、支払いを滞納してしまった場合、延滞によるリスクは1日目から発生します。この記事では、滞納するリスクやまずすべきこと、カ...
家賃滞納から強制執行までの流れ、回避方法、強制執行決定時の対応をわかりやすく解説しています。督促や内容証明郵便、支払督促、訴訟、強制執行など、それぞ...
弁護士・司法書士があなたの借金返済をサポート
債務整理では、債権者と交渉する任意整理や法的に借金を減額する、個人再生や自己破産などがあります。また、過去の過払い金がある方は、過払い請求を行うことも可能です。
ただ、どれもある程度の法的な知識や交渉力が必要になってきます。債務整理をしたくてもなかなか踏み切れないあなたをベンナビ債務整理(旧:債務整理ナビ)の弁護士・司法書士がサポートいたします。