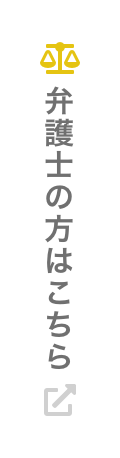自己破産の無料相談窓口|弁護士費用や生活の影響も解説


深刻な借金問題を抱えている方は、自己破産の手続きを申し立てることで解決できる可能性があります。
しかし、自己破産についてどこに相談すればよいかわからない方は少なくありません。
適切に自己破産の手続きを進めるためには、信頼できる弁護士に依頼しましょう。
本記事では、自己破産はどこに相談すればよいのかについて解説します。
また、弁護士の選び方や無料相談の活用ポイントにも触れていくため、ぜひ参考にしてみてください。
|
債務整理について弁護士に相談する 電話相談可・初回面談無料・完全成功報酬 の事務所も多数掲載! |
|
|---|---|
| 北海道・東北 | 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 |
| 関東 | 東京 | 神奈川 | 埼玉 | 千葉 | 茨城 | 群馬 | 栃木 |
| 北陸・甲信越 | 山梨 | 新潟 | 長野 | 富山 | 石川 | 福井 |
| 東海 | 愛知 | 岐阜 | 静岡 | 三重 |
| 関西 | 大阪 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 奈良 | 和歌山 |
| 中国・四国 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 |
| 九州・沖縄 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
自己破産や借金問題について無料相談できる窓口7選
借金問題をどこに相談すれば良いかわからないという方は、まず無料相談をしてみましょう。
ここでは、自己破産を検討している人が無料相談できる相談窓口3つと、借金問題について相談したい人の相談窓口4つをご紹介します。
自己破産を検討している人の相談窓口
自己破産を検討している場合は、弁護士や司法書士に直接無料相談ができる、以下の窓口をおすすめします。
法テラス
法テラスは正式名称を「日本司法支援センター」といい、国が設立した法律トラブル解決のための総合案内所です。
一定の要件を満たしている人は、法テラスと契約している弁護士や司法書士に、無料で相談することができます。
法テラスの無料相談の時間は1回30分程度と限られており、ひとつの問題について3回までしか相談できません。
法テラスの無料相談は法テラスで無料相談できる内容はどこまで?利用するための条件や注意点も解説をご覧ください。
無料相談を受けるための資力要件(収入基準と資産基準)は以下になります。
【収入が一定額以下であること】
|
家族の人数 |
収入基準 (手取月収額。()内は東京、大阪などの大都市の場合) |
資産基準 |
|
単身者 |
18万2,000(20万200)円以下 |
180万円以下 |
|
2人家族 |
25万1,000(27万6,100)円以下 |
250万円以下 |
|
3人家族 |
27万2,000(29万9,200)円以下 |
270万円以下 |
|
4人家族 |
29万9,000(32万8,900)円以下 |
300万円以下 |
また、法テラスの無料相談を受けるためには、民事法律扶助の趣旨に適すること、という条件を満たしていることも必要です。
報復的感情を満たすためだけの場合や、権利濫用的な訴訟の場合などでは、法テラスの支援を受けることができません。
市役所の法律相談
各自治体では、その地域の在住者などを対象に定期的に法律相談を受け付けている場合があります。
借金問題に限らず様々な法律相談があり、多重債務の相談を受け付けているかは市区町村によります。
事前に自分が住んでいる市区町村のホームページを確認しましょう。
市役所の法律相談のメリットは、無料で弁護士に相談できる点にありますが、相談には20分~45分ほどの時間制限が設けられていることがほとんどです。
お近くの弁護士・司法書士事務所
自己破産することを決めている方は、ご自宅や勤務先に近い弁護士事務所や司法書士事務所に直接相談問い合わせてみるとよいでしょう。
弁護士・司法書士事務所を選ぶときのポイントは、債務整理の事件を多く扱っている事務所を選ぶことです。
債務整理を多く扱っている弁護士や司法書士であれば、ケースごとに自己破産が必要なのか、他の解決策はないのかなど的確なアドバイスをもらえます。
相談時間や相談料などは事務所によって異なるので、まずは無料相談が可能な弁護士・司法書士事務所を探して、自己破産について相談してみるとよいでしょう。
【関連記事】【トラブル別】弁護士に無料で法律相談できるおすすめ相談窓口|24時間・電話相談あり
その他借金問題について相談したい人の相談窓口
借金癖を見直したいなど、借金問題について相談したいという方には、以下のような相談窓口があります。
日本クレジットカウンセリング協会
日本クレジットカウンセリング協会は、多重借金に苦しむ人に対し、消費者保護の立場から構成・中立にカウンセリングを行ってくれる公益財団法です。
「多重債務ほっとライン」という、電話での無料相談を受け付けている他、対面による無料カウンセリングもおこなっています。
カウンセリングでは弁護士とアドバイザーによるアドバイスが得られる他、希望すれば無料で任意整理をしてもらえる場合もあります。
【参考】多重債務ほっとライン|日本クレジットカウンセリング協会
日本貸金業協会
日本貸金業協会は、貸金業法に基づく貸金業界の自主規制機関です。
貸金業者への苦情や相談の窓口として、「貸金業相談・紛争解決センター」を開設しています。
多重債務の問題については、相談者の状況に応じ、債務整理の方法等についてのアドバイスを受けられたり、再発防止を目的としたカウンセリングや家計管理の支援なども行ってくれます。
【参考】貸金業相談・紛争解決センターについて|日本貸金業協会
金融庁
金融庁は金融機能の安定、金融円滑化等を目的として活動する行政機関であり、多重債務問題解決の取り組みもおこなっています。
都道府県ごとに多重債務者の無料相談窓口が設けられ、電話などでアドバイスをしてくれますので、問題解決の助けになるでしょう。
全国銀行協会相談室・あっせん委員会
全国銀行協会は、日本国内で活動している銀行を直接の会員とする組織で、日本の銀行業界の代表として、日本の銀行業の発展に取り組んでいる組織です。
全国銀行協会では、多重債務に苦しむ方に対するカウンセリングのサービスを行っているほか、銀行とのトラブル解決のためのあっせんなどもおこなっています。
自己破産における相談の流れ
自己破産の手続きを進めるにあたって、主に下記の流れで相談します。
- 相談先を決める
- 相談先を決めたら、相談予約をする
- 面談をする
- 依頼するかどうかを決める
①相談先を決める
まずは、自己破産に詳しい専門家を探します。自己破産は自身でも手続きを進めることは可能です。
しかし、書類作成や関係各所とのやり取りにおいて専門的な知識が必要になったり、裁判所へ出頭する回数が多くなったりするため、代理権を持つ弁護士への相談・依頼がおすすめです。
弁護士に自己破産の手続きを依頼すると、消費者金融などの貸金業者に対し受任通知を送ります。
受任通知を受け取った貸金業者はお金を借りている依頼者に対し返済を請求できなくなるため、督促が止まります。
弁護士の特徴や実績を確認のうえ、相談先を決めましょう。
②相談先を決めたら、相談予約をする
相談・依頼したい弁護士が決まったら、相談予約をしましょう。無料相談を実施している弁護士に相談すれば、初回は費用がかからないため安心です。
ただし、弁護士によって無料相談の有無・回数・時間などは異なるため、事前に確認しておきましょう。
たとえば、初回30分無料・ひとつの問題について3回まで相談無料など、弁護士によって条件に違いがあります。
また、法律事務所へ相談する際は原則として事前予約をする必要があるため、電話やWebサイトなどで問い合わせてください。
③面談をする
予約の時間になったら、実際に弁護士と面談します。自己破産の相談をする際には、弁護士から以下のような内容を質問されるため、事前に答えを用意しておきましょう。
- 借金の総額
- 借入先
- 借金の理由
- 現在の収入や財産の状況
- 希望する手続きの種類 など
無料相談の時間は限られていることが多いですが、事前に質問への回答を用意すれば、短時間のうちにも有益なアドバイスを受けられます。
④依頼するかどうかを決める
弁護士との面談を通じて信頼できる、自己破産の手続きを任せられると感じた場合、正式な依頼へと進みましょう。
もちろん、相談したからといって必ず依頼しなければならないわけではありません。
時間に余裕がある場合は複数の法律事務所の無料相談を利用し、自分に合った弁護士を探したうえで依頼しましょう。
また、弁護士によって自己破産の手続きに要する費用は異なるので、見積もりを比較して選ぶことも大切です。
|
債務整理について弁護士に相談する 電話相談可・初回面談無料・完全成功報酬 の事務所も多数掲載! |
|
|---|---|
| 北海道・東北 | 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 |
| 関東 | 東京 | 神奈川 | 埼玉 | 千葉 | 茨城 | 群馬 | 栃木 |
| 北陸・甲信越 | 山梨 | 新潟 | 長野 | 富山 | 石川 | 福井 |
| 東海 | 愛知 | 岐阜 | 静岡 | 三重 |
| 関西 | 大阪 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 奈良 | 和歌山 |
| 中国・四国 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 |
| 九州・沖縄 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
自己破産の相談先は弁護士がおすすめな理由
自己破産について相談できる専門家としては、弁護士と司法書士が挙げられます。
いずれも法律の専門家ですが、自己破産の手続きを適切に進めるには、弁護士への相談・依頼がおすすめです。
司法書士は、自己破産の申立書類の作成のみに対応しており、裁判所でおこなわれる破産手続きの代理人となることができません。
そのため、実際の申立ては債務者自身がおこなう必要があります。
一方、弁護士は破産手続きの代理人として対応可能です。必要な手続きの大半を代行してもらえるため、手間が大幅に省けます。
自己破産について相談する弁護士の選び方
自己破産については、適任の弁護士を選んで相談することが大切です。
ここでは、自己破産を相談する弁護士の選び方を解説します。
債務整理に強みがある弁護士を選ぶ
弁護士には離婚問題・相続・交通事故・刑事事件など、それぞれ得意分野があります。
そのため、自己破産を成功させたいと考えている方は借金問題や債務整理を得意とする弁護士を選びましょう。
弁護士の得意分野を確認する際には、法律事務所のホームページが参考になります。
実績や債務整理手続きの解説などが豊富に掲載されていれば、借金問題や債務整理についてきちんと対応してもらえる可能性が高いでしょう。
ほかにも、法律事務所の情報をまとめたポータルサイト(「ベンナビ」など)を利用すると、債務整理を得意とする弁護士を見つけやすいです。
複数の法律事務所を確認し比較検討をする
抱えている借金問題が深刻で急いでいる場合でも、ひとつの法律事務所だけに相談・依頼するのは危険です。
弁護士との相性が合わない、弁護士費用が高すぎるなどのトラブルに繋がるおそれがあります。
弁護士に相談する際には、複数の法律事務所を比較しましょう。そうすることで、自分に合った弁護士を選べる可能性が高くなります。
法律事務所のホームページを確認することで、得意分野や実績などは確認できることがありますが、依頼する弁護士の人柄などは相談しなければわかりません。
また、具体的な弁護士費用の金額も、見積もりを提示してもらうことで初めてわかります。
複数の事務所の無料相談を利用し、信頼して依頼できる弁護士を見つけましょう。
|
債務整理について弁護士に相談する 電話相談可・初回面談無料・完全成功報酬 の事務所も多数掲載! |
|
|---|---|
| 北海道・東北 | 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 |
| 関東 | 東京 | 神奈川 | 埼玉 | 千葉 | 茨城 | 群馬 | 栃木 |
| 北陸・甲信越 | 山梨 | 新潟 | 長野 | 富山 | 石川 | 福井 |
| 東海 | 愛知 | 岐阜 | 静岡 | 三重 |
| 関西 | 大阪 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 奈良 | 和歌山 |
| 中国・四国 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 |
| 九州・沖縄 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
自己破産の無料相談を有効活用するポイント
弁護士への無料相談は、時間が制限されているケースがほとんどです。
貴重な時間を無駄にしないためにも、以下のポイントを押さえておきましょう。
- 質問を箇条書きにして準備しておく
- 相談時に伝える項目を用意する
- 自分の希望を明確にしておく
質問を箇条書きにして準備しておく
自己破産などの債務整理の手続きが初めての方であれば、具体的な流れがわからず不安になることは少なくありません。
たとえば、自己破産が認められるまでの期間や必要な費用、借金問題を解決するほかの方法など、知りたいことはたくさんあるでしょう。
その場で思いつくままに質問をしていると、本当に聞きたいことが聞けなかったということになりかねません。
事前に聞きたい内容を箇条書きでメモしておくと、無料相談の時間内で効率的に質問できます。
相談時に伝える項目を用意する
自己破産について弁護士に相談する際は、以下のような内容を質問されます。
その問いに対してスムーズに回答するためにも、事前に情報をまとめておきましょう。
- 借金総額・全債権者名・各借入金額
- 過去の債務整理の有無
- 返済の滞納歴(債権者名と滞納期間)
- 債権者からの督促の有無
- 所有する財産
- 職業・年収
- 家族構成
- 家計全体の収支
想定される主な質問について、あらかじめ回答をまとめておくことで、時間を無駄にせず相談を進められます。
自分の希望を明確にしておく
借金問題を解決したい場合、自身の希望を明確にしておくことも必要です。
たとえば、借金問題が解決するまでに要する時間や費用などについての希望を明確にすることで、弁護士もそれに応じた提案が可能となります。
ただし、本人は自己破産を希望している場合でも、ほかの債務整理手続きの方が適しているケースは少なくありません。
弁護士から自己破産以外の債務整理手続きを提案された場合には、アドバイスを踏まえて真剣に検討することをおすすめします。
自己破産の相談でよくある質問
自己破産の相談に関して、よくある質問と回答をまとめました。
自己破産とはどういう手続きですか?
自己破産とは、借金などの債務負担を解消するため、裁判所に申し立てておこなう手続きです。
財産を処分して債権者に配当した後、原則として残った債務全額が免除されます。
特に、収入に比べて債務が非常に多く、完済が不可能な方には自己破産がおすすめです。
ただし、自己破産をすると財産が処分されるほか、ローンやクレジットカードを利用できなくなる、連帯保証人に対する請求がおこなわれてしまうなどのデメリットがあります。
弁護士のアドバイスを踏まえつつ、メリット・デメリットを比較したうえで、自己破産をすべきかどうか適切に判断しましょう。
自己破産をすると財産はどうなりますか?
自己破産が認められると、原則として価値がある財産は没収・処分されます。
たとえば、自宅の土地・建物、自動車、現金、預貯金など幅広い財産が処分の対象です。
ただし、99万円以下の現金や生活必需品など、最低限の生活に必要なものは処分の対象外となります。
自己破産は財産を全て失うというイメージを持つ方は少なくありませんが、生活できない状態に陥ることはありません。
自己破産後の生活への影響にはどんなものがありますか?
自己破産をすると、価値ある財産は処分されます。財産を失えば、生活水準が低く抑えられてしまうことは避けられないでしょう。
自己破産の手続き中は、士業や警備員など特定の仕事に制限が生じます。
ただし、大半の方は制限の対象外です。また、制限の対象となる仕事に就いている方も、免責が確定すれば制限が解除されます。
また、自己破産をすると個人信用情報機関に事故情報が登録され(いわゆるブラックリスト入り)、その後一定期間はローンの契約やクレジットカード作成などの審査に落ちる可能性が高まります。
ほかにも、借り入れをする際に家族や知り合いを保証人としている場合、破産者の代わりに責任を負うこととなるため、迷惑がかかってしまう点にも注意が必要です。
まとめ
自己破産の主な相談先は、弁護士と司法書士です。
自己破産をスムーズに進めるためには、代理人として対応してもらえる弁護士への相談をおすすめします。
実績や費用などを確認したうえで、信頼できる弁護士に依頼しましょう。
多くの法律事務所は、債務整理について無料相談を受け付けています。
無料相談を通じて複数の弁護士に相談し、自分に合った弁護士を見つけると失敗のリスクが軽減されます。
無料相談の時間や回数が制限されている場合は、事前に質問事項や必要な情報をまとめておくとよいでしょう。
時間内にスムーズに相談でき、有益なアドバイスを受けられます。
借金問題で困っている方は、自分に合った弁護士を探し、相談・依頼してみてください。
|
債務整理について弁護士に相談する 電話相談可・初回面談無料・完全成功報酬 の事務所も多数掲載! |
|
|---|---|
| 北海道・東北 | 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 |
| 関東 | 東京 | 神奈川 | 埼玉 | 千葉 | 茨城 | 群馬 | 栃木 |
| 北陸・甲信越 | 山梨 | 新潟 | 長野 | 富山 | 石川 | 福井 |
| 東海 | 愛知 | 岐阜 | 静岡 | 三重 |
| 関西 | 大阪 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 奈良 | 和歌山 |
| 中国・四国 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 |
| 九州・沖縄 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |